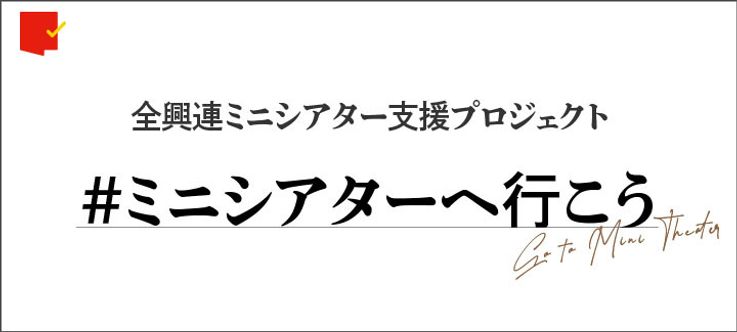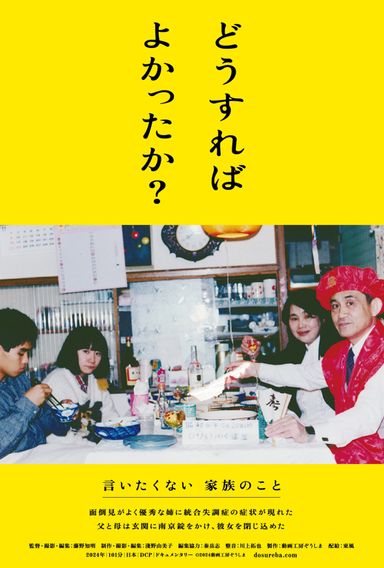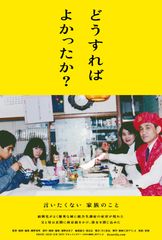シネマ・ロサ支配人が明かす、『侍タイ』『ベビわる』大ヒットの舞台裏とインディーズ映画が持つ“魔力”「思いがけないヒット作が出るのは映画業界ぐらい」
「若い人たちがどうしたら興味を持ってくれるのかを、まだまだ考えていかなきゃいけない」
ところで、シネマ・ロサがIFSを始めたそもそものきっかけはなんだったのか?当時を振り返る矢川支配人の言葉からは、ミニシアターの現状や存亡に関わる様々な事実が浮かび上がってきた。
「2019年の7月19日にグランドシネマサンシャイン 池袋さんが、2020年の7月3日にTOHOシネマズ 池袋さんがオープンし、池袋エリアに都合16もスクリーンが増えました。その報せを聞いた時に、メジャー作品がシネマ・ロサに回ってこなくなったり、番組を組む自由度が落ちるだろうと危惧して、なにかシネマ・ロサにしかできない柱になるような企画がないといけないなと考えたのが始まりです。そこから、以前は年に1、2作品しか上映していなかった自主映画を通年で力を入れてやろうという話になり、担当者を立ててロサ独自のプログラムとしてやるようになってから7年が経ちました」。
その決断が『侍タイ』や『カメ止め』の大ヒットという形で実を結んだのだが、IFSが軌道に乗ったわけではない。「すべての作品にお客さんが入ったら、こんなに楽な商売はないですよ!自主映画は認知度が当然ないし、始めたころよりは『シネマ・ロサのインディーズ作品なんですね』ってお客さんや業界の方たちにも知っていただけるようになったけれど、いまでもまだまだ大変です」。
客足が伸びないのは、池袋という地域の問題と自主映画をとりまく閉塞的なイメージが関係していると矢川支配人は見ている。「一般のお客さんは『池袋?遠いな~』『行きづらいな~』ってまず思うし、『池袋でレイトショーを観たら終電がなくなっちゃうから物理的に無理』っていう方も結構います。しかも、自主制作映画は身内的なノリがどうしても感じられるから、映画を作っているスタッフ、キャストと同年代の若い人たちこそ敬遠しがちで。観にきてくれるお客さんの年齢層は実際けっこう高いので、普通の若い人たちがどうしたら興味を持ってくれるのかをまだまだ考えていかなきゃいけない。そこが悩ましいところではありますね」。
だが、そこには若い人たちがミニシアターや自主映画に足を運ばない決定的な問題があると矢川支配人は強調する。「いまの20代の人たちって、生まれて初めて行った映画館がシネコンなんです。私はいま50手前の年代ですけど、僕らの若いころは新宿や渋谷に電車に乗って映画を観に行くのが普通でした。でも、いまの子たちは電車に乗る必要がない。お父さんやお母さんに車で乗せてもらって観に行ったり、友だちと自転車で行くエリアのシネコンで上映しているのが自分の知っている映画のすべて。そのそばにミニシアター系の作品が存在しているのに、未知の領域に足を踏み入れない。幼少期の映画鑑賞が原体験だから、それを拭いきれないところがあるのでは、と」。
「『侍タイ』や『カメ止め』のようなヒット作が生まれることもあるので、やり続けることが大事」
コロナ禍で映画を配信で観る人たちが急速に増えたことも否めないが、矢川支配人は大きな変化が見られる観客の動向には期待を寄せる。
「1980年代や90年代のミニシアターブームの時は1人で映画を観る人が多かったような気がするんですけど、いまの若いお客さんは友だちを誘って観る傾向が強い。それぞれの趣味嗜好で最初は1人で観ても、すごくよかったから友だちを誘ってもう一度観に行く人も多いし、おもしろさや価値観を共有できる作品が好まれる傾向が強くなっているので、ミニシアター系からそういった作品が出てくるといいですね。彼らはお客さんを増やしてくれているわけだし、シネマ・ロサに来て、『へ~、こんな映画館もあるんだ!』って、目新しく感じてくれる可能性もありますから(笑)」。
とはいったものの、現在、全国の映画館のうちミニシアターが占める割合はわずか5%。95%がほぼ同じ映画を上映しているシネコンになるわけだが、そこでミニシアターを運営していくことの意義を矢川支配人とはどのように考えているのだろうか?
「映画には扱うテーマが違う、いろいろな国の作品があるので、今後も多種多様な作品をできるだけ数多く提供していきたいと思っています。地方には成り立ちやロケーションも含めて、当館とは比較にならないぐらいのご苦労を強いられながら頑張っていらっしゃるミニシアターさんもありますし、我々も当たる映画ばかりをやっているわけではないけれど、『侍タイ』や『カメ止め』のようなヒット作が生まれることもあるので、やり続けることが大事だなと。ちょっとやってダメだからって方向転換するのはよくないですね。ある程度の長いスパンで、本当に細々とやっていくしかない。その結果、種々雑多の映画をやるのがシネマ・ロサらしさになってきたし、IFSをやってきたこともあって、日本映画の上映作品の割合が、以前の4割から8割に変わった。自主映画に力を入れていることも、お客さんだけでなく、業界の人たちにもチェックしていただけるようになって、新作を『ロサさんにお願いしたい』というお話も近年では増えてきました」。