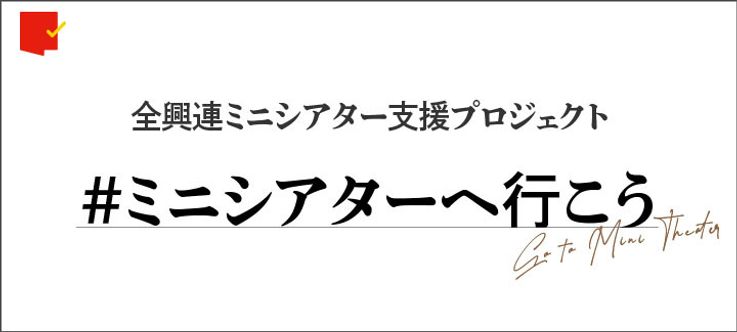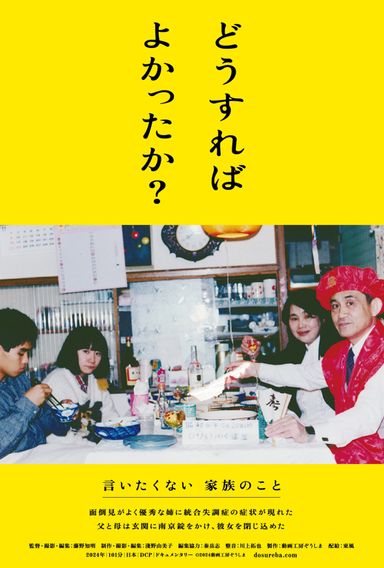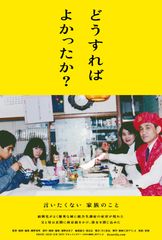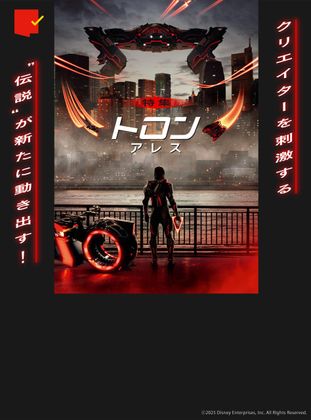シネマ・ロサ支配人が明かす、『侍タイ』『ベビわる』大ヒットの舞台裏とインディーズ映画が持つ“魔力”「思いがけないヒット作が出るのは映画業界ぐらい」
「若い人材がミニシアターの未来を担うことになると思っている」
話の流れで最後に聞いてみた。矢川支配人はなぜ映画の道を志すようになったのか?突き動かすものはなんなのか?
「僕がシネマ・ロサの支配人になったのは11年ぐらい前です。学生時代は別の映画館でバイトをしていたんですけど、25年ぐらい前に先ほど話したIFSの担当をしてもらっている方に拾ってもらって(笑)。2000年台のはじめのころまで、ロサはフランス映画の特集とか配給をよくやっていて、元々私もそっち界隈が好きだったんですが。その手の興行が難しくなってきて邦画に目を向けた時に、テアトル新宿さんやユーロスペースさん、いまはもうなくなってしまった中野武蔵野ホールさんにお客さんとして観に行って、こういう作品も映画館でやれるんだっていうことを知ったんです。その時の楽しかった思い出が僕の中に残っていて。当時、自主映画を引き受けられる映画館が少なくなってきていたこともあって、『ロサで自主映画をやってみるか』という方向に自然になれたんです」。
そう言及したうえで、「僕はこれから映画館の業務に携わる人たちに『よその映画館にもっと映画を観に行け!』って強く訴えかけたい」と矢川支配人は強調する。「悲しいかな、ウチもそうですけど、いまの映画館のスタッフは本当に映画を観ない。自分が働いている劇場の映画も観ないから、『そんなに忙しいの?』って思うんだけど、よその映画館に映画を観に行くことがいかに重要か、 勉強させてもらえるのかということをもっと知ったほうがいい。よその劇場さんがどんな取り組みをしているのかは直に見ないとわからないし、自分の劇場の中だけで学ぶのは限界がありますからね」。
そこにこそ、ミニシアターを取り巻く悩ましい現状がくっきりと浮かび上がる。「ミニシアターの存亡について語られる時に、DCP映写機を買い替えるお金がないからクラウドファンディングをやらなきゃいけないといったハード面で一括りにされることが多いけれど、人材不足、人手不足の問題も結構大きくて。これも、先ほどの若い人の原体験がシネコンだからということと関係しています。なぜなら、彼らは映画館で働きたいと思ったら、自分の知っているシネコンに応募してしまうから。自分の知らないお店では働きたくないですからね(笑)。しかも、いまお話したように、映画館で働くようになった若いスタッフは他所に映画を観に行かない。そうすると、『この映画をどんなふうにお客様に届けたらいいのか?』という発想が育まれにくくなるんです」。
それが実際に形になって表れている。
「僕は、この“映画館のメンツが変わらない問題”を結構前から言っているんですけど、ミニシアターの方々は特に20年ぐらい変わっていなくて、従業員の高齢化も進んでいます。だからこそ、20代、30代の若い人たちに訴えたい。ミニシアターの仕事は大変だけれど、映画が好きな人にはこのうえない職場で、ほかではできない楽しい体験ができるということを。シネマ・ロサでは常にバイトも募集しています。若い人材がミニシアターの未来を担うことになると思っていますから」。
取材・文/イソガイマサト
※高石あかりの「高」ははしごだかが正式表記