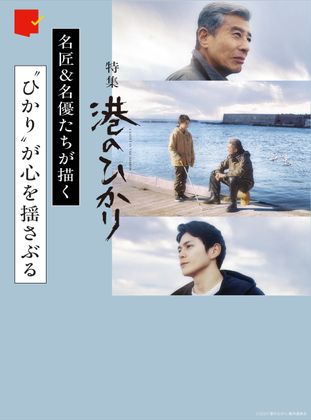『鬼才の道』ジョン・スー監督が語る『返校』での成功と葛藤、そして創作者としての今後【インタビュー後編〈監督編〉】
端々に登場する“キリン”と、遊び心満載なミュージックビデオの仕掛け
ジョン・スー作品に一貫する「遊び」のひとつが、短編時代から全作品に出現している“キリン”の存在だ。「大した意味はありません。やはり遊び心です」と笑った。
「大学院生時代に『匿名遊戯』という短編を撮ったとき、ハッカーがネット掲示板を攻撃する話なので、変な動物の写真を出してハッカーの侵入を示すことにしました。そのときに“キリンがぴったりだ”と思ったのが始まりで、その後も継続的に登場させるようになりました。MVや広告、AFK PL@YERS、 金馬奨のCMにもキリンが出てきています」
映画の場合は、「シリアスなシーンには登場させない」という基本ルールがあるという。しかし、それゆえに全編がシリアスな『返校』では苦労したそうだ。
「ルールに従うとひとつも出せない(笑)。最終的に3~4か所でキリンを出しましたが、最後のひとつはラストシーンの教室の落書きです。それなら合理的かつ違和感がないだろうと。見つけにくいのは、ファン・レイシンの自宅にある古い絵。明の時代、鄭和という冒険家がアフリカからキリンを連れて帰り、皇帝に献上したという伝説を描いた絵です」
『鬼才の道』には、もはやスー監督も把握しきれていないほど大量のキリンが登場している。美術スタッフに「キリンを用意しておいて」と頼んだところ、知らないうちにキリンの小道具が置かれており、逆に自分で探さなければいけないこともあったそうだ。
ちなみに、最も難易度の高い“キリンポイント”は主人公の女性幽霊が生前に通っていた大学の名前。「台湾語でキリンは『長頸鹿(チャンジンルー)』ですが、大学の名前が『常景禄(チャンジンルー)』なんです(笑)」
「遊び」といえば、エンドクレジット後に『愛的視線』のMVが何度も繰り返されるのもそのひとつ。「せっかく3分くらいのMVを作ったのに、本編では少ししか使えなかった。もったいないので、これを使って観客の皆さんと遊びたいと思いました」という。
「マーベル映画を観ていると、エンドロールの後になにかあるはずだと思い、最後まで帰らない観客が多いので、同じことをしたかったんです。フルで流すのは長すぎるので、観客が『これで終わりかな?』と思い、座席を立った瞬間にまた始まる……というのを繰り返しました。いつ帰っていいのかわからなくしてやろうと思って(笑)」
実際に台湾の映画館では、帰りかけた観客が再び立ち止まり、そのままスクリーンを眺める光景があった。これは劇場ならではの体験で、監督も「映画館で観る前提の編集だった」という。「Netflixだとクレジットの途中で再生をやめる人も多いだろうし、意図した効果がどれだけ損なわれるかは予測できなかった。そこは受け入れるしかありません」
台湾映画界の異端児
スー監督は『返校』で台湾現代史を正面から描き、ドラマ「聖筊(原題)」では占いに使われる「ポエ」とSFを融合し、『鬼才の道』では個人的な物語と幽霊・妖怪文化をミックスした。一作ごとに台湾の歴史や伝統、文化を再解釈してきたが、本人は意外にも「台湾文化を映画で表現しよう、という意識があるわけではない」という。
「僕は台湾人ですが、台湾文化とはなにかがよくわからないところがあります。むしろ、海外の皆さんのほうがよく知っているのではないかと思うほど。国の文化というよりも、この地で生まれ育つなかで触れてきたものが自分の映画を形づくっていると感じます」
アメリカやヨーロッパの映画、日本のポップカルチャーに大きな影響を受けてきたスー監督は、意図せずとも日常的に接してきた自国の文化を咀嚼し、独自の手つきで映画にしてきた。巨大な題材にパーソナルな問題意識を織り込む方法は、ハリウッドで活躍するフィルムメイカーたちが、有名フランチャイズやスタジオ映画の枠組みで個人的なストーリーを語ろうとしていることにも通じるだろう。
取材中、筆者が「台湾映画界の異端児」と形容したことに、どうやらスー監督は納得してくれたようだ。「もしかすると僕は、これまでもずっと異端児のような存在だったのかもしれません」という。
「台湾映画の主流と好みが合わないことへの困難を感じたことはあります。では、僕のような監督が台湾の映画市場でいかに生き残り、いかに独創的な映画を作るのか。決して見下すのではなく、僕にはメインストリームの台湾映画を作ることはできません。過去には挑戦したけれど、その才能はないと思う。活躍している人たちを心から尊敬しています」