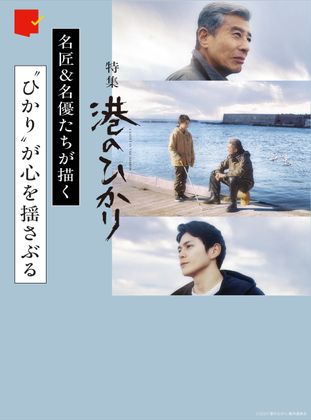『鬼才の道』ジョン・スー監督が語る『返校』での成功と葛藤、そして創作者としての今後【インタビュー後編〈監督編〉】
自身の経験が反映された、『鬼才の道』のプレッシャー表現
「自分の手元にあるよりも、父親のほうが喜ぶのではないか」。『返校』での受賞以来、贈られた賞状やトロフィーなどはすべて両親のもとに送っている。実家の棚には、それらがずらりと飾られているそうだ。
「まるで自分の墓場か記念碑が建っているかのよう。実家に帰り、それを見るたびに言葉にできないプレッシャーを感じます。いつか、すべてが崩れてしまうのではないかと」
こうした不安とプレッシャーは、『鬼才の道』にそのまま反映された。ワン・ジン演じる主人公の女性幽霊は、家族の賞状やトロフィーなどが飾られている棚に押しつぶされて命を落とすが、劇中の棚は実家にあるものをそっくりに再現している。
「プレミア上映に家族を招待したとき、両親たちの反応が怖かったし、本当に心配でした。『“よく知っているもの”が出てくるけれど、あまり考えすぎないで』と何度も話しました(苦笑)」
また、登場人物の全員に自らの性格や経験を注ぎ込んだ。主人公の女性幽霊は、「実際はいろんなことを成し遂げてきたのに満たされず、自分の価値を認められない」自信の欠如が表れているという。また、元スター幽霊のキャサリンは監督本人により近いそう。「常に人目にさらされることへの不安、それでも全力を尽くさなければならないという義務感による過剰な努力。まさに僕自身です」と語った。
劇中には、幽霊たちがプレッシャーにさらされるシーンがいくつもある。例えば、一同がホテルでホラー映画を観ている場面はそのひとつだ。「みんなが想像しているほど自分たちは怖くない、映画みたいに怖くなるのは無理だと思っているんです」
台湾には「幽霊は人間と一緒に映画館で映画を観る」という怪談があり、監督いわく「幽霊たちはホラー映画に興味津々。自分たちがどう見られているのかを気にしている」という。それゆえ初期段階の脚本では、この場面はホテルでなく映画館が舞台だったそう。本当は映画館で撮りたかったというが、残念ながら予算の都合で実現しなかったそうだ。
映画の終盤、キャサリンとジェシカの直接対決を幽霊たちが画面越しに応援しているシーンでは、彼らにさらなるプレッシャーがのしかかる。
「人間を怖がらせようとしている幽霊たちを誰もが見つめている。あらゆる期待を背負いながら、同時に全員を失望させてしまうかもしれないプレッシャーがそこにあります。だからこそ、彼らは必死にやり切ろうとする。ただし観客がいなくなったあとは、もはや他人が見ているかどうかなど気にならなくなるのです」
「遊び心」への回帰
『返校』のあと、自らの本質と経験にとことん向き合ったスー監督は、自分が本当に描きたかった内容と表現を『鬼才の道』に詰め込んだ。2022年にオムニバスのドラマシリーズ「你的婚姻不是你的婚姻(原題)」の一編『聖筊(原題)』を手がけ、低予算のコメディ路線に回帰したことも助けになったという。
「昔の創作スタイルに少しだけ戻れたことで、自分がどんなクリエイターなのかをより理解できた気がしました。あの作品で一種の癒しを得られたことで、『鬼才の道』で自分のスタイルに向き合う準備が整ったのだと思います」
創作のキーワードは「遊び」だ。ひとりの観客としても「シンプルな物語を、シンプルではないやり方で描いている作品が好き」だという。エドガー・ライトや宮藤官九郎のほか、コーエン兄弟、ポン・ジュノらを例に挙げた。
「僕も創作のなかでは常に面白い要素を探していますし、いつも遊び心を持っていたい。脚本を書く時は、物語とは別に“なにをどう遊ぶか”を考えていますし、俳優やスタッフの面白いアイデアもすぐに採用します。映画づくりは本当に大変で、ものすごく疲れること。だからこそ、プロセス全体をできるだけ楽しく遊びたいんです」
創作における「遊び」のスタイルは、子どもの頃によく読んでいた日本のギャグ漫画などから影響を受けている。小学校時代は教科書の内容をパロディにしたギャグ漫画を描き、クラスメイトを笑わせていたそうだ。
「孔子があれこれ教訓を説くけど、本人は一切実践できなくて弟子からバカにされる話とか(笑)。新学期になると国語の教科書を熟読し、物語をどう面白くぶち壊すかを考えていました。友達は僕の漫画を教科書よりも先に読んでいて授業中にニヤニヤしているけど、先生からすると意味がわからない(笑)。そういう状況も含めて楽しかったです」
こうしたパロディの精神は、『返校』よりも以前、映像制作集団「AFK PL@YERS」として手がけた短編コメディ作品や、ビデオゲームの映像を使用して制作したマシニマ作品などに直接表れている。大学時代に自ら制作したゲームも方向性は同じだったそうだ。
「結局のところ、僕は小さい頃から同じことを続けていて、ただ形が変わっただけなのだと思います。シリアスなものをぶち壊す、“破壊”の感覚を面白がっているところがあるんです」