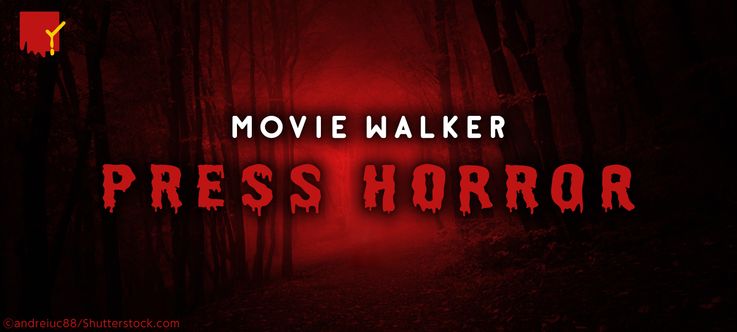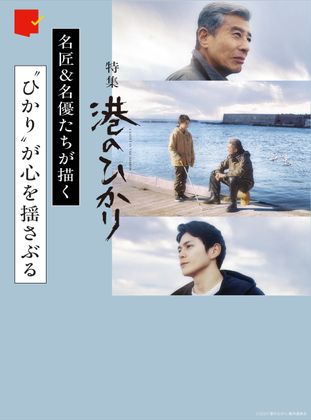笑い泣き必至のホラーコメディ『鬼才の道』ジョン・スー監督が明かす、傑作誕生までの道のり【インタビュー前編〈作品編〉】
台湾映画らしくない「コメディ」を
『返校』ではシリアスな物語をじっくりと描いたスー監督だが、短編時代から多数のコメディ作品を手掛けてきた。敬愛するクリエイターは、『ベイビー・ドライバー』(17)のエドガー・ライトや日本の宮藤官九郎ら。「本当はテンポの早い作品が好み。台湾映画のリズムはちょっと遅い」と言い、今回は自らの理想的なスピード感にこだわった。
映画を盛り上げるのは、ビッグバンド・ジャズやスカの要素を大胆に取り入れた劇伴音楽だ。作曲は『返校』をきっかけに台湾映画界で最も忙しい作曲家の一人となったルー・ルーミン。スー監督は「この数年間、彼は本当に大変だったはず」とねぎらう。
『返校』のほか、『疫起/エピデミック』(23)や『流麻溝十五号』(22)などのシリアスなドラマ作品で叙情的な音楽を手掛けてきたルーミンだが、本作では「鬼才大BAND」を率いて新境地を開拓。豪華なバンドサウンドは映画館の音響でこそ真価を発揮する。
「台湾のコメディ映画はいかにも喜劇的な音楽が多く、こうした方向性は珍しいと思います。ルー・ルーミンは厳粛で深みのある音楽を作ることも多いですが、本人はユーモアたっぷりで、人をからかうのも大好き(笑)。あまり知られていないだけで、本当はこの映画にぴったりの人物です」
クライマックスのイメージはコンセプトムービーの時点からあったといい、音楽の方向性はその構想から逆算して決まっていた。メインテーマも当時と同じメロディだが、今回はより豪華なアレンジが施されている。
多忙なルーミンに、監督は「今回はプレッシャーを感じず、自由に楽しんでほしい」と伝えたという。ところが、チェン・ボーリン演じるマコトが歌い踊る挿入歌「愛的視線」の作曲は難題だった。「彼は抜群のセンスを持つプロの音楽家。だからこそ、あまりよくない曲を作るのは大変だったのでしょう」とスー監督は笑う。
「愛的視線」のミュージックビデオは劇中の見どころのひとつ。90年代に絶大なる人気を博した金城武の「標準情人」へのオマージュなど、懐かしさに満ちた映像は当時を知るファンの間でも話題を呼んだ。
「もしもマコトが華語ポップス全盛期の90年代を生きていたとしたら。“誰にでもチャンスがあった時代、才能に恵まれず無名のまま命を落とした歌手”という設定をひらめき、MVを作ろうと思いました。当時を思わせる、チープでおもしろいMVを。あの撮影をした日は、誰にとっても製作期間で一番楽しい一日だったと思います」
「台湾ホラー」の常識を覆す
スー監督は1981年生まれで今年44歳。現在の台湾映画界について、「もともと小さい市場でしたが、ますます縮小が続いています」と危機感を語る。
「僕たちの世代や、さらに若い観客はハリウッド映画を観て育ちました。台湾映画は“低予算でチープ、エンタテインメント性に欠ける”というイメージがあり、観客にあまり信頼されていません。台湾映画を好んで観る台湾人はさらに減っているように思います」
スー監督は「市場が小さいほど保守的になり、安全なジャンルや題材の映画しか作れなくなる」と言うが、実際に2010年代後半から台湾ではホラー映画の製作本数が急増。そのなかでジャンルの“お約束”を逆手に取り、予想外の展開と笑いに転化した本作は、まさに独創的な方法でブームに切り込んだ一本だった。
「この映画の公開後、観客があまりホラー映画を怖がらなくなったという話を聞きます。ホラー映画を撮っている友人には、『なんて映画を撮ってくれたんだ』と怒られました(笑)」
『鬼才の道』は台湾のみならず海外の映画祭でも高い評価を受け、アメリカでの評判が特によかったという。監督が驚いたのは、観客の反応が国境を超えて共通していたこと。「笑ってもらえるところはもちろん、泣くところも同じ。もっと文化的なギャップがあるのかなと想像していました」という。
日本での劇場公開にあたり、監督は「小さい頃から大好きだった、日本のポップカルチャーの影響がとても強く出た映画です」と語った。「だからこそ、日本の皆さんの感想がとても気になっていました。楽しんでもらえることを願っています」
『返校』で台湾や日本の観客の心をつかんだジョン・スーは、『鬼才の道』でホラージャンルの常識を覆し、“台湾映画”のイメージを超えてグローバルな人気を獲得する作品を完成させた。その骨太な創作を支える根源や、自身の現在地とは――。インタビューの後編〈監督編〉では、フィルムメイカーとしての核心により深く迫っていく。
取材・文/稲垣貴俊