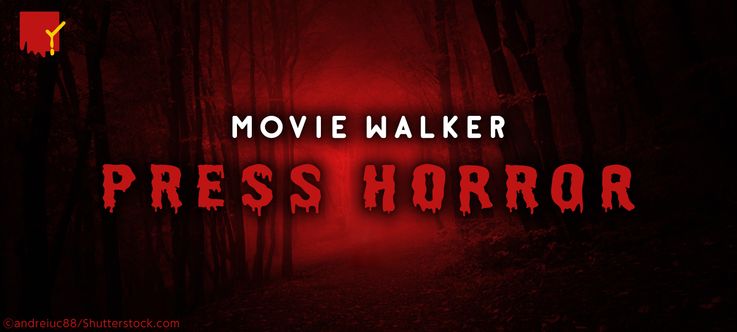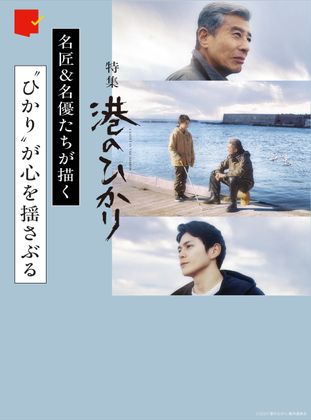笑い泣き必至のホラーコメディ『鬼才の道』ジョン・スー監督が明かす、傑作誕生までの道のり【インタビュー前編〈作品編〉】
“見られること”のホラーコメディ
消滅を回避するためには、自分は怖い幽霊だと証明し、周囲から注目と評価を得なければいけない。常に一定の基準を満たしていなければ、容赦なく現世から抹消されてしまう――。
「なぜ他人から承認されなければ、“自分には生きる価値がある”と実感できないのか」。本作のテーマは、スー監督にとって非常に個人的なものだった。創作は常に「自分自身が共感できる要素を見つけること」から始まるというが、今回はそれこそが全編を貫く主題となったのだ。
「幽霊の物語を通して、普遍的なテーマや感情、そして皆さんが共感できる物語を作りたいと考えていました。現在、世界ではSNSで注目されること、アテンションを集めることが重要なトレンドになっています。けれども、“見られる”とは一体どういうことなのか。役者であれYouTuberであれ、他者の注目を集めるため必死に努力しているのは幽霊と同じです」
主人公の名もなき幽霊も、霊界のスターやマネージャーたちも、ルールに翻弄されながら他者に注目されようと必死に生きている。死後も身体を張って奮闘する幽霊たちの物語を、スー監督はスピード感と遊び心――これは本人のキーワードでもある――に満ちたスラップスティック・コメディとして演出した。
「特別な能力を持たない彼らは、影でとんでもない苦労をしています。映画の裏側にキャストやスタッフの大きな努力があるのと同じように、幽霊たちも必死に練習し、一生懸命にリハーサルしている。あくまでも人間と同じような存在として描きたいと思いました」
モチーフとなったのは台湾に古くから伝わる幽霊・妖怪文化だ。脚本はオリジナルだが、劇中に登場する幽霊の多くは実在の怪談や伝説に基づいている。「新しい怪談を創作するのは難しいですが、台湾にはたくさんの怪談があります。伝説を網羅した百科事典のような本をめくりながら題材を探しました」
「達成への不安」を抱える、自信のない幽霊たち
“消滅”を回避したい主人公の女性幽霊、うさんくさい芸能マネージャーのマコト、元トップスター幽霊のキャサリン、そしてキャサリンのライバルである現スター幽霊のジェシカ。個性あふれる彼女たちに共通するものは「達成への不安」だ。
「主人公の幽霊は自分に自信がなく、ひとつうまくいかないことに苦悩しています。キャサリンは優秀ですが、いつか実力が及ばなくなることを不安に思っている。そして、マコトはなにひとつ成功していませんが、主人公とは異なり最後まで諦めません。彼は非常に楽観的で、自分は失敗していないと信じている。そういう人は最も思いやりがあり、弱く傷つきやすい人々にも優しさと希望、慰めをもたらすと思うのです」
主な出演者に起用されたのは、いずれも台湾映画界で屈指の人気俳優たちだ。主人公の女性幽霊を演じたのは、『返校』や『赤い糸 輪廻のひみつ』(21)のワン・ジン。再びタッグを組んだスー監督は、自らのテーマを託すうえで欠かせない存在だったと語る。
「彼女は『返校』で初めて大作映画に主演し、大きな注目を浴びました。あの時、僕自身も大きな注目を集めるようになった。“注目される”とはどういうことで、人間にどんな影響を及ぼすのか――実は、この映画には僕自身の経験が多分に反映されているのです。同じ経験をしたワン・ジンは、この物語を最も理解できる人だと思っていました」
マコト役には『藍色夏恋』(02)で知られ、日本でも活動したチェン・ボーリン。キャサリン役はチャン・ロンロン、ジェシカ役はヤオ・イーティーが演じた。ボーリン&ロンロンのほか、コウジ役のソーソー・チェンはコンセプトムービーから続投。主要キャストは脚本の執筆段階でほぼ決まっていたため、スー監督は本人たちの性格や個性を役柄に反映したという。