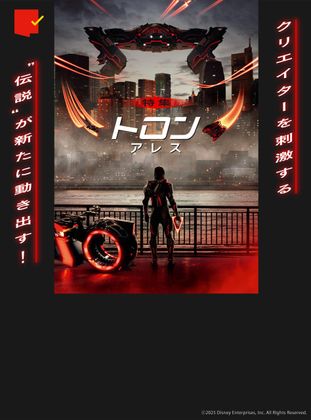「記憶を次の世代に継承することも本作のテーマのひとつ」(奥浜)
奥浜「劇中でも、悦子や佐知子を含め、悦子の夫や義父、登場人物たちの『変わっていかなければいけない』というセリフがすごく印象的でした。戦後という時代のなかで、誰もが感じている大きな変化の波と、自分自身の内側から芽生えてくる、自分が変わらなきゃいけないと思う、精神的な変化の両方がありますよね」
モモコ「アメリカに行けば、なんとかなると話す佐知子も、内心では不安を抱えていて、だけど、無理やりにでも希望を持たないといけないという」
奥浜「口にすることで、自分を鼓舞しているという感じでしたね」
モモコ「そうなんです。自分自身に一生懸命言い聞かせているような印象で、せつなさもすごく感じましたね。戦後の女性って、そうしなければ生きづらい世の中だったのかなあと。そんな弱さも含めて、強いなあって思いました。いまだって、古い自分を捨てて、いつでも変わることはできるんだと勇気づけられたような気がします」
奥浜「この物語は、悦子がニキに対して、自分の過去を話していくことで展開していきます。母の半生を作品にしたいと考えるニキという娘の立場の目線で、なにか感じたことはありましたか?」
モモコ「ニキは作家を目指しているという設定なので、長崎にいた母親がどんな人生を送ってきたかを知りたいっていうのもあるし、イギリスで生まれた自分のルーツを知りたい、悦子から生まれてきた自分のことも、もっと知りたいっていう気持ちもあったのかなって思いました。実は私も、すでに他界している祖母が生きていたころ、ニキみたいに、どういうふうに生きてきたのかを聞いたことがあって」
奥浜「どうして、おばあさまに過去の話を聞いてみようと思ったんですか?」
モモコ「戦時中や戦後のことって、教科書にいくらでも書かれているんですけど、私は祖母自身の言葉で、どういう現実があったのか、どんな生き方をしていたのかを知りたかったんです。祖母から話を聞いたことで、祖母もかつては一人の少女で、いろんな不安を抱えていて、それでこういう性格になったんだとか、いろいろ知ることができてよかったです。カズオ・イシグロ作品も、回想や記憶が大きなキーを握っていると思いますが、私もそういう一人称で語られる、その人の歴史について興味があるタイプですね」
奥浜「それを自分の作品に書き残しておきたいと思いますか?」
モモコ「はい、自分はそういうところがあって。私はBiSHというグループに8年間所属していまして、ある日、プロデューサーから、解散を提案された日があったんですね。それで、その日から、日記形式で解散までの日々を書き残そうと思ったんです。その3年半の日々の記録は『解散ノート』というタイトルで1冊にまとめて、出版しました。アーティストの方が、解散後に活動当時のことを書くケースはけっこうあると思うんですけど、その日のうちにリアルタイムで書くドキュメンタリーと、後日、人が話すことは別物だと私は思うので。
だから、本作だと、悦子が語ることは現実のとおりではない、という部分も含めて観るのがおもしろいところなのかなと思っていて。やっぱり人は自己防衛的な気持ちを持っているから、自分にとって痛い部分は、記憶の中で無意識にねじ曲がっていて、違う記憶になったり、美しくなっていたりする。どちらにもそれぞれのおもしろさがあるなと」
奥浜「そうですよね。カズオ・イシグロさんは1954年長崎県出身で、本作はフィクションですが当時の長崎のことを小説にして、それを石川慶監督がいま映像化し記憶をしっかり残しておく。そうやって次の世代に引き継いでいくことの大切さも、この作品のテーマのひとつかなと思います」
モモコ「カズオ・イシグロさん自身、5歳の時に、両親と共に長崎からイギリスに渡った方で。彼は5歳までの記憶を美しいまま留めたかったがゆえに、その後、あまり日本や長崎に帰らなかったという話を読んだことがあります。私も幼いころのことをぼんやりとは覚えていますけど、そういう記憶自体が、実体験よりもいまの私を作っているなと感じる部分はあります。この作品が映画化されることは、観た人たちが自身のルーツを振り返るきっかけにもなるかなと。私も母親に対する見方を見直さなきゃいけないなと思いましたし、いろんなことがいまにつながってくるのかなと思います」

■衣装協力(モモコグミカンパニー)
ブラウス・スカート・シューズ/Randa/03-3406-3191、ピアス/STELLAR HOLLYWOOD/03-6419-7480