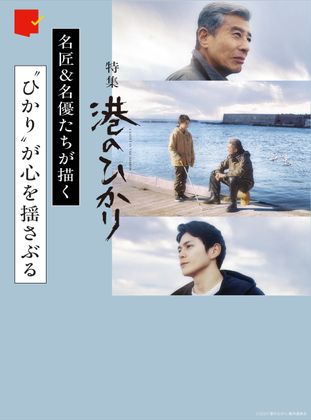『エターナル・サンシャイン』から始まっていた『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』への道。ケイト・ウィンスレット渾身の一作の制作秘話とは?
華やかなトップモデルから、「撮られる側ではなく、撮る側でありたい」と写真家に転身。20世紀を代表する報道写真家となったリー・ミラーの数奇な人生を描いた『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』が5月9日(金)より公開される。昨年、話題となった『シビル・ウォー アメリカ最後の日』(24)の主人公のモデルとなったことからも、“使命感に突き動かされた、恐れ知らずのジャーナリスト”のアイコン的存在だとわかるだろう。本作は、戦争の足音が近づいてくる1938年、写真を撮り始めたばかりのミラーが戦争勃発と共に従軍記者への道を突き進んでいく、その10年間に焦点を当てて、いかに彼女が唯一無二の報道写真家になり得たのかを映しだす。監督のエレン・クラスに映画化までの道のり、撮影の舞台裏を聞いた。
「『エターナル・サンシャイン』の現場で、ケイトを“リー”と呼んだりしていたんですよ(笑)」
本作は、リー・ミラーを演じるケイト・ウィンスレットが8年以上の月日を掛けて実現した渾身のプロジェクトだというが、実は映画化の萌芽はそれよりずっと前にあったようだ。『エターナル・サンシャイン』(04) の現場で撮影監督としてウィンスレットと出会ったクラスは、「撮影していた2002年にケイトと知り合って以来、長く友人関係を築いて来ました。実は『エターナル~』の現場で、“モデル時代のリー・ミラーとケイトって似ているよね”という話になって、みんなでケイトを“リー”と呼んだりしていたんですよ(笑)。その時にケイトはすでに、“彼女のことを映画化するには、誰が権利を持っているのかな?”と発言していました。詳しいことは聞かなかったけれど、どうやらそこから彼女は権利関係を調べていたらしいです」と明かす。
それから10年以上経った2015年、クラスはウィンスレットから「リー・ミラーの義理の妹が使っていたテーブルを買った」と聞いたという。「もしかしたらピカソやポール・エリュアール、マン・レイほか、シュルレアリスト派のアーティストたちが座ったテーブルかもしれない、という話で盛り上がりました」とその時の様子を教えてくれる。義理の妹とはつまり、本作でリー・ミラーが結婚するローランド・ペンローズの妹のこと。オークションで手に入れたテーブルが縁を運んでくれたかのように、ウィンスレットはリー・ミラーの息子、アントニーから映画化権を手に入れていた本作のプロデューサーの一人、トロイ・ラムと知り合うことになる。まさにウィンスレットの想いが運命を引き寄せたのだろう。
そのトロイ・ラムとウィンスレットを中心に開発された脚本を、クラスが手にしたのは2018年。ウィンスレットは脚本を手渡しながら、「あなたって結構ハイエンドなテレビ番組やCMを作っているわね。実は『リー・ミラー』の脚本があるのだけれど、この作品で初の長編監督に挑戦してみない?」と持ち掛けたという。その時の心境をクラスは、「私は元々映画畑の出身だし、文化的なアイコンであるリー・ミラーについて自分の手で映画にできるなんて、まるで夢のよう。ついに自分の夢が叶うのかと、ワクワク大喜びしながら引き受けました」と思い返す。
「それまで描かれてこなかった彼女の側面を語りたいと思いました」
本作が大きな感動をもたらす理由に、若いジャーナリストが老齢の彼女にインタビューし、そこから過去にさかのぼるという回想形式を取ったことが挙げられる。その構造は、終盤、意外な驚きと感動をもたらすことに。非常に功を奏した、その形式や構成は、「最初に手渡された脚本にはなかった」とクラス。「おもしろい人物像としてのリー・ミラーのいろんな側面はすでに脚本に入っていましたが、いわゆる普通の伝記映画的な構造でした。彼女の人生にいつなにが起きたのか、たくさん盛り込まれていました。それもシリーズものならアリだけど、1本の映画として彼女の全人生を語るのは難しいな、と感じました。そこで、なにか新しい構成が必要だと」、そこから頭を捻ったようだ。
まさに慧眼。リー・ミラーの回想は、1938年の南仏ムーシャンへ飛ぶ。「まずは、ある時期を選んで、そこを濃縮して見せていこうと考えました。そのなかに、ちゃんと起承転結のある物語の流れを作ろうと。リー・ミラーが登場する映画はすでにありましたが、それまで描かれてこなかった彼女の側面を語りたいとも思いました」と続ける。南仏でアーティストらと語らって過ごす、ミラーの優雅な日々から幕を開ける回想シーンは、やがて戦争が勃発したことで一転。激動の時代をミラーが駆け抜ける、暗くシリアスな世界観へとトーンが転調していく。1930年代後半からの約10年に絞ったことを、クラスは「あの当時と、21世紀といういまを生きる私たちの経験が、非常に似ていると感じるのも理由の一つです。それも表現したかった」と、付加的かつ大きな動機を挙げる。
「30年代後半には、すでに政治的に大変なことが起こり始めていたにもかかわらず、誰もそれを気にかけることなく、人生を楽しみ、アートを楽しみ、戦争のことなど頭になかった。そしていま、私たちが生きるこの時代には権威主義的なリーダーが現れ、それが段々と力を持ち始めている。アメリカやヨーロッパのみならず、世界中でファシズムが台頭してきているように感じるんです」と真剣な表情で続ける。一方、回想形式を取った理由については、「観客がリー・ミラーに共感できる視点にしたかった。それなら本人がインタビューを受け、自分の言葉で自分の人生を語るのがいいのではないか、と。彼女がモデルをやめて写真家になり、すでに若くはなくミドルエイジとなった彼女が、真実を伝えるために戦場に入っていくという時期を選びました」と最大の理由を語る。