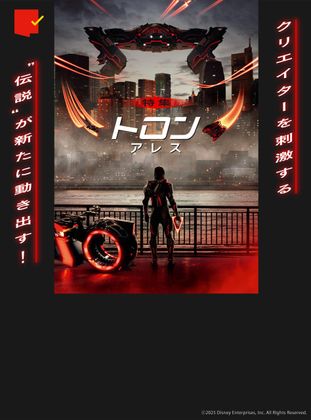『愚か者の身分』永田琴監督&林裕太を釜山で直撃!「⽣きようとすることは決して愚かな選択肢ではない」
真の弱者は助けたくなるような姿をしているとは限らない。軽い気持ちで闇バイトに手を染めた若者は、そこから抜け出すことを許されず、弱者が際限なく搾取されていく負のループが加速する…。映画『愚か者の身分』(公開中)は、「今際の国のアリス」シリーズや「幽☆遊☆白書」で知られ、グローバルコンテンツを創造するプロデューサー集団 THE SEVENが初めて手掛けた劇映画となる。同作は第30回釜山国際映画祭が新設したコンペティション部門にノミネートされ、メインキャストの北村匠海・林裕太・綾野剛がレッドカーペットを歩いただけでなく、3人揃って最優秀俳優賞を受賞。授賞式には永田琴監督、森井輝プロデューサーと共に林が登壇し、「⽣きようとすることは決して愚かな選択肢ではない」というメッセージを伝えた。
戸籍売買に携わるタクヤ(北村匠海)は、自分がこの世界に引き込んだ弟分のマモル(林裕太)と一緒に足を洗うべく、兄貴分である梶谷(綾野剛)を頼る。彼らは犯罪者であると同時に、劣悪な環境で育った被害者であり、ごく普通の人間でもある。オーディションで選ばれたマモル役の林裕太は、デビューからわずか5年の間に映画やドラマの出演作を重ね、めきめきと頭角を表した注目株だ。レッドカーペットを歩いた翌日、釜山国際映画祭会場近くのホテルで、林と永田琴監督に話を聞く機会を得た。
「お芝居をしてもらった瞬間に、マモルだと思いました」(永田監督)
林「面談+お芝居という形式のオーディションで、最初はすごく緊張していました。それが役者を始めたきっかけや家族のことを聞かれて話していくうちにリラックスしてきて。準備していったお芝居がどう見られていたのかはよくわからなかったんですけど、自分の人となりを見せることができたなという実感はありました」
永田「ちょっとお芝居してもらった瞬間に、『マモルだ!』と思いました。本人に『マモルってどういう人だと思う?』と聞いた時も、ビシッと言い当てていて、脚本の読みとり方がすばらしかったですね」
林「マモルって強いな、生きる力があるな、というのが脚本を読んだ最初の印象で、それはいまでも変わらないんです」
――マモルの髪型や衣装も特徴的でした。
林「ちょうど別の作品で坊主にしていたので、頑張って限界まで伸ばしました」
永田「伸ばして、金髪にして、思春期にできなかったお洒落を一気に開花させている感じにしたいと思っていました。マモルは基本的にタクヤの真似をしているんです。着るものや身につけるものはタクヤのお下がりをもらっていて、タクヤと2人で歌舞伎町に繰り出すシーンも全身タクヤのお古を着ている想定で作っています。逆にタクヤは、以前着ていた柄物を全部マモルにあげてしまって、いまはモノトーンの洋服しか着ていない。そして綾野剛さんの演じた梶谷は衣装が1着しかありません。これは3人のストーリーなんですけど、1人の人間の“過去・現在・未来”みたいに見えたらいいなと思っていました」
――脚本のメインライターには『悪い夏』(25)や『リンダ リンダ リンダ 4K』(25)などを手掛けた向井康介さんの名前がありますね。
永田「以前から“道を踏み外した若者とその社会復帰”をテーマに映画を撮りたいと思っていました。そのなかで親交のあった西尾潤さんの原作小説と出会って、これなら自分のテーマと合致させつつエンタテインメント性のある作品に仕上げられると思ったんです。ただ、男性同士の空気感や会話のディテールを、原作よりもう少し深めたところで描きたかったので、脚本は男性にお願いしたいなという気持ちがあって。青春ものから“イヤミス”のようなジャンルまで幅広く書かれている向井さんにお声がけしました」
「仕事を楽しもうとする匠海君の姿勢がステキだなと思います」(林)
『愚か者の身分』が描く若者の貧困はホットなテーマでもあり、カメラはショッキングな現実からも目を逸らさない。タクヤたちを取り巻く状況はどんどん過酷になっていくが、物語は刹那的な破滅へ向かうと思いきや、それと同時にオフビート的な瞬間があったり、アメリカン・ニューシネマのような逃亡劇に突入したりと、緩やかな“脱線”を繰り返してドラマの行方に様々な可能性を持たせる。しかしそれは作品そのもののトーンが変わるというよりは、登場人物が見せる異なる側面に沿った転調のようにも見える。
――ストーリーの展開だけでなく、演出のトーンとしても、変化をつけるのはねらいだったのでしょうか。
永田「私はテレビドラマを多く撮ってきたので、自分の中にドラマの撮り方の方法論みたいなものは持っているんです。ただ、この映画ではそのやり方とは違うところで芝居を撮っていきたいという思いがありました。このシーンはこう撮る、とあらかじめ明確に決めていたわけじゃないけど、現場で芝居を見ながら、ここは芝居を長く見せられそうだからカットを割らずに撮りたい、といったふうに判断していきました」
――タクヤとマモルは本当に劇中の関係性にしか見えません。どうやってあのケミストリーを作り上げていったのでしょうか。
永田「そう見えてくれていたらうれしいです」
林「うん、うれしい!匠海君とは台本の読み合わせで初めてお会いしたんですけど、その時から空気感が合いそうだなと思っていて、現場で上手くやっていけそうな兆しは感じていました。撮影順もタクヤとマモルの出会いのシーンから始められたのは大きかったです。徐々にコミュニケーションを取って、だんだんとマモルとタクヤが僕と匠海君にリンクして、役が乗り移ったみたいな関係を作っていけたし、お互いにそこを意識していた部分もありました。特に2人が歌舞伎町で遊んでいるシーンは、直前まで雑談していた延長で現場に歩いて行って本番が始まる……という流れで撮っていたので、それが活きたのかなと思います」
永田「歌舞伎町のシーンは日にちと時間の経過を示すために、衣装を変えて3回ぐらい撮りました。細かい行動やテンションの違いだけを伝えておいて、ゲリラ的に撮影したよね?」
林「楽しかった……!」
永田「撮影中は2人でカラオケに行ったりもしてたよね」
林「あ、行きました。僕は『浪漫飛行』を歌いました(笑)」
――初めて戸籍の売買に成功してドヤ顔をしてみせたマモルに、タクヤがリアクションするコミュニケーションがすばらしかったです。
永田「あれは台本に書かれてなかったんですけど、マモルの空気感が出来上がりつつあったところで、匠海君がそれに対して返してきてくれたのはすごくありがたかったですね」
林「うれしかったですね……!あの顔は絶対にやろうと思ってたんです。匠海君はどう反応してくれるかなと思ったら、僕と同じような顔をしてくれて。『兄貴……!』と思いました」
――カメラの外でも先輩である北村さんの背中から影響を受けたことはありますか?
林「とにかく仕事を楽しもうとしている姿勢が本当にステキだなと思っていました。『あれだけ忙しくされていて、大変な時はないんですか?』と僕が聞いたら、『楽しいからこの仕事を続けている、どんなに忙しくても全部楽しいと思う』と話してくれて。大変な時や辛いなと思うことがあっても、そのなかで楽しめるところを探して、それを楽しむ努力をしている。僕はいま、俳優の仕事が楽しくて仕方ないんですけど、そのうちそうじゃなくなりそうな瞬間も来るかもしれません。そうなった時に、あとから結果的に楽しくなるんじゃなくて、最中を能動的に楽しもうとする姿勢がすごく大事だなと思うんです。匠海君みたいに長くこの仕事を続けている人が、いまもそう思い続けられるのは簡単なことじゃないと思うからこそ、見習いたいなと思っています」