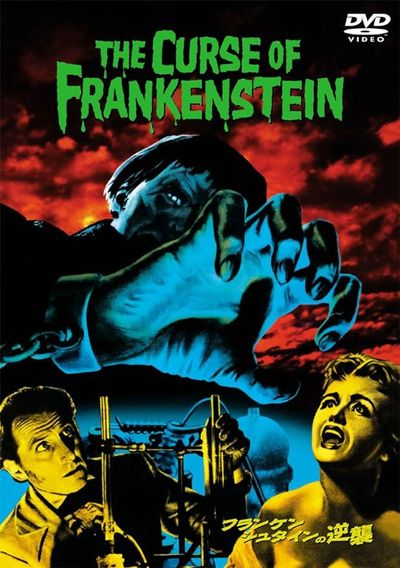100年以上にわたる「フランケンシュタイン」の映画史…その誕生からギレルモ・デル・トロ版までを俯瞰する
ギレルモ・デル・トロによる「創造した者の責任と放棄の罪」としての再構築
こうした主題は2025年、ギレルモ・デル・トロによって新たな形で蘇る。
デル・トロの新作『フランケンシュタイン』(10月24日一部劇場で公開中、11月7日よりNetflixで世界独占配信)は、同シリーズの再生であると同時に集大成でもある。『デビルズ・バックボーン』(01)から『シェイプ・オブ・ウォーター』(17)に至るまで、彼はモンスターを純粋さと哀しみの象徴として描いてきた。シェリーの小説を「世界で最も悲しい物語」と呼ぶ監督は、今回の映画化においても原作への忠実さと独自性の両立を目指している。
脚本は原作の書簡体構造を踏襲しつつ、ヴィクター・フランケンシュタイン(オスカー・アイザック)と怪物(ジェイコブ・エロルディ)の交錯する回想によって物語が進行する。創造主と被造物がそれぞれ自らの視点で語る構成は、シェリー原作の語りを映画的に展開するものであり、従来にない心理的な対称性を生みだしている。
デル・トロはこの物語を、科学的傲慢である以上に「創造した者の責任と放棄の罪」として再構築する。真の悲劇は生命を生みだした行為そのものではなく、その存在を拒絶することにある、と。この倫理的な転換は、AIや遺伝子工学といった現代のテクノロジー不安と共鳴する。
さらにデル・トロはヴィクターを現代的な人物として定義する。彼は生物科学の先駆者でありながら、名声を超越と錯覚する自己陶酔的な存在だ。その姿はクリエイターが過剰に自身をブランド化する現代文化の象徴であり、また『シェイプ・オブ・ウォーター』に連なる「異形への共感」は、人間性を定義するのは理性ではなく、共感であるという信念を改めて提示している。
1世紀を超える翻案の歴史を経ても、『フランケンシュタイン』は依然として映画そのものの換喩として生き続けている。産業社会では機械化への不安を、冷戦期には科学的破局への恐怖を、そしてデジタル時代にはAIによる人間の陳腐化を映しだしてきた。その根底には常に、「創造者はどう在るべきか?」という原初的な問いが流れている。
デル・トロによる新たな映像化は、そうした「フランケンシュタイン」の歴史的系譜を総括する試みである。シェリーのロマン主義や、ユニバーサル映画のゴシック主義、ハマーや東宝による再解釈、そして自身の映像的感性。そのすべてが一つの生命体のように連続している。映画もまた絶えず自己を再生し続ける創造の装置であり、ギレルモ・デル・トロの『フランケンシュタイン』は、その定義を改めて認識させるのだ。
文/尾崎一男