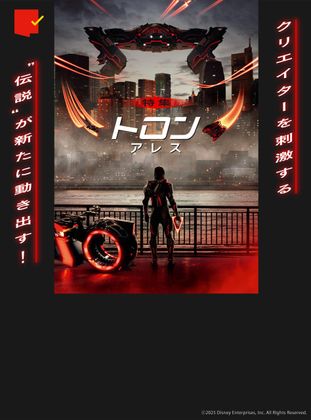石田ゆり子、『もののけ姫』サン役「もう一回やりたい」と告白。「絶対に甘やかさない」宮崎駿監督“独特な演出指導”エピソードに会場沸く
1997年に公開された宮崎駿監督作品『もののけ姫』を4Kデジタルリマスター版としてIMAXのスクリーンに蘇らせる期間限定上映が、いよいよ10月24日(金)よりスタートする。10月20日にはTOHOシネマズ新宿でプレミア試写会が行われ、主人公のアシタカを演じた松田洋治、サン役の石田ゆり子、スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーが登壇。公開から28年、それぞれが当時の思い出や制作秘話を語り、会場を沸かせた。
人間と自然の衝突を壮大なスケールで描いた本作は、1997年7月12日の初公開時、観客動員1420万人、興行収入193億円という大ヒットを記録、社会現象を巻き起こした。アシタカとサン、タタラ場に生きる人々、そしてシシ神の森に棲む神々の交錯する運命を描いたこの物語は普遍的なテーマを投げかけ、公開から四半世紀以上が経った今もなお、国内外で多くの人々を魅了し続けている。
スタジオジブリが監修した4Kデジタルリマスター版では、映像の細部に至るまで鮮明になり、森の緑やキャラクターの表情、そして壮大なアクションシーンがより一層際立つ。大スクリーンを見上げた松田は、「この大きさで『もののけ姫』を28年ぶりに観る。IMAXの画質と音質に期待しています」と興奮しきり。「この画面の大きさ、本当にびっくりしています」と切り出した石田も、「ものすごい没入感だと聞いているので、楽しみにしています」と期待していた。
スタジオジブリ作品の大役に決まった当時の心境を振り返ることになると、松田は「事務所から、『スタジオジブリの新作映画のオーディションに行って』ということだけしか言われていなかった。オーディションのスタジオに行ったら、誰もいなかった」と回想。個別オーディションなのかと思い、ストーリーやアシタカ役について説明を受けつつも、「まさか自分が主役をやるとは思っていなかった」と主人公のサンプル録りだと思い込んでその日を終えたという。その後は松田に連絡がないまま、映画館で自分の声が吹き込まれた予告映像を観た友人から連絡が来たとのこと。映画館に予告編を確認しに行き、「自分の声が聴こえてきて、『俺、主役をやるんだ』とびっくりしました」と裏話を明かして、会場を笑わせた。鈴木によると、「アシタカの声を誰にするかというのは、結構悩んだんです。決め手はおそらく、松田さんが『風の谷のナウシカ』で演じたアスベル」だと語っていた。
石田は、オファーを受けて「なぜ、私なんだろうと思った」と率直な想いを吐露。とはいえスタジオジブリの最新作だということで「天にも昇るほどうれしかったです」とにっこり。鈴木は「石田さんは、宮崎駿のタイプだった。『平成狸合戦ぽんぽこ』で宮崎駿が石田さんに挨拶をした。その時に、鼻の下が長くなっていた」と茶目っ気たっぷりに語る。
アシタカとサン、どちらも難役となり、演じるうえではもちろん苦労もあった様子。松田は「あまりに難しいうか、どうすればいいのかわからなかった。アニメーションのアテレコ自体、ほとんどやっていなかった。アテレコの経験もないものですから、考えても無駄だと。当たって砕けろしかないなと思っていました」ととにかく思い切ってやってみたという。石田は「サンというのは、実はそんなにセリフはないんです」と分析しつつ、「動きの息や、立ち昇ってくる気配とか。人間であって、人間ではない。動物になりたいけれど、動物にもなれない。不思議な役なので、それはそれは難しかったです」と打ち明けた。
実際に始まったアフレコでは、「私は一番、大変でした。完全に全員のなかで、一番下手くそでした」と告白した石田。「あまりそれを言うと、皆さんが映画を観る時にそれが気になったらイヤだなと思うんですが…」と上映前の観客を気遣いながら、「私一人、居残り授業みたいな感じで。洋治くんは上手なので、どんどん終わっていく。皆さんが終わっていくなかで、居残り」をしていたと苦笑いを見せた。
さらに「サンがアシタカを助けて、弟犬に乗せて一緒に走る。あそこのくだりが、本当に難しくて。なんでもないようなシーンのようでいて、最も難解でした」ととりわけ悪戦苦闘したシーンを説明しながら、「『お前、死ぬのか』というセリフを、『お前、パンツ履いてないじゃん』というふうにやれと言われたんです」と宮崎監督の独特の演出方法を明かして、これには会場も大爆笑。「最初に私は『お前、死ぬのか!』と死んじゃダメ!というふうに言っていたと思うんですが、(宮崎監督が言うには)この子にとっては『パンツ履いていないけど、どうしたの』という程度の出来事だと。そう言われて、当時の私には難解すぎて。毎日泣きそうな気持ち。でもこんなに夢みたいなことはなかったので、夢のなかなんだけれど、地獄みたいな。不思議な恍惚感がありました」と、特別な経験を果たしたと目尻を下げた。「絶対に甘やかさない。多分、私はギリギリまで『この子、やめた方がいいんじゃないか』と思われていたと思う」と最後まで、宮崎監督の妥協なき姿勢を目にしていたという石田。自分自身、「いまでも、もう一回やりたい。でももう、この声は出ないので。それくらい思い出に残っている」と本音をこぼしていた。
大ヒットを記録した本作だが、松田は「(ゴンザ役の上條恒彦さんが)小さい子や家族連れはしんどいから数字的にはそこまでは行かないんじゃないかとおっしゃっていて。なるほどそうかもしれない思った。蓋を開けたら、えらいことになった」、石田も「10歳未満の子どもたちに、どういうふうに受け入れられるかなと思っていた」と難解な物語でもあることから、子どもたちの反応が気になっていたというが、「宮崎さんが『実際に一番深いところで理解しているのは、10歳くらいの子どもたちだ』とおっしゃっていた。それは真実だなと思います」としみじみ。鈴木は「お客さんがいっぱい観てくれたのは、素直にうれしかったですね。なんのために作るかと言えば、お客さんに観てもらうため。自分たちのために作るんじゃない。お客さんのために作ろう。そのことに改めて、気付かさせてくれた作品になりました」とプロデューサーとしても大切なことを教えてくれた作品だと、熱を込めていた。
※宮崎駿の「崎」は「たつさき」が正式表記
取材・文/成田おり枝