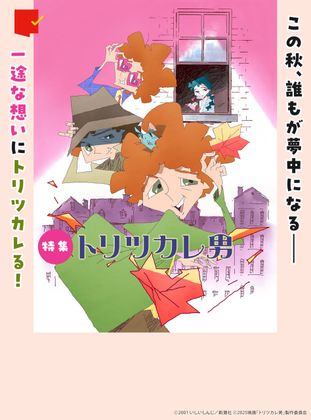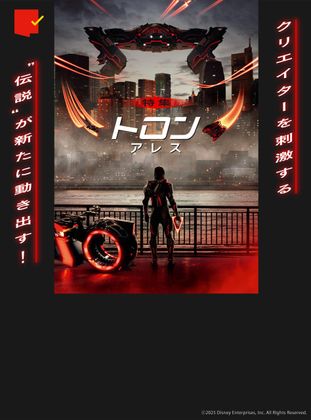韓国で35万人が感動した『最後のピクニック』キム・ヨンギュン監督が語るヒットの要因「高齢世代の主人公の人生を視聴者が繊細に感じている」
「自分が抱える悩みや特別な感情を、映画を作ることで解きほぐす作業を続けてきた」
韓国で公開時に、韓国で単館公開規模ながら5 年ぶりのヒット記録を更新し35 万人を動員した。コロナ禍以降、劇場に観客が戻らない寂しい状況が続く韓国映画界での異例のヒットについて、キム・ヨンギュン監督はどのように分析しているのだろう。
「韓国も現代では50代以上の人口が多く、高齢化社会になりました。なので、そんな中年や老年が共感できる作品があまり多くなかった時期に、この映画の口コミが広まったのが効果的だったのかもしれません。そして俳優の方々が韓国で本当に有名な方々だということもありますね」。
たしかに、ドラマで言えば「ナビレラ -それでも蝶は舞う-」や「君は天国でも美しい」など、近年高齢世代を主人公にした作品が増えている。『最後のピクニック』は同じ系譜に連なりつつ、壮年男性の主人公が活躍する作品が多い映画界のパイオニアとなっていくのかもしれない。
「社会だけでなく、ドラマや映画界でも、50代以上の製作者や監督たちがいまでも多く活動しています。だからこそ高齢者をテーマにし、視聴者がその人生を繊細に感じていく流れが今後もさらに続いていくと思います」。
『最後のピクニック』は、“宝島”と呼ばれる南海を舞台にしたウンシムとグムスンの穏やかな小旅行を描くだけでは終わらない。島ではリゾート誘致による再開発をめぐり、テホをはじめとした反対派と、グムスンの息子ソンピル(イム・ジギュ)が加わる賛成派による対立が起きている。またウンシムは、ソウルで同居している息子ヘウン(リュ・スンス)が事業の失敗で窮して妻から離婚を突き付けられていることに胸を痛めている。監督は世代間の葛藤も、もう一つのテーマとした。
「韓国の地方ではいま、若者が都市に流出してしまい、共同体がかなり崩壊しています。そこには農村や漁村としての価値がもう残っていないので、きれいな景色だけが残ってなんですよね。 同時に景色が良い場所だから観光のためのリゾート開発が可能なわけなので、ある意味では、開発ブームもまた間違いなく唯一残された価値なのだと思います。でも農村と漁村、山村は、私たちの生活の基盤だと信じています。都市での暮らしだけで一つの国が健康に生きていくことはできません。現実には残念ながらそれらが崩れてしまっています。まるで病んで死んでいく私たち人間の姿のように感じました」。
長編デビュー作のラブストーリー『ワニ&ジュナ ~揺れる想い~』から始まり、『殺人漫画』(13)、『怪談晩餐』(23)といったホラー、そして本作のようなヒューマンドラマに至るまで、手掛けてきたジャンルは幅広い。多岐に渡る創作活動の中で一貫して持ち続けてきた信念について質問すると、「人間関係やその中で生まれる感情のストーリーを書いたり、エモーショナルな表現をしようと深く考えているようです」という答えが返ってきた。たしかに、人生の終わりに関する不安が老年期だけの問題ではなく、あらゆる困難に直面し苦悩するそれぞれの世代に眼差しを向ける『最後のピクニック』は、彼が口にしたような映画作りのエッセンスが最もよく現れている。
「映画を作ったその時その時の年齢に合った悩みや特別な感情を、映画を作ることで解きほぐす作業を続けてきたんじゃないでしょうか。そういうふうに見ると『最後のピクニック』も、いまの私が持つ感性の深さを表現しようと努力しました。だから私が30歳、40歳、50歳とそれぞれの年代に作った映画では、それぞれ私が別人になっていく感じなんですよね。だからこそ、多様なジャンルもできるんじゃないかと思います」。
取材・文/荒井 南