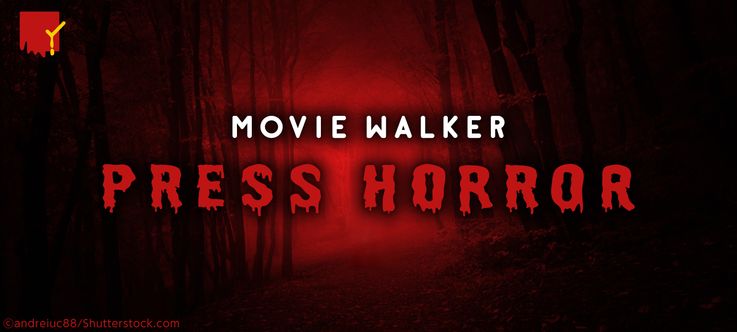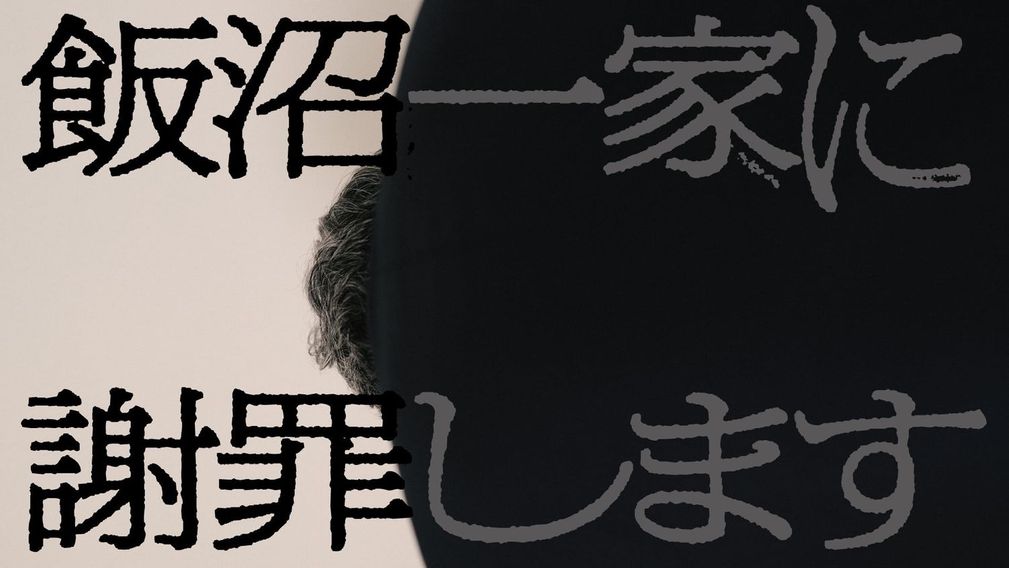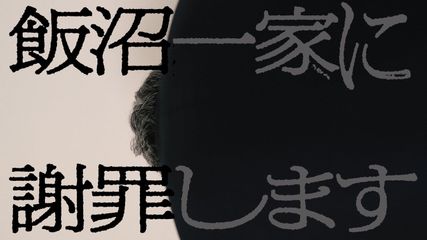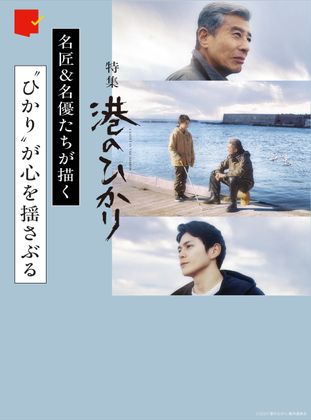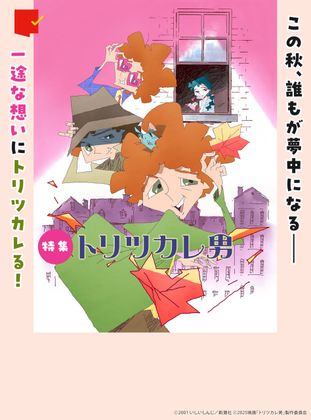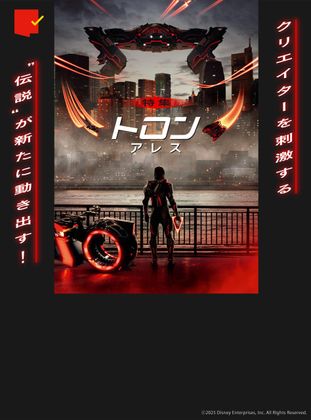「魔法少女山田」総括座談会。「TXQ」と“考察”を大森時生、寺内康太郎、皆口大地が語り合う
「入口は誰でもわかるもののほうが本当っぽさがある」(寺内)
――先ほど「恐怖心展」の名前があがりましたが、どのような流れで本作がかたちづくられていったのか気になります。
寺内「大森さんから『恐怖心展』をやるという話を聞いたのが、昨年末の『飯沼一家』の頃で、そこからモチーフをどうしましょうかという話が始まりました」
大森「“恐怖心”というテーマがあり、その後に“魔法少女”というモチーフが出てきて、寺内さんと福井(鶴)さんの脚本のなかで“唄うと死ぬ歌”が登場した。そんな順番だったと認識しています」
寺内「最初に魔法少女と恐怖心というキーワードを聞いた時に、めちゃくちゃ難しいなと。途中で大森さんは『そんなに魔法少女にこだわらなくても大丈夫ですよ』と言ってくれたんですが、高いミッションをいただいた方が乗り越えた時によくなると思っているので、意地でも魔法少女で作らなければと僕のほうがこだわっていました(笑)」
――そもそもなぜ“魔法少女”をテーマにされたのでしょうか。
大森「僕が考えるに、魔法少女というものはすごく変なジャンルなんです。『美少女戦士セーラームーン』とか『プリキュア』シリーズのように純粋な“魔法少女もの”作品もありますが、近年はオマージュのほうが多く、『魔法少女まどか☆マギカ』に代表されるように“ズラし”の対象として使われやすい傾向にあります。“恐怖心”もまた、自分の知っているものからちょっとズレたことで紐づきやすいものですから、この二つは合うのではないかと思ったのが一つ。あともう一つは、エルサゲート(※)という概念に興味があったのです」
(※註:子ども向け動画に見せかけて、残虐なものや性的なものなど不適切なものをわざと見せること。『アナと雪の女王』がその題材に使われたことから、“エルサゲート”と呼ばれている)
寺内「最初はエルサゲートに端を発して、小さい頃になにかがあったということを考えていたのです。そこで歌を作り、悪い人の目線というか、世の中をおかしくしようと考えている人が作った曲が伝播して、エルサゲートになる。でもそれはあまりにもストレートでつまらなかった。色々と考えているうちに『TXQ FICTION』であることを忘れて普通の話になってしまったので(笑)、“唄うと死ぬ歌”にしてみようと」
大森「オカルトらしきものがスタートになって、そこから現実世界が展開していく点は、一般的なものと逆の順序で興味深いと思います」
寺内「オカルトから入りながらも、進むにつれて全然違った出口へと向かっていく。なので入口は広くキャッチーかつ、誰でもわかるもののほうが本当っぽさがあると思うんです。とはいえ今回は『TXQ FICTION』では珍しく本当のオカルト現象が画面に登場していないんですよね」
――あの歌はどのように作られたのでしょうか?
寺内「幼稚園で歌われる、事務員の人が作ったオリジナル曲ってどんな感じだろうかと作曲家の方にお願いしたんです。歌詞は台本にもある山田さんの伝えたいメッセージが詰め込まれているのですが、なにしろ音程が複雑な3拍子ですごく歌いづらい。これはきっと、作曲家の方が『TXQ FICTION』だから普通じゃダメだと考えてやったことだと思います(笑)。しかもピアノの演奏も元教師の人にお願いしていたり、ただ音楽を作るのではなくその背景から作るという、小道具づくりのようなやり方がされています。なので魂が乗っかった曲になっているはずです」
「触れちゃいけないものに触れずにいられない」(皆口)
――今作が前2作と大きく異なる点としては、テレビ番組が軸になっていないということもありますよね。しかも自主映画を中心に、さまざまなメディアを横断している。
大森「これまではたまたまテレビ番組を大きなモチーフに選んできましたが、必ずしもそうしなきゃいけないとはあんまり思っていないんです。今回は、最後の最後で三田愛子という人の自主映画を観ていたとわかる作りになっていて、寺内さんと福井さんの考えを推察すると、貝塚が偏執的に“唄うと死ぬ歌”について調べた結果としていろいろなメディアを横断しながら真実に近づいていったのではないかと」
寺内「コンセプトとしては二つあって、一つ目はたくさんの短い映像を集めて、そのすべてにヒントがあって、全部を集めると一つの物語になるという実話怪談のようなイメージ。もう一つは、いまの社会ではXやInstagramやTikTokとか、同じ時代の同じ社会に生きていてもみんなレイヤーが違っていて、それぞれのレイヤーにいる人たちが交わることがないという点でした。なので異なるレイヤー、異なるメディアを渡っていくのはきっとおもしろいだろうなというねらいがあったんです」
大森「現代社会はとにかくエコーチェンバー化しているので、偏執的に取り憑かれている人は一つの集団のなかにいて、メディアを横断しないことが当たり前になってきています。例えば、Xをやっていない人からしたらNintendo Switch2をめぐる騒動はまったく知らないけれど、Xをやっている人のなかではガザの情勢と同じくらいのバリューで扱われているという奇妙な現象が起きています。貝塚の場合は、一つの事柄にこだわって追い求めながら、自分の過去、ひいては自分自身というものを見つけようとしています。それは一つのメディアに囚われていたら絶対にできないことですよね」
――それを聞くと、「魔法少女山田」という作品は貝塚の成長物語に思えてきますね。
大森「僕も観ながらそう感じていました。まあ、成長したのか、取り返しのつかないことになったのかは観る人によって分かれる部分ではありますが。結果的に貝塚は、恐怖心と向き合って、それを探し出すことで広い意味で成長している。個人的にはそう信じています」
寺内「一番最初に貝塚は『なにも知らずに生きてきて、いま思えばそれでよかったんです』と言います。知らずに済んでいたらそれはそれでいいけど、でも知りたいという強い思いもある。だから後半では変な行動をたくさんしてしまう。それを“怖い”と感じるよりも、“自分もそうなってしまうかも”と共感して観てくれたらいいなと」
皆口「触れちゃいけないものに触れずにいられないというのは、怖がりなのにTSUTAYAに通い詰めてホラー映画を借りまくっていた学生時代を思い出してしまいます(笑)。はたから見ればなにやってんだと思われることですが、本人はいたって真面目だし一所懸命。これがなにかに取り憑かれているということなのかもしれませんね。よい結果にならなくても触れたくなってしまうし、あわよくば克服できるかもしれない。そう考えると、やっぱりこれは貝塚くんの成長物語。ちょっと歪んだ青春な感じもしますけど(笑)」
大森「たしかに歪んでいますね(笑)」
TVerにて配信中
https://tver.jp/series/srog0v9atu
■「恐怖心展」
会期:〜8/31(日)
会場:BEAMギャラリー 東京都渋谷区宇田川町31-2 渋谷BEAM 4F ※渋谷駅徒歩5分
開催時間 :11:00〜20:00 ※最終入場は閉館30分前まで ※観覧所要時間約90分
料金:2,300円(税込) ※小学生以上は有料
主催:株式会社闇、株式会社テレビ東京、株式会社ローソンエンタテインメント
会場協力:東急不動産株式会社
企画:梨、株式会社闇、大森時生(テレビ東京)
医学監修:池内龍太郎(精神科医)
公式HP:https://kyoufushin.com