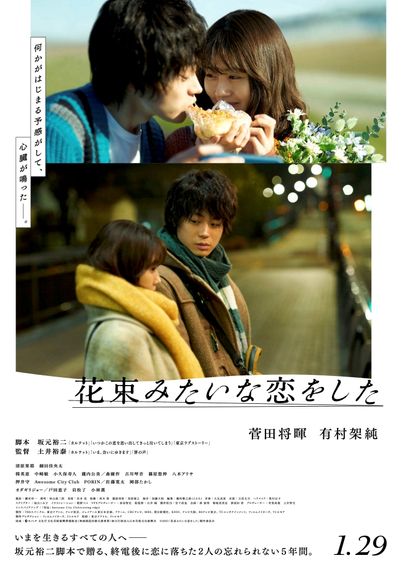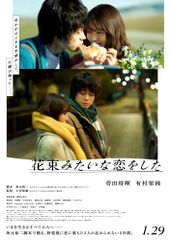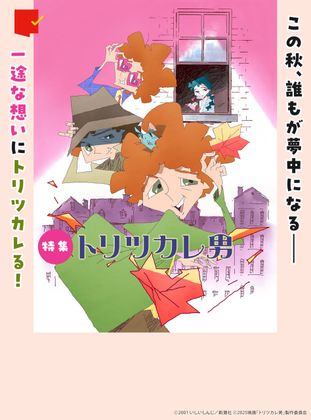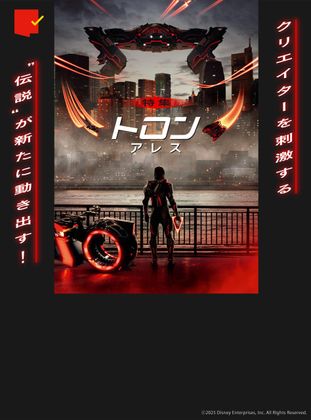土井裕泰監督が『片思い世界』の“あの秘密”を語る。「最初にタイトルから受け取ったイメージが、観ていくうちに変わっていく作品」
「この映画において大事なことは、3人が一つとなってなにかを表現すること」
主演の3人は、撮影前からごはん会をするなどして親睦を深めてきたという。まるで映画における12年間という時間を埋めるかのように実際にも距離が縮まっていった。美咲はしっかり者、優花は好奇心旺盛、さくらはザ・末っ子。まるで本物の姉妹のように映っていたが、それは現実の仲の良さがそのまま反映されていたのかもしれない。
「今回3人は常に一緒にいました。カメラの前ではなくても、本当にずっと一緒に3人が寄り添って、ずっとなにかをしゃべっている。そういう時間を過ごしていたんです。もちろん一人ひとりの役にそれぞれキャラクター性があるのだけど、この映画において大事なことは、3人が一つとなってなにかを表現すること。彼女たち自身がそれが一番大事なことだと思っているのではないかと感じ、私も意識するようになりました。また、横浜流星さんについては、やはりピアノの苦労があったと思います。典真という人間を表現するうえでものすごく大きな意味を持つので、彼自身もピアノを自分で弾くことの大事さを理解していました。複数の作品の様々な稽古を同時進行されていたと思いますが、ピアノの練習もずっと続けてくれて、本当にありがたかったです」。
本作はファンタジーでありながら、リアルさもある。美咲、優花、さくらの3人が別のレイヤー世界で存在しているという演技をすることも、それを演出することもさぞ難しかったことだろう。わかりづらい世界観を、映像としてどのラインで表現するかは本作における課題だった。
「坂元さんにはクランクイン直前まで、多くの質問をぶつけました。受け取っては返す。まるで手紙のようなやり取りだったと思います。主人公たちが『人にぶつかって転ぶ』というト書きについては、現実のレイヤー世界で彼女たちは『透明なケムリ』のような存在だという脚本上のワードを手がかりにして、相手と体が接触する前に押されて倒されるようなイメージでアクション練習をしてもらいました。最近の作品では一瞬透明になる、空気が歪む、体がすり抜けるなどいろんな表現方法がありますが、今回はあえてアナログな手法を取ったほうがこの作品にはふさわしいという思いがありました。結果的に作品の世界観に合うような表現になったと思います」。
「最後の合唱シーンを灯台のようにして、そのあかりを目指して作り上げた」
本作は東京の片隅が舞台。特別な固有名詞で地名が語られることはなかったが、雑多で混沌としながらも生活が感じられる東京という街の魅力が活かされていた。なかでも監督の思い入れのある撮影場所は「駒沢オリンピック公園」だという。
「駒沢オリンピック公園は夜になると実際に若者たちがバスケをしていたり、ダンスの練習をしていたりする場所。あそこでロケをできたことはとても大きかったです。彼女たちは主役なので、普段なら絶対に暗い中でも光を作り、その中で撮影するところなのですが、今回3人は光の当たらないところに普通に座っているんですよね。そして普通に、恋の話をしたりしている。こんな3人の画はあまり観たことがないな、と思いながら撮影していました」。
そこは特別な場所でも、輝かしい場所でもない。私がよく知る、普段のままの、日常の東京の風景だ。そこに3人が溶け込んでいる。だからこそ、本当に登場人物がこの街で生活しているかのようなリアリティがあった。
そして最大のカタルシスを提供してくれるのが、最後の合唱シーンだ。あのシーンを観た時に、これは映画館の音響でちゃんと体感したい音楽映画だと思った。合唱曲「声は風」の作詞は明井千暁の名義になっているが、その正体は、作詞家・坂元裕二。歌詞はあくまで普遍的で、実際に合唱曲として歌われそうな、希望に満ちたものになっている。それと同時に、本作のストーリーにもリンクしたものとして読み取ることもできる。劇場を出た後もつい口ずさみたくなる名曲に仕上がった。
「坂元さんが作詞された歌詞に曲をつけてもらう形で、合唱曲を作りました。もちろん3人にも歌ってもらわなければいけないので、最初に杉並児童合唱団の子どもたちに歌ってもらったものを録音したんです。それを初めて聴いた時、自然と涙がこぼれてきました。この物語は最後に、観客がこの合唱曲をどういう気持ちで聴くかというところへ向かって作る映画なんだなと、僕のなかで腹を括った瞬間でした。だからこそ、歌詞の一つひとつを思い浮かべながら、彼女たちのシーンを撮っていきました。最後の合唱シーンを灯台のようにして、そのあかりを目指して作り上げたのが『片思い世界』です」。
取材・文/綿貫大介