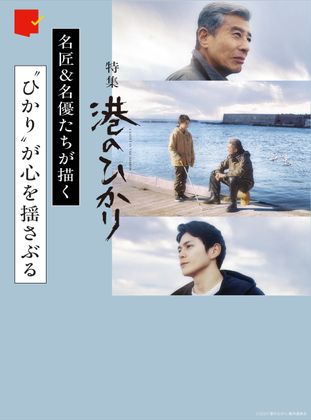大友啓史監督が映画『宝島』に込めた想い「『これが最後の作品になってもいい』とそのくらいの覚悟で臨んだ」
「沖縄の土地には死者の魂と自然が交わるような感覚がある」
――今回、大友監督がなぜ沖縄の物語を描こうと思われたのかを考えていたのですが、「龍馬伝」や、その前のNHKドラマ「白洲次郎」(09)のころから、常にジャーナリスティックな視座から“世界の構造”を描こうとしていた印象があります。そして“いま”を描こうとした時、ご自身にできることを考えた結果、沖縄にたどり着いたのではないかと。
「まさにそうですね。声にならない声を届けること、見過ごしてはいけないものを見ること。それを僕自身が作品として形にするには、沖縄に仮託するしかなかった。アメリカと日本、強者と弱者、戦争の勝者と敗者の関係性はいまも続いています。『白洲次郎』では、戦後に世界のシステムが変わった瞬間、弱い人々にシワ寄せがいく構造と、でも、そんな場所でこそ動き出す人がいるという、あの時代の人々が立ち上がっていく“鼓動のようなもの”を描きました。一方で、いまの世界には、大きな表舞台でのヒーローはもういない、もはや市井の無名の人の中にしかいないのではないかという感覚が『宝島』にぴったりはまったんです。
ただ日本映画の枠の中で、この規模の作品を作るのは本当に大変でした。僕自身も沖縄での撮影が始まってからも、資金繰りや様々な事情でずっと止まるんじゃないかと不安でした。役者やスタッフとは別のホテルに泊まり、誰にも弱気な顔を見せないようにしていた。一人で気持ちを整えて、毎晩脚本に手を入れながら現場では捨て身の覚悟というか、ある種御嶽に跪くような思いで手を合わせながら、『いくぞ』と。そういうスタンスで撮影に臨んでいました。
撮影中は土地独特の死生観にも向き合わざるを得ませんでした。沖縄はマジックリアリズムがリアルに感じられる島。死者の魂と自然が交わるような感覚があるんです」
――コザ暴動の場面も、オンちゃんの魂に導かれるように進んでいくのが印象的でした。グスク(妻夫木聡)とレイ(窪田正孝)のやり取りは映画オリジナルの台詞も多いですが、物語の核ですよね?
「そう、芯にあります」
――あそこには、ポジショントーク的なリベラリズムを超える力があると感じました。
「そんなふうにご指摘いただき感激です。いまはポジショントークばかりの時代。でも、日本でも、物語の登場人物たちが異なる意見や各々の価値観をぶつけ合い、アウフヘーベン(止揚)して新しいなにかを生み出す創作の根源がありました。そしてそれは、私たちの現実世界にも確かな影響を与えていた気がします。例えば山田太一先生が脚本を書かれたNHKドラマ『男たちの旅路』(76~82)のように、世代の違う人間が討論しながら新しいものを生み出し、視聴者に突き付けてくる作品などがあって、僕には輝かしく見えたものです。
フィクションでもリアルでも、大人が本気で議論する機会が減ってしまった。だから『宝島』では“言葉”にすることが重要でした。コザ暴動の夜、グスクとレイが対峙して、それぞれの立場から想いを全力でぶつけ合う。これは原作を踏まえた部分ですが、レイは“沖縄独立論”を主張します。本土復帰ではなく国家の首都の座を獲得する、そして幼なじみのヤマコ(広瀬すず)を首相にすると。彼はとことん本気です。言葉尻だけ捉えると幼稚に思えるかもしれないけど…」
――いや、レイの言葉は、ラジカルに暴走してしまう実際の革命組織の行動原理をリアルに踏まえたものだと僕は理解しています。もちろん極端で危険な世界転覆の思想ではあるけれども、虐げられてきた側の理屈としては一本筋が通っている。レイの言葉に納得できる部分があるからこそ、グスクの「でもよ、俺は諦めんよ」という未来の可能性を探る言葉が際立つんですよね。
「まさにそうです。あの台詞はグスクが、本来心根の優しいレイと久々に再会し、その変貌ぶりに驚いて思わず口にした言葉なんです。だからこそグスクはせつない顔をする。それが“ドラマ”なのだと思います。歴史の中から、と同時に、登場人物たちの個人史の中から零れ落ちるように生まれるドラマ。偶発的でありながら、必然にも見える、あの妻夫木くんの表情を撮りながら、僕も泣いてました」
「沖縄の歴史を、沖縄出身ではない本土の人が身ひとつで体感することで、相互理解の入り口が生まれる」
――すばらしかったです。やっぱり『宝島』は“対話の映画”だと感じます。
「ええ。知らないものを知ろうとする…それがコミュニケーションの本質ですよね。キャスティングも、今回は意識的にウチナンチュではない俳優をメインに据えました。いまの時流では、例えばマイノリティの役は実際にその属性を持つ俳優が演じるべきという考え方が主流になりつつあります。でも、それではフィクションの想像力はどこへ行くのか?“自分ではない誰か”になることこそが芝居の本質ではないのか?と」
――演技と当事者性の問題ですね。僕もよく考えます。
大友「そう。演技は他者理解の方法論です。沖縄の歴史を、沖縄出身ではない本土の人が身ひとつで体感することで、相互理解の入り口が生まれる。演技とは役柄との“対話”なんだと思います」
――さらに映画完成後も、大友監督や妻夫木さんは観客と対話されていますね。
「今回はもう衝動に近いです。自分も劇場に足を運んで、観た人の感想を直接聞きたい。本当にどう思ったかを知りたい。その声の質が、僕にとっての希望につながる。オンちゃんの『そろそろ本当に生きる時が来た』という言葉もそうですが、レイも言っているように、いまは『すべて言葉にして言え』と求められる時代になってきた。だからこそ、SNSで吐き捨てるような言葉でも、ポジショントークで目立つための大声ではなく、ちゃんと議論できる言葉で話すべきだと思う。遠慮してる場合じゃない。そうしないと、もう一度“生きる”ことができない気がする。これはいまの日本にとって、すごく大事なことだと思いますね」
取材・文/森直人