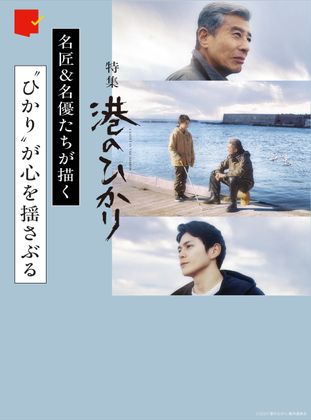大友啓史監督が映画『宝島』に込めた想い「『これが最後の作品になってもいい』とそのくらいの覚悟で臨んだ」
「見て見ぬふりをしてきた日本人として、贖罪の意識を背負って描かなければならない」
――大友監督は2001年に始まったNHK連続テレビ小説『ちゅらさん』でも沖縄を描かれています。ドラマは大きな人気を集め、続編も制作されました。
「はい。当初は三番目の演出家として、続編2作はチーフとして参加しましたが、沖縄の方々が喜んでくれたし、自分にとっても大切な経験でした。ただ、主人公は本土復帰の年、1972年生まれという設定で、復帰前の沖縄には踏み込んでいませんでした。“癒やしの島”として受け取られることへの、漠とした違和感もありました」
――その違和感が『宝島』につながっている?
「そうですね。もっと歴史に深く潜り込んで、沖縄の人々の優しさの裏にある強さの理由を探りたかった。それは戦争やアメリカ統治下の記憶と深く関係している気がしていたんです。そんななか、プロデューサーの五十嵐(真志)くんが『宝島』の原作を持ってきてくれて、一晩で読み終え、『これは絶対にやりたい』と思いました。
僕には“声なき声に寄り添いたい”という想いがずっとあって、どこに目線を置くかと問われれば、迷わずそちら側に置く。今回の映画では、その立ち位置を改めてしっかりと取らなければと思いました。
映画化までには新型コロナウイルスの影響もあり6年かかりましたが、『これが最後の作品になってもいい』とそのくらいの覚悟で臨みました。この作品は、商業的な視点では向き合えないテーマ、だからです。
2010年のNHK大河ドラマ『龍馬伝』の時も、改めて坂本龍馬を“いま”に刺さるリアルな存在として描くなら、自分たちも変わらなければと、撮影方法まで変えました。今回の『宝島』も、ウチナンチュ(沖縄人)ではない僕らは当事者にはなれないけれど、見て見ぬふりをしてきた日本人として、贖罪の意識を背負って描かなければならないと思いました。沖縄の人々が長い間日々背負ってきたリスクに比べれば、映画にかけるリスクなど小さい。そう自分に問いかけ続けましたね。だからこそ、3時間11分という長さも含め、どう受け入れてもらうかをずっと考えながら進めてきました」
「なぜ自分たちは、そして世界は沈黙しているのか…そんな想いが、僕たちが生きているこの時代にずっと張り付いている」
――大友監督の作品を拝見してきて、「龍馬伝」以降、また新たなメルクマールが生まれた印象があります。ただ『宝島』には、決定的に違うものを感じました。これは本質的に、大友監督の“個人映画”ではないでしょうか。
「まさにそういう部分はあると思います。『龍馬伝』では“憎しみからはなにも生まれない”というテーマを意識していましたが、『宝島』は2020年以降の社会状況…パンデミックやウクライナ、ガザなど、無力感に覆われた時代の中で生まれた作品です。そうした現実を前に、思想としてのリベラリズムが機能しなくなっていると感じました。戦後民主主義教育を受けた世代として、リベラル思想の普遍性を信じてきましたが、いまでは特定の政治的立場に閉じ込められてしまっている」
――その感覚、よくわかります。
「僕は“ひとつの命は地球より重い”と教わった世代です。隣人の命を大切にする、それが生き方の基本だと。でもいま、その主張が通じにくくなっている。例えば(ステーヴィン・)スピルバーグの『シンドラーのリスト』(93)には、“目の前のひとつの命を救える者だけが世界を救える”というメッセージが込められている。それは聖書の一節でもあります。『宝島』も、まさにその想いで作った作品です」
――『シンドラーのリスト』は3時間15分。『宝島』とほぼ同じ尺ですね。
「その点にも勇気づけられてきました」
――オンちゃん(永山瑛太)はまさにシンドラーですね。僕が『宝島』を観てパッと連想したのは、ブラジル映画『シティ・オブ・ゴッド』(02)でした。
「『シティ・オブ・ゴッド』は企画段階から参考にしていた作品のひとつです。ほかにも(マーティン・)スコセッシの『グッドフェローズ』(90)、(ベルナルド・)ベルトルッチの『1900年』(76)や『ラストエンペラー』(87)など、歴史や社会を深く描く映画に影響を受けています。『宝島』では、じっくりと腰を据えて観るような映画を作りたいという想いが強かったですからね。
そうしているうちに、個人的な感情がどんどん入り込んできました。ウクライナやガザのニュースを見て、自然と涙が出ることがある。美しい街が爆撃され、母親や子供たちが泣き叫んでいる映像に、なぜ人間はこんな野蛮に戻るのかと胸が裂けるような思いになる。遠く離れた国にいてなにもできないけれど、痛ましい現実に心が揺さぶられる。なのに、なぜ自分たちは、そして世界は沈黙しているのか…そんな想いが、僕たちが生きているこの時代にずっと張り付いていることに改めて気づいたんですね。
でも、その苛立ちを前面に出すのではなく、映画を作る者として、どこかに忍ばせるように反映させ、静かな共鳴に繋げたい。そしていまの時代に、特に若い層にどうやれば届くのだろうか。長尺かつタイムスリップのような仕掛けもないなかで、どう伝えるかという葛藤がずっとありました」
――『宝島』には若い世代にも届く力があると信じています。時期的に『るろうに剣心 最終章 The Beginning』(21)や『レジェンド・オブ・バタフライ』(23)と並行して作られていたわけですよね。この2作と『宝島』は、完全に通じているように思います。
「おっしゃるとおりです。『レジェンド・オブ・バタフライ』の時、僕は半ば本気で『独裁者の孤独』というタイトルにしたかったんですよ。あの映画は織田信長を通して独裁者の心情を描こうとした試みで、それは現在の世界を牛耳る強権的なリーダーの肖像に通じるものではないかと」