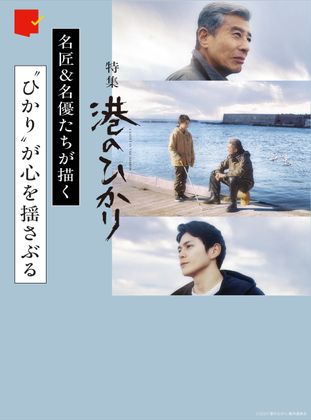大友啓史監督が映画『宝島』に込めた想い「『これが最後の作品になってもいい』とそのくらいの覚悟で臨んだ」
第160回直木賞をはじめ、第9回山田風太郎賞、第5回沖縄書店大賞の三冠に輝いた作家・真藤順丈の同名小説を映像化し、191分を息もつかせぬハイエナジーで駆け抜ける圧巻のエンタテインメント超大作となった映画『宝島』(公開中)。
アメリカ統治下の戦後沖縄を舞台に、1952年から約20年にわたる物語が展開する壮大な人間ドラマ。激動の時代の中で、友情や希望の行方、自由への憧れが交錯し、人々の絆が描かれていく。
MOVIE WALKER PRESSでは、本作のパンフレットにも寄稿している映画評論家の森直人による、大友啓史監督のインタビューを実施。「『これが最後の作品になってもいい』とそのくらいの覚悟で臨みました」と明かした大友監督が、『宝島』の制作に情熱を注いだ理由が見えてきた。
「沖縄の歴史を全身全霊で追体験してもらうには、大スクリーンで映像と音を浴びる映画がやっぱり最適」
――映画『宝島』、心底圧倒されました。驚くほどすばらしかったです。今回、大友監督は主演の妻夫木聡さんと共に「全国キャラバン」として日本各地を回る活動もされていますよね。トークショーやティーチインで、映画についてはもう語り尽くしているのでは?
「いや、まだまだ全然話し足りないくらいです。“ちゃんと届ける”ということを考えると、すべてが一期一会なんですよね。だからこそ、まったく手を抜けない。鮮度を落とさず何度でも同じことを語れるかどうかが試されている気がします」
――ライブという意味では、映画もトークも“一回性”の体験ですものね。その時が、人生を変えるような決定的な出会いになるかもしれない。
「そうなんです。『宝島』には本当に大切なものが込められているからこそ、何十回でも何百回でも語らなきゃいけない。妻夫木くんがドラマ撮影に入ってからは、僕ひとりでも地方を回りました。
初めてお会いする劇場支配人の方々と話すと、思いがけない共鳴があるんです。例えば、あるイオンシネマの支配人が、カンボジアの炊事事業で水事情の研修に行った話をしてくれて、『宝島』が描く戦後沖縄の世界と重なる部分があったとおっしゃっていました」
――確かに、『宝島』が描く「戦果アギヤー」(アメリカ統治下の沖縄で、生き抜くために米軍基地から医薬品や食料などの物資を盗み出し、住民に分け与えていた若者たち)の存在は、いまも世界中にいるストリートチルドレンと重なりますよね。
「そうなんです。真藤順丈さんの原作を読んだ時、これは“いまの物語”でもあると感じました。そして、この作品のメッセージを届ける方法として、作品世界を丸ごと体験してもらうには、映画が最適だと思ったんです。
実はテレビドラマで、という話もあったんです。確かに1952年から約20年、戦後沖縄のクロニクル(年代記)を描く壮大な物語なので、例えばリミテッドシリーズのような形式だと収まりがいいのかもしれません。けれど頑なにずっと断ってきました。その理由が日本各地の劇場を回るうちに自覚できてきたんです。映画じゃないと、おそらくただの情報として消費されてしまう。でも映画なら、観た人の心にずっしり残るものがある。沖縄の歴史を全身全霊で追体験してもらうには、大スクリーンで映像と音を浴びる映画がやっぱり最適なんです」
――3時間11分という長尺にも関わらず、編集で削ることなく公開されましたね。
「プロデューサーや配給の皆さんが、編集初期に観てもらった段階で、『これはワンシーンも切れない』と、一緒に頭を抱えてくれたんですね。僕は最後まで不安で、『本当にいいんですか!?』と一番ビクビクしてました(笑)。でも、最終的には皆さんがこのままで勝負しようと言ってくれて、自然と一本の映画として成立していったのは、本当に驚くような体験でした」
――体感時間があっという間でした。ジェットコースターのような映画ですね。
「ありがたいことに、そう言ってくださる方が少なくありません。全国キャラバンの前に関東の大手興行会社でプレゼンした際も、1時間ほどかけて『この上映時間でなければ描けなかった』と丁寧に説明させていただきました。話を聞いてくださった方の中には涙を流された方もいました。
沖縄戦では多くの犠牲があり、いまも米軍基地の7割が沖縄に集中している。日本人には、沖縄に対する贖罪の意識があるのかもしれないと感じました。
劇場を回っていても、返ってくる反応が尋常ではありません。言葉にならなかった想いが映画を通して言葉になり、僕や妻夫木くんも毎回泣かされるような瞬間がありました。こんな経験は滅多にありません。皆さんからの熱い反応をいただくことで、この映画を作った意義を僕自身、何度も噛み締めています」