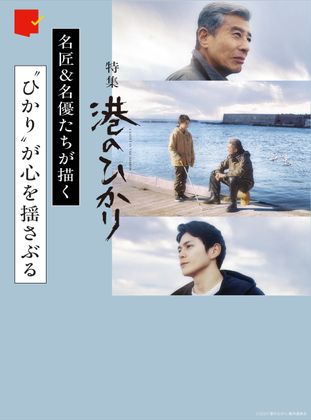森下suuが感銘!手話がつなぐ心と恋――漫画「ゆびさきと恋々」に重なる映画『君の声を聴かせて』の世界
「手話に対してもとても誠実に向き合っていることが伝わってきました」(マキロ)
――劇中における手話の表現で、印象的だったことがあれば教えてください。
マキロ「役者さんは、この映画のために手話を覚えたということですよね…。すべてが自然に感じられて、すごかったですね。指先ってすごく感情が表れるところだと思うので、『ゆびさきと恋々』も手ではなく“ゆび”という表現を使っているんです。本作でも役者さんが指先からも感情が伝わるような演技をされていて、手話に対してもとても誠実に向き合っていることが伝わってきました」
なちやん「皆さん、バーっとおしゃべりをしているように手話をされていましたよね。なんの違和感もなく彼らの会話を感じられたので、本当にすごいなと。『ゆびさきと恋々』では逸臣がまだあまり手話を使うことができない時代もあるので、ボードや携帯のメッセージで書いた文字を見せるというシーンもあるのですが、本作では3人とも“手話ができる人”という設定なので、全編を通して会話の中心が手話になります。あそこまでできるようになるには、役者さんは相当な練習をされたのだろうなと思います」
――登場人物が手話を通して心がつながっていく姿を描く本作は、「ゆびさきと恋々」との重なりも感じられます。お2人が、手話を使った作品を紡ぎ出す上で心がけていることはどのようなことでしょうか。
マキロ「ろう者の方に敬意を持ち、家族や友だちなどその身の回りにいる人たちも、傷つかないような表現をすること。それはとても大事にしています。そして、本作にも同じような想いを感じました。決してお涙ちょうだいの悲劇であったり、過剰に社会になにかを訴えようとするのではなく、ヨンジュンとヨルムという人を見つめている。障がいを題材にしようとしているのではなく、どこにでもある恋愛だという描き方をしている点は、私たちが大切にしていることでもあります」
なちやん「手話を使うキャラクターを描く際、私自身はキャラクターの目線をとても大事にしています。手話でやり取りをするシーンでは、相手に対してキャラクターの顔が横を向いていたり、目線が違うところを向いていたりするわけにはいきません。本作でも、目線や構図にはかなり気を遣って取り組んでいるのではないかと感じました。またアップで表情を描きたいと思っても、手元までしっかりと見せていくことになるので、構図が固定されてしまう場合もあります。本作では坂道を利用するなど、手元を見せるために構図にも工夫が込められていて、すごいなと思いました。ヨンジュンとヨルムの衣装も、手話が見やすいような色を選んでいるのではないかと思います。向き合っている相手と共に、観客にもきちんと手話を伝えたいという真摯な想いを感じました」