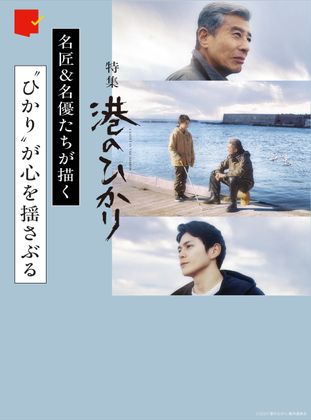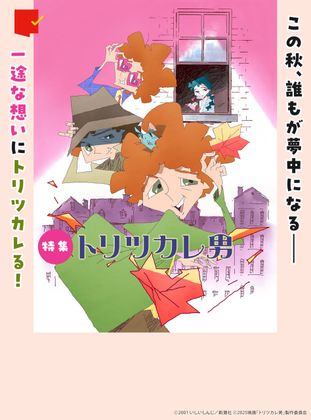呪物コレクター・田中俊行が語る『火喰鳥を、喰う』における呪物の在り方「戦死者の呪物を利用するのは、理にかなったすばらしい着眼点」
第40回横溝正史ミステリ&ホラー大賞受賞作を映画化した『火喰鳥を、喰う』が10月3日(金)に公開される。強い思念が込められた“死者の日記”がもたらす恐怖を描いた本作は、呪いによって日常が一変していく様をミステリアスに描いた衝撃作だ。そんな本作を、怪談師として活躍している田中俊行がひと足早く鑑賞。呪物コレクターで火喰鳥の骨を使った呪物も所有しているという田中が、独自の視点で本作の魅力や見どころを語ってくれた。
信州で暮らす久喜雄司(水上恒司)と妻の夕里子(山下美月)のもとに、太平洋戦争の激戦地ニューギニアで戦死した祖先、久喜貞市(小野塚勇人)の遺品である従軍手帳が届けられる。そこにはジャングルで米軍や飢えと戦う過酷な日々と、生への強い執着が綴られていた。ところが日記に触れた久喜家の人々は、次々に怪異や悪夢に見舞われていく。その原因を探るべく、夕里子は知人の超常現象専門家、北斗総一郎(宮舘涼太)に協力を依頼。調査を始めた雄司たちは、やがて衝撃の真相にたどり着く。
「使い方によって、いいものにも悪いものにもなってしまうのが呪物」
500点を超える呪物を収集している田中は映画を観終え、「日記が書かれた従軍手帳は呪物ですね」とひと言。「呪物に惹かれる自分としては、人の執着の強さや呪物によって起きる怪異が描かれるなど、たくさんのポイントがあって通じるものがありました」と感慨深げに振り返る。戦死した貞市の遺品である“死者の日記”が届いたことで、世界そのものが一変していく壮大な世界観にも驚かされたという。「手帳を手にしたことで、世界線が変わってしまう展開も興味深かったです。呪物を題材にした映画には『死霊館』や『フンパヨン 呪物に隠れた闇』、古くは『インディ・ジョーンズ』シリーズなどたくさんありますが、呪いによって過去や未来まで変わってしまうこれまでにない作品ですね」。
祖先の思念が込められた呪物を軸に展開していく本作。呪物と聞くと忌まわしいものを連想するが、本来は神聖な存在なのだという。「依頼を受けた呪術師が、願いを込めて精霊を宿したものが呪物です。人知を超えた力が宿ると信じられていて、そこには禍福と言って災いだけでなく福も内包されています」。基本的に呪物には、いいものと悪いものが混在していると指摘する。「呪という字は“のろい”のほかに“まじない”とも読めるんです。ですから人をのろうことも守ることもできる。手にした人の使い方によって、いいものにも悪いものにもなってしまうのが呪物です」。呪物は呪術師によって作りだされるだけでなく、自然から生まれるとも考えられているそうだ。「人の願いや悩みなどを込めて作られるものですが、それだけでなく自然発生的に思いが宿る呪物もあります。いわゆる祟りの木とか、触ってはいけない岩などで、これらも呪物に分類されます」。