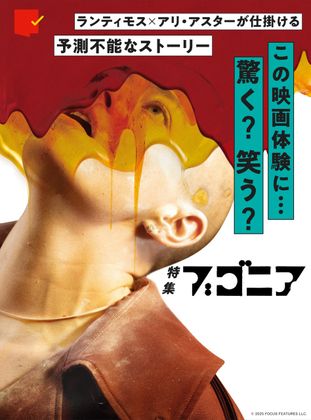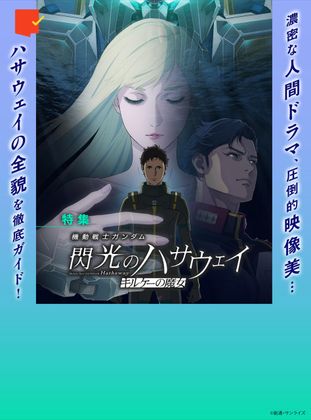妻夫木聡&広瀬すず&窪田正孝、運命に導かれて出会った映画『宝島』を語る「徹底的に取り組まないと終わりにはできないものがあった」
「『これはあなたの物語だよ』と伝えられたらいい」(妻夫木)
――これから劇場公開になる『宝島』ですが、間違いなく大きな衝撃と感動を持って迎えられると思います。皆さんは本作が世の中に向けてどのように届けばいいなとお考えですか?
妻夫木「多分みんな沖縄に対してそれぞれのイメージを持っていますよね。例えば青い海と太陽に恵まれた人気の観光地だとか、明るくゆったりした癒しの雰囲気だとか。もちろんそういったことも沖縄の魅力だとは思いますが、ただ知れば知るほど、本当に僕らの知らないことが多いんだなっていう場所です。
沖縄県北谷町の砂辺という地区があって、すごく美しい場所なんですよ。砂辺海岸というビーチはサーフィンやダイビングの有名なスポットでもあって、一見トロピカルムードの遊び場がいっぱいあるんです。そこにある日、僕の親友が連れていってくれたんですけど、実は『宝島』でも描かれた嘉手納空軍基地(極東最大規模のアメリカ空軍基地)に隣接していて、戦闘機がゴーッとすごい音を立ててすぐ近くを飛んでいく。すると親友が『妻夫木、これが沖縄よ』って言うんですね。もうズーンときて。僕たちはカフェにいて、ゆっくりお茶でもするのかなと思っていたんですけど、自分が何気なく見ていた風景の奥にある歴史や現実が一気に迫ってくるような気がしました。
こういう僕自身が沖縄についていろいろ感じてきたことが、『宝島』という映画には全部流れ込んでいるように思います。自分になにができるかわからないけれど、役者をやっている身としては精一杯いい芝居に変えて発信していくしかない。試写を観終わった時に思ったことですが、この映画は復帰前の沖縄を舞台にしているけれど、日本の話なんですよね。だから『これはあなたの物語だよ』と伝えられたらいいですね」
「ちゃんと責任や理想や覚悟を持ってやれば、そこに生きた人間の息吹を伝えることもできる」(窪田)
――いまおっしゃったこと、世界中のあらゆる場所に応用できる気がします。
妻夫木「そうですね。いろんな国や場所、地域には、表面的に見えているものだけじゃない固有の歴史や現実がある。僕らはそれを知る必要がある。決して他人事ではなく、どこかで自分とつながっているから。そういったメッセージが伝わるとうれしいです」
広瀬「妻夫木さんは沖縄にたくさん知り合いがいらっしゃって。クランクインの前日にも、あるご家族のお家に伺わせてもらったんです」
妻夫木「そこでカチャーシー(沖縄の伝統的な踊り)を踊ったんだよね、みんなで」
広瀬「そうなんです(笑)。三線に合わせて。あの時間は本当に楽しかったです。映画の中でカチャーシーを踊るシーンが何度かあったので、撮影に活かすこともできました。
今回とてもありがたかったのは、ヤマコを演じるための時間を十分にいただけたことです。私はまだ10代の時に李相日監督の『怒り』という映画でも今回につながるテーマ(沖縄とアメリカ軍の関係)を持った役を演じました。だからこそ実体験とまではいかないけど、役を通して当時感じたことが意外と抜けなくて、どこかその延長で『宝島』のヤマコという役に出会った気がしています。今回は撮影がない日も『宝島』の世界と向き合いながら、その時代にこの環境で生きていることの意味や、現在とのつながりを考えることができましたし、沖縄の方々や土地からはものすごいエネルギーをいただきました。自分にとっても大切な作品になりましたので、皆さんにも楽しんでいただければうれしいです」
窪田「沖縄での撮影期間は約2か月あったんですね。その間、毎日沖縄のものを食べて、沖縄の空気を吸って、どんどん肌が焼けていき、台詞で沖縄弁を喋るたびに、僕はレイになれていく気がしました。ウチナンチュではない自分がこんなことを言うのは憚れますが、自分はいまここで生きているんだ、という体感がしっかりあったんですよね。エンタテインメントというものは事実をいかようにも変える力があると思います。どこをトリミングするかで全然伝わり方が違うから。もちろんこれは危険な側面も含んでいますが、ちゃんと責任や理想や覚悟を持ってやれば、歴史の上澄みだけでなく、そこに生きた人間の息吹を伝えることもできる。
そこに『宝島』はフォーカスしているからこそ、グスク、ヤマコ、レイ、オン、それ以外のキャストから見た歴史を、沖縄から世界に発信していける作品なのかなって思いました。人間は愚かだから同じことを繰り返してしまう。それは過去の歴史で証明されていますし、いまも戦争はなくなっていない。誰かがなにかをしなきゃいけないけど、ひとりだと無力さを感じますよね。だからこそチームでこの作品が出来たと思うし、自分もレイとして作品の一部になれたことが光栄です。僕らが全力で沖縄に向き合った想いを、次の世代につないでいけるんじゃないかなと思っています」
取材・文/森直人