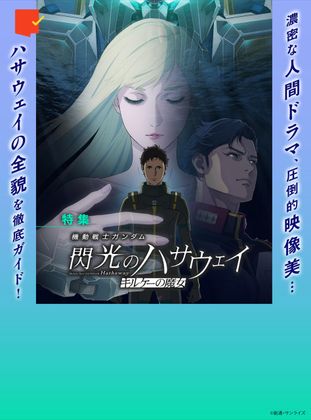石川慶監督が『遠い山なみの光』で描いた「記憶の物語」の伝え方。日本外国特派員協会で記者の質問に回答!
映画『遠い山なみの光』(9月5日公開)の「日本外国特派員協会 上映会」が8月20日、公益社団法人 日本外国特派員協会(FCCJ)にて開催。上映後には石川慶監督が登壇し、海外メディア向けの記者会見に応じた。
本作は戦後間もない1950年代の長崎と1980年代のイギリスで、女性3人の記憶に隠された嘘と真実を紐解いていくヒューマンミステリー。原作の同名小説はノーベル文学賞受賞作家、カズオ・イシグロのデビュー作。第78回カンヌ国際映画祭のある視点部門への正式出品され世界から注目を集めた本作は、現地時間9月4日より開幕する第50回トロント国際映画祭スペシャル・プレゼンテーション部門に正式出品されることが決定している。
FCCJでの会見について「今回で3回目になりますが、刺激的な質問をいただくことが多いのでみなさんの感想を楽しみにしています」とあいさつした石川監督。ノーベル文学賞受賞作家との仕事について「今日もこの場にカズオさんがいてくれたら…と思っています」とにこやかに答えた石川監督は「最初はすごく緊張したけれど、本当にチャーミングで気さくな方です」とイシグロの印象を語る。イシグロとの打ち合わせで意識していないとどんどんほかの映画の話へと脱線してしまうほど盛り上がることも多かったと振り返っていた。原作はイシグロのデビュー作。「最初の小説なので、いろいろな間違いもあるけれど…と言いながら、いまだったらこうするといったアイデアを気さくに言う方です」とイシグロとのやりとりを紹介していた。
物語の舞台は戦後復興期。戦時中の凄まじい思い出は、忘れたいと思いながらもキャラクターに出てしまうもの。この映画でもキャラクターの内面にもなにか影響しているものがあると想像したという記者には、同じ時代を舞台にした小津安二郎の映画『東京物語』(53)が思い浮かんだという。この記者から「キャラクターを作り上げる際には小説だけを参考にしたのか、ほかの作品も参考にしたのか」と問われると長崎、原爆というものを扱うにあたり「いま、自分たちの世代がなにができるのかを考えるとすごく難しい映画でした」と答える。続けて「小津、成瀬(巳喜男)の映画を参考にしながらも、自分たちのストーリーテリングでこの物語を語っていきたいという想いがありました」とし、当時のファッション、食べ物など様々な資料を漁り、手がかりは特定の作品ではなく当時の事実が書かれた資料だったと説明していた。
また、三浦友和が演じる緒方のシーンが小説よりも多く登場することで、小説で理解しきれなかったところが、映画で補足され物語を深く理解するきっかけになったと感謝した記者からの「いまの時代にあわせて描くためにどこを補足し、どこを変えたいと思っていたのか」との質問には「僕はイシグロ文学の大ファンで『日の名残り』が大好き。カズオさんは緒方というキャラクターをとても気に入っていたけれど、(『遠い山なみの光』では)十分に描けなかったとおっしゃっていて。女性たちの物語ではあるけれど、その裏で男性たちがどう生きていたのか。緒方の息子の二郎(松下洸平)もそういった理由で膨らませて作っています。そのあたりをおろそかにしてはいけない。ひとりひとりのバックグラウンドを見つめたい、リアリティを持って描かないといまの人には届かない」と考えていたと伝えていた。
「いつも複雑で重いテーマをあえて見つけているのか」という質問に「どうだろう…」と微笑みながら首を傾げた石川監督。「複雑なものを選んでいるつもりはないけれど、映画は何年もかかる仕事になってくるし、それだけの時間をかけてもどこかに消化しきれないものが出てきます。必然的になかなか答えがでないものに『なってしまうのかな』と思っています」と結果的に出来上がってしまうものが「複雑になっているのかも」と説明していた。
戦後80年のタイミングでの映画化となったことについては「カズオ・イシグロ作品はいつか映画化したいとは思っていました。でも、原爆や戦争に対しては自分たちのトピックではなく、もっと上の世代、経験した人たちがやるべきトピックとも考えていました」と語った石川監督。「真似しても近づけないと思っていたけれど、自分たちのストーリーじゃないと逃げていたら、記憶の話がこれからは記録となりもうすぐ歴史になってしまう(タイミング)」と考えたとし、「小さい記憶の物語として自分たちがやる必要がある」と付け加える。さらに「自分がすごく勇気づけられたのが、カズオさんがイギリスから長崎を思い、英語でこの物語を書いたということ」だとし、「この距離感は自分たちのジェネレーションにも、(長崎、原爆、戦後)というトピックに対してもすごく近いと思いました。だからこそトレースするのではなく、自分たちのやり方で語れるんじゃないか」と映画化に向けて動くことができた理由を明かしていた。
また1980年代の悦子とニキの関係性に触れ「これは悦子の記憶の物語。ニキが悦子の話を聞くなかで、全部を理解する必要はないと思っていました」とのこと。記憶の一部がおぼろげで、事実かどうかわからない部分があるのは、現実でもあることとも話し、「全部分かったとは思えないけれど、全部引き受ける」というニキのような渡し方が、歴史の継承であるとまとめ、「そうやって伝わっていくものだなと思いました。母と娘の小さな物語だけど、僕にとっては大きなトピックに見えていたのかもしれません」と改めて、本作で描きたかったとにも触れていた。
取材・文/タナカシノブ