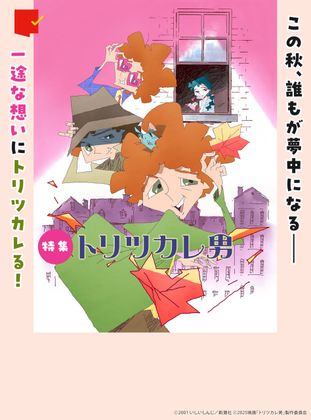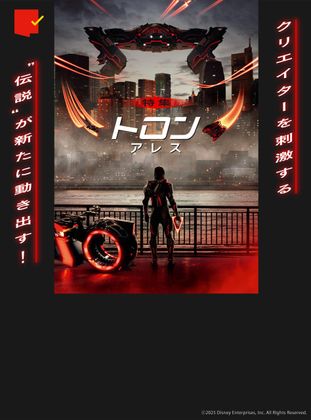井上伸一郎と氷川竜介が”おたく文化史”を語り合う。アニメ業界の”裏側の歴史”を残す意義と、「メディアミックスの悪魔」執筆裏話
「それまでの”ガンダムのようなものを作ろう”という流れから、”エヴァのようなものを作ろう”と、流れを大きく変化させました」
――角川書店の初期、井上さんにとって大きな転機だったのは、どんなことでしたか?
井上「佐藤良悦さんが創刊後2年で会社を辞めたため、改めて『ザテレビジョン』の正社員として採用されたのが、キャリアにおける主要な転機ですね。その後、新創刊の女性雑誌『ChouChou(シュシュ)』を担当しますが、そのころ角川歴彦氏が退社する事件が起きます。自分も会社を辞めようと思いました。でも『ChouChou』には手ごたえもあってすぐには退社できなかったし、あるビデオメーカーさんからお誘いも受けましたが、1年後に角川歴彦さんが角川書店に戻ってきて『残れ』と言われたため、退社を思いとどまりました」
――その言葉が歴史を変えましたね。井上さんはいろんな変革を起こされますから。
井上「歴彦さんがいったん会社を去る前に、月刊漫画雑誌の創刊を提案していたんです。『機動警察パトレイバー』の初期から企画に関わっていたゆうきまさみさんが『少年サンデー』に漫画版を連載したことが、プロジェクトを大きく成功させました。それを見て、漫画の重要性を痛感していたからです。『ニュータイプ』増刊として『コミックGENKI』を発刊し、一定の成果が出たため、漫画事業を確立すべく『少年エース』を創刊するんですね。漫画雑誌単独での収支は難しくても、単行本コミックスとセットにすれば黒字化できる構造です。この成功によって、文芸の会社であった角川書店においても”漫画は力がある”という認識が広まりましたし、その時期は社内での協力体制構築にも尽力しました」
――「少年エース」は1995年のテレビ版『新世紀エヴァンゲリオン』のコミカライズを掲載して躍進しますから、グッドタイミングだったわけですね。
井上「1990年代は、『エヴァンゲリオン』の登場がアニメ業界における大きな転換点となりましたね。それまでの”ガンダムのようなものを作ろう”という流れから、”エヴァのようなものを作ろう”と、流れを大きく変化させました。それだけではなく、深夜アニメが激増し、ビデオメーカー、レコード会社、出版社、ゲーム会社などが製作委員会を組み、直接スポンサーとなる構造に変化しました。映像メディアもLDからDVDへ移行し、映像がより身近なものとなって、『ニュータイプ』もメーカーからの広告収入が非常に増えた時代です」
「IPとして変換し、可能な限り多くの人に知ってもらいたい。それが私の考えるメディアミックスであり、ファンを増やす”運動”や”流れ”」
――アニメ業界のビジネス構造が次第に変化するなかで、井上さんはメディアミックス戦略の最先端を走っていたと思います。井上さんにとっての”メディアミックス”とは?
井上「そうですね。今回の本の執筆の背景には、アニメ業界の市場が国際的になっている現在、アニメを支えるメディアミックスの起源から現在までの成り立ちを書き残したい、そんな想いもありました。起源と言うと、1960年のテレビ映画『快傑ハリマオ』の時代からコミカライズでのメディアミックスは存在します。明確にメディアミックスを意識した人物、具体的にはプロデューサーの西村俊一さん(当時、宣弘社)がキーマンと考えています。それ以前も映画やドラマの漫画化があり、『笛吹童子』などラジオドラマや紙芝居の映像化という記録に残りにくいメディアミックスの萌芽は多数あったはずです。
私の考えるメディアミックスの本質と定義は、単なる小説から漫画、漫画からアニメへの媒体変換ではないんですね。それは”目的”に主眼を置いているからです。つまり、小説や漫画だけではお互い接点のなかった読者、ファン、視聴者を獲得する。その目的意識の有無が違います。作品の魅力を近年の言い方だとIP(知的財産)として多角的なメディアに乗せられるよう変換し、可能な限り多くの人に知ってもらいたい。それが私の考えるメディアミックスであり、ファンを増やす”運動”や”流れ”であるとしています。書籍のタイトルを『メディアミックスの悪魔』としたのも、そういう理由です」
――なるほど。そうした流れとして捉えたからこそ、いま海外にまで拡がったと考えられるわけですね。井上さん御自身のキャリアも、その流れというか波に乗っていたように感じられます。
井上「そこも運が良かったと思いますね。2006年5月には代表取締役専務に就任しますが、その期間は半年ちょっとでした。2007年1月には社長に就任することが決定していたので、専務の期間は一種の勉強でした。社長就任時には『涼宮ハルヒの憂鬱』を京都アニメーションでアニメ化した最初のテレビシリーズが大ヒットし、原作の文庫シリーズも売れて好調なスタートを切りました。他にも映画の影響で『ダヴィンチ・コード』の文庫が大ヒットするなど、メディアミックスが関係した幸先の良いスタートを切れたと思っています」
――その後も多面的な活動で2024年にKADOKAWAを退職され、起業してアニメ業界を牽引されてきた井上さんですが、読者のためになにかヒントになるような「仕事術」があれば教えていただけますか? 例えば人と人をつなぐ工夫とか。
井上「なるほどね。”悪魔の仕事術”って、いいタイトルかもしれませんね。まずウソのように聞こえると思いますが、実はこう見えて、ものすごく人と会うのが苦手なんですよ。人に会うのって毎回プレッシャーで、なにもなければずっと一人でいたい人間なんです。でも人生っていうか、仕事は当然そういうわけにはいかない。そこはもう一所懸命、オンとオフを切り替えるようにしています」
――それは意外ですね。
井上「ですから、毎朝ものすごく気合を入れて目を覚まし、身体を覚ますことをルーティンにしています。起きたら朝風呂に入り、そこから朝ごはんを軽く食べて、それから40分ぐらいかけて軽い運動をするんです。そこでだんだん身体が目覚めていくわけです。人によっては通勤の時に歩くのでもいいし、自動車に乗るのでも良くて。なにかオンオフを無理矢理切り替えるルーティンが必要かなと思うんです。
あとは本書にも書きましたが、可能な限り人と会うこと。なるべくたくさんの人と会う機会を作る。一番いいのはパーティに出ること。単にご飯食べて帰ってくるんじゃなく、知らない人を含めていろんな人に挨拶して、関係性を深めるきっかけを作るということが、自分の中でいいのかなと思っています。とにかくいろんなところに顔を出せる限りは出すのが重要。いまでも家に帰ったあと深夜に『これから飲みに来い』みたいな電話がよくかかってくるんですけど、疲れているので行かなかった時に、『ああ、あのとき行っておけばアノ人に会えたのに』って後で後悔することが、いっぱいあるんですね」
――ありがとうございます。最後に私事ですが、たまたま私(氷川)も同じ3月にメディアミックスの話題を含む単行本「空想映像文化論 怪獣ブームから『宇宙戦艦ヤマト』へ」(KADOKAWA刊) を出しまして。井上さんとは1歳しか違わないから重なり合うところもあり、相互補完的なところもあって、ご縁だなと思いました。
井上「氷川さん、なんで同じ月に出版するんだよって思ったけど(笑)。私の場合は最初から評論的なものを書こうとは思わず、普通の人が知らない出版とかアニメ、自分を育ててもらったもの、仕事として携わってきたものの裏歴史みたいなもの提示したかったということなんですね。もっとこういういろいろな角度からの本が増えて、多角的な視点からアニメーション業界を語る書籍が増えたらうれしいですね」
――まさにそうだと思います。学術研究や文芸批評的なアプローチも良いんですが、そもそもアニメーション作品を成立させるための、社会的な営みへの関心が高まることを期待しています。
取材・文/氷川竜介