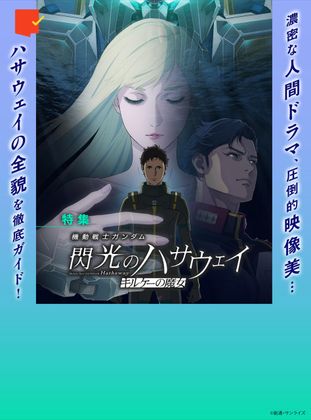井上伸一郎と氷川竜介が”おたく文化史”を語り合う。アニメ業界の”裏側の歴史”を残す意義と、「メディアミックスの悪魔」執筆裏話
日本のオタク文化とメディアミックス戦略を牽引してきた井上伸一郎が、自らの半生と業界の変遷を語る一冊「メディアミックスの悪魔 井上伸一郎のおたく文化史」。今春刊行された本書は、‟おたく第一世代“としての幼少期から、アニメ雑誌「アニメック」での経験、角川書店在籍時の歴代のプロジェクトの舞台裏まで、メディアミックスの現場にいた本人ならではの視点から、"おたく文化"がどのように社会に浸透していったのかをひも解く「おたく文化史」だ。
プロローグから「東京国際アニメフェア」のボイコットについての内幕が明かされ、井上がいかにアニメ文化に誠実でいるために闘ってきたかの片鱗が見える。本著の聞き手・解説を務めた評論家の宇野常寛氏の年代解説も、井上の熱にあてられ、次第に自身の青春期を振り返るような構成になっているのもおもしろい。
MOVIE WALKER PRESSではアニメ・特撮研究家の氷川竜介を聞き手にインタビュー。本書の執筆裏話から、メディアミックスの定義、アニメ業界の変遷、IPのロングライフ化とは?といった議論までを展開してもらった。
「アニメ作りの”裏側の話”を残さないといけないと、そんな問題意識が動機でした」
――まずはご執筆の動機からお願いします。
井上「きっかけは3年ほど前のことです。小牧雅伸さん(「アニメック」初代編集長)、ライターの近藤さん、池田憲章さん。皆さんまだ67歳前後なのに、相ついで逝去されたんです。『人はいつ死ぬかわからない』という想いが生まれましたし、特に小牧さん、池田さんにはもっと語っていただきたいことが多かったので、私自身も自分の体験を記録に残す必要性を感じました。
映画作り、アニメ作りでは監督を中心に”表の歴史”は残っていくものですが、『実はその裏側ではこんなことがあった』という話は、なかなか残っていかない。だからせめて自分が編集者やプロデューサーとして体験した”裏側の話”を残さないといけないと、そんな問題意識が動機でした。いま残しておかないと、永遠に忘れ去られてしまうこともあると思ったんです。例えば、ライトノベルの起源は諸説ありますが、スニーカー文庫、富士見ファンタジア文庫というレーベルがどんな意図で設立されたか、当事者の発言が少ない。スニーカー文庫の立ち上げ時、企画を理解できない年長の営業担当者に、角川歴彦さんが『これは立川文庫だよ(大正時代に講談、戦記など少年向けの小説を収録してヒットし、後の映画やテレビの娯楽作の原作を多数生んだ)』と説明した話は、私を含め、その場にいた数人しか知らないんです。こうした歴史的事実を記録に残していきたいんです」
――そうした記録書としての役割も担いなら、「メディアミックスの悪魔 井上伸一郎のおたく文化史」は自伝のようにも書かれています。
井上「担当編集からは、ビルドゥングスロマン(成長物語)のように自身の経緯を追って話すことで、読者に伝わりやすくなるというアドバイスを受けました。石原慎太郎さん(当時・都知事)との衝突から書き始めたのは、自分がどうして『漫画やアニメ、特撮を否定されると腹が立つ人間になってしまったのか』という理由を明確にしたかったから。たしかに幼少期の体験にルーツがあるんですね。若い世代にとっては”生まれる前の話”は知らないでしょうから、当時感じたことを振り返って探ることで、時代背景も伝わるだろうと」
――井上さんは1959年生まれですから、この世代は自分の成長とテレビ文化の成長が同期していたんですよね。
井上「ええ。中学生ぐらいになると『ルパン三世』や『海のトリトン』など、いままでより大人っぽい作品が出てきたことを実体験してきて、成人したころには”アニメの仕事”があるという。得をした世代ですね。ただ、前例がないから、自分が『アニメック』という雑誌で編集者になった時には、そもそもアニメ雑誌の編集者とはなにをする仕事なのか、それすら教えてくれないんですよ。ですから、自分で手探りで仕事を始めていきました。ただ、アニメックはすごく不思議な編集部で、出渕裕さん、ゆうきまさみさんたち同世代のアニメ関係者や漫画家たちが自由に出入りしていたんですね。特に編集部で原稿を書いていた自分より年下の會川昇さんが、高校生の時に脚本デビューしたときはショックを受けました。彼はシナリオライターになることを決め、着実に階段を登っていたんです。そんな姿を見て、『クリエイターではかないそうにない』と感じ、編集者としての道を定めました。クリエイターと読者をつなぐ役割で、それが重要であると認識したわけですね」
「記録に残っていないことも含めて、富野(由悠季)さんの“雑談相手”になれたっていうのが、一番の財産です」
――その頃の手ごたえはどんなものがありましたか?
井上「『アニメック』がやたらと文章が多い雑誌だった理由は明確で、お金がなかったのです(笑)。自分たちで原稿を書いたり、インタビューを取らせていただいたり、イラスト代わりに設定資料を使ったり…必死に誌面を作っていました。あと1982年の3月に『機動戦士ガンダムⅢ めぐりあい宇宙編』が公開された後、急に空白が――共通言語がなくなったみたいな感覚を覚えたんです。‟みんなが同じものを観て語る“機会が薄くなった時期というか。それを埋めるためにも、一生懸命文章を書いていたのかもしれません」
――井上さんの多彩なキャリアパスで転機となったのは、言うまでもなく角川書店(現:KADOKAWA)への移籍ですよね。
井上「ええ。『ニュータイプ』創刊当初2年4か月はフリーランス編集者として活動していました。それなのに角川歴彦さんの部数会議に出席させられていたりして。いまなら『ガバナンスが効いてない』と言われるでしょうね。当時は角川書店子会社の(株式会社)ザテレビジョンが雑誌制作のエンジンとして機能していました。テレビ情報誌としての『ザテレビジョン』は創刊当時は売れなかったんです。それもあって開き直って初代タイガーマスクや初代ゴジラを表紙に起用し、サブカルチャー色の強い誌面作りをしていたので興味があったんです。一般誌なのに富野由悠季監督の『聖戦士ダンバイン』を毎週カラー見開きで掲載するなど、ユニークな取り組みに注目していました。そして富野監督との交流を通じて『ザテレビジョン』の編集者とも出会い、原稿依頼を受けるようになって転職の機会を得たんです。角川書店はアニメ業界とは違う、一般に開かれた会社という印象も受けましたし」
――それが「ニュータイプ」創刊に結びつくわけですね。やはり富野さんとの関係は、井上さんにとって大きな財産ですか?
井上「非常に大きいですね。企画として形になったものもいくつもありますけど、記録に残っていないことも含めて、富野さんの“雑談相手”になれたっていうのが、一番の財産です。1983年の『幻魔大戦』以後、 角川書店が年に1回劇場アニメ映画を制作していましたから、必ずアニメ雑誌を創刊するだろうと予測していました。その創刊が決まって会議に呼ばれたら、池田憲章さんや徳木吉春さんたちアニメ誌編集の強力メンバーがいたので、『これはおもしろいものができるな』という強い期待を抱きました。当時の編集長は佐藤良悦さんで、最初の台割では投稿雑誌にする構想があったようです。でも自分も意見を出して記事ページを増やし、特集ページ全般を担当しました」
――本書の中では、創刊号は“65点”だと思った、というエピソードも登場します。
井上「良悦さんはもっとビジュアルで見せたい、という想いが強かったと思います。私は『アニメック』出身なので、とにかく文字が埋まっていないと不安になってしまう(笑)。お互いに満足していないポイントは違ったでしょうが、点数は一致していた。それからの雑誌作りで強く意識したのは”メジャー志向”ですね。創刊メンバーの一人は映画コーナーで素晴らしく美しいホラーファンタジー作品を取りあげようとしましたが、後に『東京ウォーカー』編集長として成功する情報ページ担当の土屋良彦さんと意見が衝突し、編集部を去ることになるんです。この出来事を通じ、『好きなだけで誌面を作ってはいけない』という現実を強く認識しました。土屋さんは徹底的に”分かりやすさ”を追求するので、私が好むひねった見出しはみんなボツにするんです。この”分かりやすさ”の重要性については、多くのことを学びました」