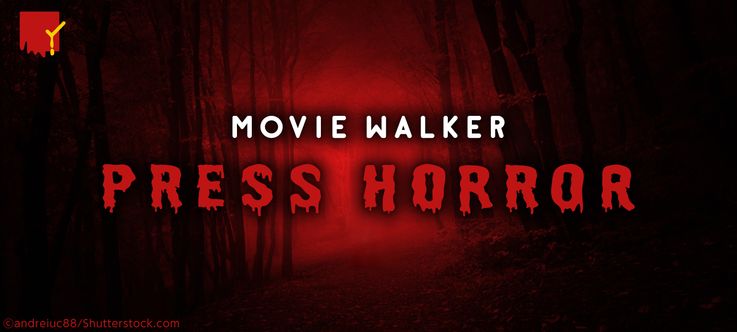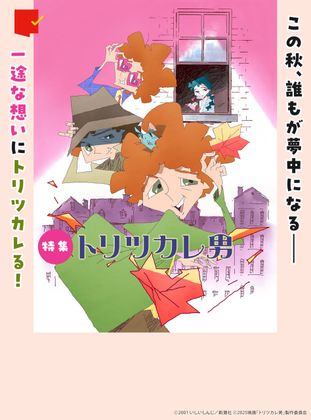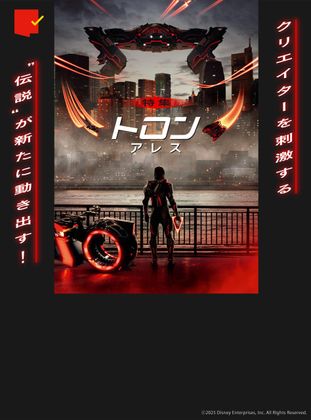気鋭監督JT・モルナーが『ストレンジ・ダーリン』で追求したユニークなホラー映画作り「映画監督になる前から、お化け屋敷の創造に関わってきた」
「フィルムが回っている音を聞き、それを目にすることで、映画作りのプロセスを真剣に受け止めることができる」
さらにスタッフの中で目を引くのは、撮影監督として俳優のジョヴァンニ・リビシが参加していること。『プライベート・ライアン』(98)や『ロスト・イン・トランスレーション』(03)、『アバター』(09)などの作品に出演し個性を発揮してきたリビシが、カメラの裏側に回っていることはちょっとした驚きでもある。「ジョヴァンニとは全米撮影監督協会賞の授賞式で知り合いました。私の映画に出演してほしかったのですが、当時の彼は映画に出ることより映画を撮ることに興味があると語っていたんです」と、モルナーは振り返る。
モルナーは、ここでも一緒に映画を作る仲間との緊密な関係を築いた。もちろん映画業界ではリビシの知名度は高く、彼の参加は『ストレンジ・ダーリン』の製作に良い作用をもたらした。リビシは製作も兼任し、本作の成功に大きな役割を果たしたのだ。
「LAにあるジョヴァンニのスタジオに招待され、彼が撮った短編や音楽ビデオを見せてもらったり、話し合ったりしましたが、映画の趣味が似ていることに気づき、一緒に何かをやろうということになったのです。それまでにも、彼は私が送った脚本の感想を述べてくれたことはありましたが、『ストレンジ・ダーリン』の脚本を送ったときは『一緒にやるならこれしかない』と言ってくれたんです。そこからはトントン拍子に話が進みました」
モルナーとリビシの共通認識は、昔ながらの映画作りをしたいということ。すなわち、デジタルのカメラではなく、フィルムで撮影することだ。デジタル撮影に比べて、これは予算も時間もかかるが、それでもモルナーには譲れない一線だった。「15年前に初めて短編を撮ったときから、フィルム撮影をしたいという意思は一貫しています。低予算製作なので、デジタルで撮った方が割安なのはわかっていますが、そこにはこだわっています」。ちなみにモルナーはデジタル撮影を否定しているわけではない。デジタルで撮られたものにも素晴らしい作品があることを認めている。
それでもフィルムにこだわる理由は、こうだ。「フィルムはどんなソフトウェアでも再現できない感覚を与えてくれます。白昼の場面では顕著ですが、手触りのような独特の感覚がそこにはあるんです。また、フィルム撮影は現場の環境を整えてくれます。クルーもキャストも、フィルムが回っている音を聞き、それを目にすることで、映画作りのプロセスを真剣に受け止めることができるんです」。デジタル撮影なら、すぐにその場で撮った映像を確認できるが、フィルムの場合は現像されるのを待たねばならない。必然的に、そこには綿密な準備が必要になり、スタッフ間の緊張も高まる。これこそがモルナーの求めた古き良き“昔ながらの映画作り”だ。
最後に、細かいことではあるが、映画の中でひとつ気になったことをモルナーにぶつけてみた。それは、劇中で何度かサブリミナルのような短いショットが盛り込まれていたこと。自分はいったい、何を見たのだろう?そう尋ねると、モルナーは笑ってこう答えた。「サブリミナルなのか否か、はっきりしないところがいい。 まさにそこがポイントでした。だから、あなたが何かを見たと思ったことをとても嬉しく思っています」。
煙に巻かれたかたちとなったが、いずれにしても『ストレンジ・ダーリン』が強烈な映画であることに疑いの余地はない。モルナー監督の術中に気持ちよくハマッてみてはどうだろう?
取材・文/相馬 学