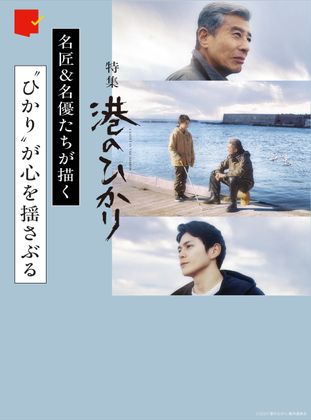大森時生と山中瑶子が語り合う、“打ちのめされた”映像体験。『サブスタンス』から得た刺激
「本作のようにスベるのを恐れない、強固なエンタメもぜひやってみたい」(大森)
――年齢を重ねていく女性の心理、“あるべき姿”を求める周囲の環境など生々しい現実を描きつつ、それらをしっかりとエンタメへと昇華させた映画だと感じます。ものづくりに挑んでいるお二人にとって、刺激を受けることはありましたか。
大森「僕は自分が制作するフェイクドキュメンタリーでは“エンタメ”に見えた瞬間に負けだと思っていて。現実に地続きの厭さを感じさせたいと思いながら作品づくりに臨んでいますが、『サブスタンス』のようにエンタテインメント的に強固に作り込まれた作品もいつかやれたらいいなと思っています。ただ本作のように振り切った、勇気が必要となる作品を生みだすためには、もう少し自意識からの解脱が必要だなと。スベるのが怖いなんて思わないような域に達したころ…いくつになるかわかりませんが、いつかぜひやってみたいです」
山中「わたしは本来ホラーが苦手ですし、痛いのも、びっくりしたりするのも、誇張した見せ方をする映画も苦手なんですが、この映画はとてもおもしろく感じて。なぜだろうと考えてみると、ファルジャ監督に強固な信念があって、映画のなかで起こることについてすべて責任を取ろうとしているからなのかなと思います。曖昧さというものに依拠しない、その振り切った気持ちよさに好感を持ちました。そして役者含め、チームの全員が監督のやりたいことを理解して挑んでいるということが感じられる映画です。そういった真摯なものづくりができることには、羨ましさも感じます」
――『あみこ』や『ナミビアの砂漠』などで、女性の生態を主軸に物語を描いてきた山中監督ですが、女性として、年齢を重ねる大変さについて感じたことがあれば教えてください。
山中「世間で話題になっていた(Netflixで配信されている、35歳以上の男女による恋愛リアリティショー)『あいの里』などを観ていても、女性は妊娠、出産など、身体にまつわるリスクや考えごとの多さに、男性との不均衡を感じます。わたしは最近、女性がすべてを諦めずに生きていくためには、心身ともにマッチョにならなければ叶わないんじゃないかと不本意ながら考えてしまっていて。そうでない方法を模索したいのですが、社会のシステムがそうなっていないことにぶち当たることが多いです。
本作では若くて美しい女性であるというだけで欲望され、そうではなくなったら都合よく切り捨てられるという構図が映しだされていますが、その社会を生みだし、取り仕切っている権力を持った男性たちの描かれ方には、むしろ爽快感もありました。でも結局、エリザベス自身が一番、自分を痛めつけ、傷つけているわけですよね。彼女は『美しくあれ』という言葉を浴び続ける職業に就いてきたことでそうなってしまっているので、とても痛々しくもあって、苦しい物語なんですけれど。だからこそ、クライマックスに向かって突き進んでいくエリザベスから、あらゆるものを超えて誰も到達できない域に達したんだ、他者を圧倒する存在になったんだと元気をもらったのかもしれません」
「オシャレなものが好きな人、オシャレなものが苦手な人、両方が楽しめるはず」(山中)
――本作は、どういった人に刺さる映画だと感じていますか?
山中「とてもクールに作られている映画だと思うので、オシャレな人は好きだと思いますし、それでいてキッチュさもあるので、オシャレなものが苦手な人でも、むしろ楽しめると思います」
大森「ハリウッドザコシショウさんやトム・ブラウンさんのようなお笑いが好きだという人は、好きになる気がしますね。破壊的なネタが好きな人は、絶対にハマる映画ではないでしょうか」
山中「たしかに!ハリウッドザコシショウさんやトム・ブラウンさんのネタも、『最後まで付き合うぞ!』という気持ちになりますもんね」
大森「本作は、キャラクター含め、全体的に誇張しすぎている点がいいんですよね。テンポがよくて、落とすところは落とすということをリズミカルに繰り返していく感じは、漫才や落語的でもあって。さらに『トレインスポッティング』など1990年代のイギリス映画のような懐かしい雰囲気もある」
山中「アンジェイ・ズラウスキー監督の『ポゼッション』や、ジュリア・デュクルノー監督の『TITANE/チタン』など、フェミニズムや身体性を表現した作品が刺さる人には当然刺さると思いますし、エンタメとしての完成度が抜群に高いので、幅広い層の人に観ていただける、熱量ある映画だと感じています」
取材・文/成田おり枝