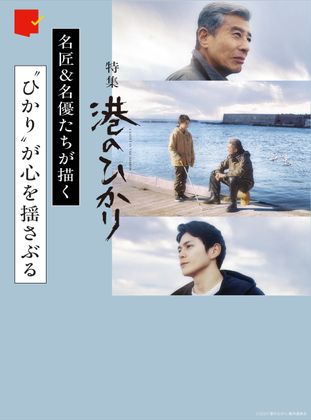大森時生と山中瑶子が語り合う、“打ちのめされた”映像体験。『サブスタンス』から得た刺激
「勇気を持つことによって、すごい作品が生まれることがある」(大森)
――エリザベスの着ている黄色いコートも印象深く、住んでいる部屋も彼女の精神状態を表現するなど、衣装や美術も見応えがあります。
大森「僕はフェイクドキュメンタリーを作ることが多いので、俳優さんが日ごろから着ている洋服を衣装として使わせてもらったりと、なるべくリアルを追求するようにしています。一方『サブスタンス』は、衣装や小道具自体がとても雄弁でスタイリッシュ。だからこそホラーでありつつ、軽妙さを感じるものになっている点もとてもおもしろかったです」
山中「わたしも自分が映画を作る時には、衣装や小道具において必要以上に過剰なものはできるだけ避けたいなと思っています。『サブスタンス』は、画面に映るあらゆるものが過剰ですよね。それが成功しているところが、本当にすごいなと思って。またリズムの刻み方も印象的です。例えば数字の書いてある注射器の殻をゴミ箱に捨てるというカットをカレンダー的に差し込んだり、ロッカーを同じ角度から撮影したカットを何度も入れていたり。それが映画のテンポやリズムを生み出すために必要な素材となり、ドーパミンを出させるような装置にもなっている気がしました。わたしは『いかにファッション的、コマーシャル的な撮り方に頼らずに表現できるか』ということを是として演出してきていたのですが、作品によっては必要なリズムの刻み方があるんだ、こういう表現方法がより適切な場合もあるのだと感銘を受けました」
大森「とにかく監督の雄弁なリズムを感じる映画でもありますね。そう考えると、ラストを含め、ジャンプカットの連発や“とりきり”(編集部注:画面いっぱいにテロップなどを映し出す用語)で文字を入れていくなど、監督の『これがいいのだ』という力強い意志を感じるシークエンスが多かったです。僕はプロデューサーとして、観客が観て冷めそうなポイントがないかをつぶさに検証してしまうタイプですが、本作を観て、多少冷める人がいようと表現を貫く勇気を持つことも大事だなと。そうすることでしか生まれない、すべてを突破するような迫力を持った作品になる可能性があるんだと実感しました」