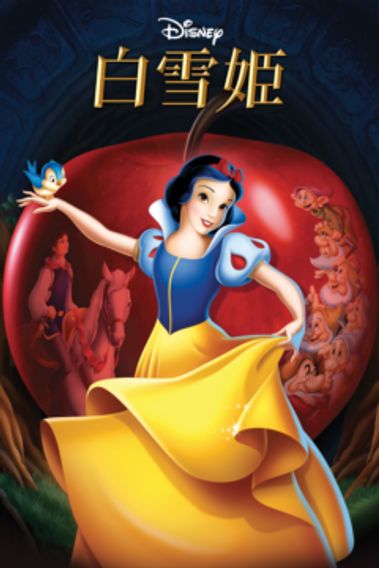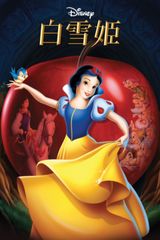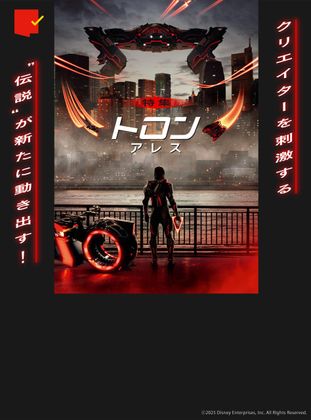『白雪姫』音楽演出が語る、吉柳咲良や河野純喜のレコーディング秘話&ディズニー・クラシックの偉大さ
ディズニーの歴史を振り返った時、様々な名作のタイトルが思い浮かぶが、なかでも“原点”として愛されているのが、1937年の『白雪姫』。世界初のカラー長編アニメーション作品として製作され、後の多くの作品やディズニープリンセスに影響を与えた同作が、時を超えてミュージカル実写版『白雪姫』(公開中)として生まれ変わった。そのプレミアム吹替版でレコーディング・ディレクターを務めたのが、島津綾乃。これまでも歌手aYanoとして『モアナと伝説の海2』(24)や、“超実写版”『ライオン・キング』(19)と実写版『アラジン』(19)といったディズニー作品に参加し、多くの吹替版に携わってきた彼女が、新たな『白雪姫』にどんな想いで向き合ったのか。吹替を担当した吉柳咲良、河野純喜をはじめとする多彩なキャスト陣とのやりとり、今回の『白雪姫』のために作られた新曲へのアプローチ、そしてディズニー作品における音楽の魅力などを語ってもらった。
「オリジナルの世界観を踏襲しつつ、新しい風を吹き込ませる。言葉のチョイスに苦心しました」
「私はオタクレベルのディズニーファン。子どものころから特に『白雪姫』が大好きで、それこそ自宅のお風呂場の浴槽を井戸に見立てて、“ハハハハハー”(「私の願い / ワン・ソング」の一節)と歌ったりしていました。家族から呆れられてましたけど(笑)。白雪姫が黒髪のプリンセスという点も、日本人からすると親近感をおぼえた理由ではないでしょうか」。
こう語るように、島津にとって『白雪姫』は人生のなかで重要な作品であった。その新作に関われたことに心から喜びを感じたそうだが、そもそも吹替版のレコーディング・ディレクターとはどんな仕事なのか。一般的にはキャストの吹替を“演出”するというイメージだが、その前段階、およびキャスティングから関わるなど多岐にわたるという。「本国から送られてきた譜面と映像を照らし合わせつつ、日本語の訳詞が上がってきたら、譜面に合っているかをチェックします。この音程にこの言葉はうまく乗るのか、作品の世界観に沿っているのか、などを確認するわけで、こうした歌詞の制作が最初の大きな仕事です。続いてオーディションの立ち会いです。その時点で仮決定している日本語の歌詞で歌ってもらい、セリフと歌の発声を確認します。高音から低音まで音域を確かめつつ、『白雪姫』のような有名な作品ではキャラクターに合った声なのかも重要なので、そのあたりをテストします」。
このような流れで吹替版キャストが決まったあとも、さらに歌詞のブラッシュアップなど作業は続く。「本国から送られてくる映像は随時修正されていますし、曲の中の細かい音が変更されていたりもします。そこに改めて日本語の歌詞を当てはめるわけで、最もキーとなるフレーズ(言葉)をどの位置に入れ込もうとか、最後の最後まで悩みながら歌詞を完成させていくのです。曲がどこまで人々の心に届くのか、歌詞が左右することもありますから。今回は現代版の映画として、誰もが知る『白雪姫』のイメージも大きく変わっています。オリジナルの世界観を踏襲しつつ、新しい風を吹き込ませる。そのバランスを考えながらの言葉のチョイスに苦心しましたね」。
公開前から様々なイベントで披露された「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」をはじめとし、完全な新曲は5曲 。「夢に見る 〜Waiting On A Wish〜」は、1937年のアニメ版で白雪姫が井戸の横で歌う「私の願い / ワン・ソング」を連想させたりもする。一方で「ハイ・ホー」「口笛ふいて働こう」など、有名曲も登場している。それぞれの歌詞の苦心について、島津は次のように振り返る。
「『夢に見る 〜Waiting On A Wish〜』は英語版のレイチェル(・ゼグラー)さんの歌い方がパワフルですが、白雪姫が強いイメージになりすぎてしまうのも避けたいので、歌詞で調整する必要がありました。今回の『夢に見る 〜Waiting On A Wish〜』のシーンには井戸が出てくるので、たしかに『私の願い』とシンクロします。ただし、曲自体はまったく別物。それでも私としては、アニメ版のファンに記憶を甦らせてもらいたくて、最初に上がってきた訳詞に入っていなかった『願いの井戸』というワードを入れました。そんな感じで『夢に見る 〜Waiting On A Wish〜』は皆さんと7回か8回くらい添削しながら仕上げていきましたね。その反面、『ハイ・ホー』などは、できるだけ当時の歌詞も受け継ぐようにしました」。