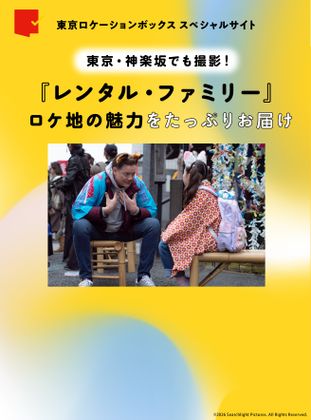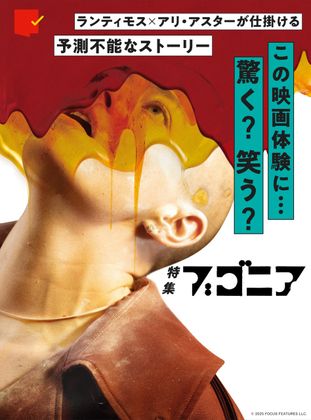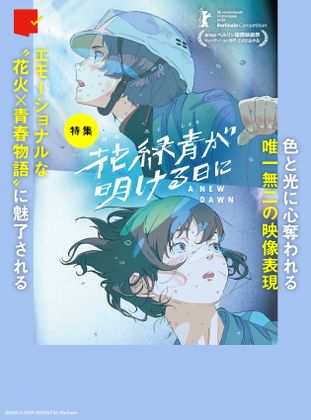これは嘘?真実?押井守も驚愕する異色ドキュメンタリー『人間蒸発』【押井守連載「裏切り映画の愉しみ方」第4回前編】
「私は破綻した映画が大好き。なぜなら、映画を考える契機になるから」
――なんか、よくわからない映画という感じでしたが。
「破綻しているから当然です。でも、私に言わせれば、だからこそめちゃくちゃおもしろい。今村昌平、『オレはそもそもドキュメンタリーの監督じゃねえし』って感じで開き直ったんだよ、きっと。でも、脚本がないわけだからいつまで経っても終わりが見えてこない。で、なにをしたかと言えばセットをバラしておしまいにした。それでも終わらなくて、最後は当時の今村の助監(督)だった浦山桐郎がカチンコを鳴らして『終わりだよー』って、やけくそ気味に終わらせている。映画としては見事なくらい破綻している。でも、私は破綻した映画が大好き。なぜなら、映画を考える契機になるから」
――ということは押井さんはこの作品でいろいろ考えたわけですね?
「そうです。今村昌平の言葉を借りると『なぜ映画は終わらなきゃいけないんだ。実人生は終わらないのに』ということ。あの姉妹だってケンカしながらも生きて行く、それもぬけぬけと生きて行くんです。でも、映画はそれをすべて捉えることは出来ず終わらなきゃいけない。それはなにを意味しているかと言えば、“映画の敗北”なの。彼女たちの実人生に映画のほうが負けちゃっているんです。たとえ映画を撮ったとしても、彼女たちを1mmも変えることが出来なかったんだから。
劇映画でそれが出来るのは、変わったふりをさせられるから。わけのわかんない感動とか共感とかを加えて、劇映画の力で変えるしかないんです。私がやっているのはそっち。人間だろうが社会だろうが、観終わったあと数時間でいいから価値観に衝撃を与えてやりたい。それが映画、劇映画の仕事だと思っていますから」
――ドキュメンタリーの場合はもっと社会性がある?
「ドキュメンタリーの監督たちはそう思っているんじゃない?彼らはエンタテインメントというより社会運動で撮っている側面が強い。もちろん、劇映画にも社会的側面はあるけど、やはりエンタテインメントなんですよ。ちなみに私は自分のことをエンタテイナーだと思っていますから」
――押井さん、いつもそう言いますけどね…。
「そういうと笑う人が多いんだけど、アクションに手を抜いたことは一度もないっていつも言ってるじゃないの!『なんで能書き垂れるんだ。アクションだけやってればいいのに』とはよく言われますけどね(笑)。『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』(95)の海外の評で言われていたのが『哲学を語りながら女性がマシンガンをぶっ放す映画』。それは正しいんです。私は『哲学』も『女性』も『マシンガン』も必要。マシンガンだけじゃエンタテインメントにはならない。ジョージ・ミラーだってアクションをただやりたいだけじゃない。彼の映画にはちゃんと哲学が見えてくるでしょ。だからこそ彼は並外れた監督の一人なんですよ』
――そうですね。
「ところで、麻紀さんは『人間蒸発』、初めて観たの?」
――はい。あの…姉妹もほかの女性もみんな似ていて区別がつかず、よくわからなかったうえに、音声が聞き取れなくて。字幕がほしかったし、そもそもピンとこなかったというか…。
「自宅で古い日本映画を観る場合はヘッドホンはマストです。昔から日本の役者はボソボソ喋っていたんです。増村保造はそれがイヤでセリフは明瞭にはっきり発音させていた。近代主義者だったからですよ。それでどうなるかというと、いかにもの演技になる。でも、それが彼の映画の魅力にもなったんだよね。そういう破格な監督もいたけれど、日本の監督は伝統的にリアリズムが好き。そうなると現場録音になってしまい、なにを言っているか聴き取れなくなる。が、日本映画の場合はそれでヨシとしてしまう。それが彼らのいうリアリズムだから。私はそう思わないので、最初の実写映画『紅い眼鏡/The Red Spectacles』(87)の時からすべてアフレコです。聴こえないとイラつくから。
女性が同じように見えたのは、今村昌平がそう見ているからです。彼にとってはみんな同じ人間。わからないから差別化させるなんてことはやりません。でも、今村昌平のような監督はもういなくなったんですよ。彼の人間の見方は本当に独特だったから…」
――押井さん、その話はまた後編でお願いします!
取材・文/渡辺麻紀