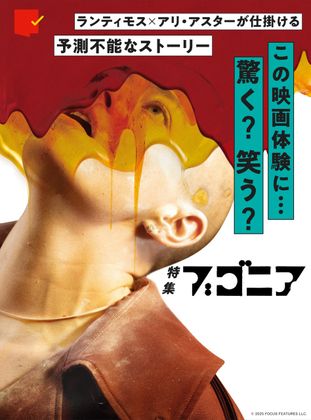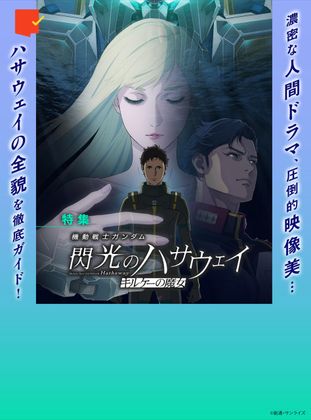軽量化という換骨奪胎のエンターテインメント『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』【小説家・榎本憲男の炉前散語】
ハリウッド的な二元論
守るというからには攻めてくる側がいることになります。それがデーモンであり、デーモンを操るラスボスはグウィマと呼ばれています。正しき者と悪しき者、光と影、このような二分法をハリウッドのジャンル映画はとても好みます。光り輝く世界にいる人間が正しき者であり、ダークサイドにいるものが悪しき者、デーモンであり、デーモンの首領たるグウィマです。
ただ、ひるがえって我が国を見てみると、このような<我々と他者>という二分法を用いたとしても、そこに明確な対立軸を設けるとは限らないのが、日本のアニメの特徴ではないでしょうか。『バケモノの子』(15、細田守監督)では、渋谷とバケモノの世界は隘路でつながっており、少年はバケモノの世界と人間界を行き来します。これは、バリアで区切られている本作の世界とは対称的です。
日本には御霊信仰という伝統があります。御霊は政治的に恨みを持って死んでいった霊という意味です。この霊がさまざまな厄災をもたらす。ところが、この禍々しいパワーそのものを敬い、時にはその力を我が物として利用しようとする心性が日本人にはあるのです。災いをもたらすデモーニッシュな霊とすがりたい偉大な霊が二重になっているのですね。そればかりか、それが入れ替わったりもする。その代表的なものが菅原道真の霊でしょう。この怨霊は数々の厄災をもたらしたと理解され、人々はこの荒ぶる霊を鎮め厄災を及ぼさないようにしようと太宰府天満宮にそれを祀りました。けれども、いつのまにか、これを敬う気持ちも育ち、いまでは、この神社は受験生にとっては学問の神を祀るポジティブなパワースポットになっているのです。
しかし、ハリウッドはこのような万華鏡のような世界の見方を嫌い、二元論を押し進めるほうを好みます(もちろん例外はありますよ)。世界をくっきり際立たせて、対立軸を明確にし、そこに葛藤の構造を創り出していくのです。『KPOPガールズ!』が取っているのはこちらの戦術です。
軽量化の戦略が生み出した効果
現在の物語では、内的葛藤は実存的な欲望が生み出すのが普通なのに、本作品では、まずは徹底的に構造を固め、そこに光と闇の対立をつくる。このような単純化は、物語をパワフルにするとともに、幅広い年齢層に受け入れやすくもする。「単純だなー」と笑う大人だって、「そういうものか、よし」と思ってみれば、子供と一緒に楽しく見ていられる。物語は明解だし、歌も踊りも楽しいし、アニメの動きも素晴らしく、スペクタクルには事欠かない。軽量化していくことによって、小説などでは味わえない映画の醍醐味が濃厚になってくる。
とはいえ、構造をここまで単純化するとキャラクターも単純化します。ヒロインが所属しているグループは3人組のハントリックス、これに対して、グウィマが送り込んだデーモンのサジャ・ボーイズは5人組。ところが、キャラクターにテーマらしきものが与えられているのは、ヒロインのルミと、サジャ・ボーイズではジヌのみ。ハントリックスでは、ダンス担当のミラが問題児だったこと、ラップ担当のゾーイが妹キャラであることくらいが述べられ、サジャ・ボーイズに至っては、ジヌ以外はほとんど記号です。なぜそこまで記号化するのか。そのことで生じるメリットとしては、時間を短縮できるということが挙げられます。各キャラクターのテーマをそれぞれ解決していくと、人数分だけ時間がかかるし、段取りくさくもなる。テーマを抱えたキャラは二人に絞ることで、飽きさせることなく、全編を実質1時間30分を切る速さで駆け抜ける、これが軽量化の戦略です。
もっとも、ハントリックスとサジャ・ボーイズから一人ずつ、ルミとジヌだけは、この光と闇の境界線を曖昧にするキャラクターとして設定されています。世界がくっきり光と闇に別れているぶん、光の世界にいるのに身体が闇に染まったルミと、闇の世界に転落してしまったがそれを悔いる心を持つジヌ、このふたつのキャラクターだけは際立つ。そして、当然二人は似たもの同士の引力によって惹かれ合うのです。
しかし、この二人とて記号的であることは否めません。なぜ二人がそのような葛藤を抱えることになったのかという経緯は、大して語られていない。そこはまあ観客の方々が適当に想像してください、そんなことより、歌や踊りの方が映画的だし楽しいでしょう、という作りになっているのです。
なので作品の印象は全体的にはとても軽い。その軽さが魅力につながっている。本作の大ヒットの裏にあるのは、実存的な重みよりも、ほとんど骨格になるまで贅肉をそぎ落とした軽さを求める観客がかなりの数いて、それこそが映画の魅力だと感じている証左なのかもしれません。ただ、この仮説が正しくても、そこから一気に、現代の観客は重苦しい実存的物語に疲れている、とか、SNS時代の高速消費スタイルが観客に軽さを求めさせている、と結論づけるのはまだちょっと早いように思います。
文/榎本 憲男
1959年生まれ、和歌山県出身。小説家、映画監督、脚本家、元銀座テアトル西友・テアトル新宿支配人。2011年に小説家、映画監督としてデビュー。近著には、「アガラ」(朝日新聞出版)、「サイケデリック・マウンテン」(早川書房)、「エアー3.0」(小学館)などがある。「エアー2.0」では、第18回大藪春彦賞の候補に選ばれた。映画『カメラを止めるな!』(17)では、シナリオ指導として作品に携わっている。

小説家・榎本憲男の炉前散語