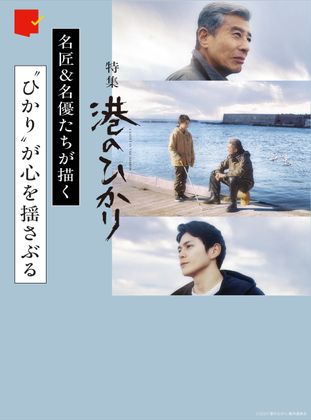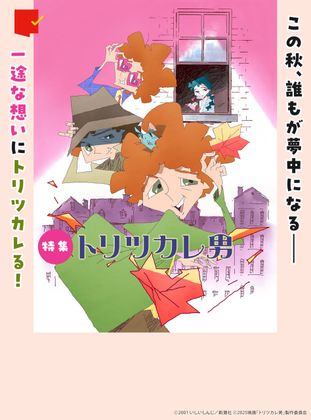「オカルティックでミステリアス」「観たあとも不可解。だけど興奮する」…映画ファンの感想からひも解く『火喰鳥を、喰う』のゾクゾクするおもしろさと、その先の驚愕
「ホラーだと思っていたらミステリー、そしてSF」…物語がどこへ向かって進むのか最後の最後までわからない
冒頭から墓石に記された貞市の名前が削られている不穏な光景から始まる本作。日記が雄司たちのもとに届けられたことを機に、玄田が「久喜貞市は生きている」と呟き、夕里子の弟、亮(豊田裕大)も日記に「ヒクイドリヲ クウ ビミナリ」と書き込むなど正気を失う者が続出。貞市と同じ部隊に属し、復員した元兵士の自宅で火事が起こり、貞市の弟で雄司の祖父でもある保(吉澤健)が失踪するなど次々と不可解な出来事が巻き起こる。
「ホラーだと思っていたらミステリー、SFになり…」(20代・男性)
「オカルティックでミステリアス。“生”と“生に対する諦め”が出ていて非常によかった」(20代・女性)
上記のコメントが示すように、貞市と日記をめぐるミステリーが繰り広げられるなか、雄司たちをじわじわと追い詰めていくホラー要素も絡んでくる。さらに、わざと焦点をぼやかさしているのか、人を煙に巻いた言動をする北斗の存在が状況をややこしくし、物語がどこへ向かって進んでいくのか最後の最後までまったくわからない。そもそも“ヒクイドリ”とはなにを指しているのか?信じていた目の前の現実まで歪めてしまう展開の連続に、登場人物だけでなく観ている者まで振り回されてしまうのだ。
「小説家が物語をどう構築していくのかを聞けた貴重な経験」…原作者の言葉で深まる作品への理解
前述した通り、今回の試写会には原作者の原浩が登壇。そのトークイベントでは、実は横溝正史ミステリー&ホラー大賞を受賞した時点での雄司と夕里子は夫婦ではなく(雄司にとっての兄嫁)、書籍刊行にあたって関係性を再構築したという初出の情報も飛びだした。また、本作を10歳の娘と共に完成披露試写会で鑑賞し、「おもしろかったよ」と褒められたこと、“火喰い鳥”が“生きたいという執念”や“作品の法則を司る象徴”であることを明かしたほか、映画では北斗役の宮舘が印象に残っており、「胡散臭さが想像の2つ3つ上をいっていた」、「立ち居振る舞いが非常に優雅」と語った。
こうした原の言葉に対し、原作小説を読んでいる人からは「より内容が理解できた。原作にないシーンがあり、その違いがよかった」(20代・女性)、「北斗に対する原先生の思い入れ、役割を知ることができてよかった。宮舘さんのお話を聞けたこともよかった」(40代・女性)といったコメントが。物語への理解がより深まり、映画化にあたってのアレンジにもスッと腑に落ちたようだ。
また、原作未読の人からも「叙述的な見せ方をしているということで、どのようにテキストで表現されているのか気になった」(10代・男性)、「宇宙論からこの小説が生まれたと聞き、小説家が物語をどう構築していくのかを聞けたことが貴重な経験だった」(20代・男性)、「最初は雄司と兄夫婦で構成されていたものを、登場人物が少ないほうが読みやすいだろうという理由で、雄司と兄を一人の人物にしたという話が興味深かった」(40代・男性)といった感想が寄せられるなど、原作を読んでみたくなるきっかけになったよう。
「ミステリーの範疇を超えた作品」「人間の本性と本能」…タイトル『火喰鳥を、喰う』が意味することに様々な考察が
改めて、『火喰鳥を、喰う』というタイトルについて考えてみると、これほど不気味で知的好奇心を刺激される言葉もないだろう。今回の試写会でも、タイトルの意味について様々な考察がされると共に、その奥深さをもっと大勢に知ってほしいと感じている様子が伺える。
「観たあとも不可解。だけど興奮する作品」(10代・男性)
「まったく話の流れが予測できなかった」(20代・男性)
「ミステリーの範疇を超えた作品として勧めたい」(30代・男性)
「執着。この作品全体で一人一人がなにかしらの執着を持っていた」(20代・男性)
「(『火喰鳥を、喰う』とは)雄司と夕里子、北斗を結ぶものではないだろうか」(20代・男性)
「人間の本性と本能」(30代・男性)
怪異をめぐる雄司と夕里子、北斗の運命はどのように絡み合い、いかなる結末を迎えるのか?不気味なのにどんどんスクリーンに引き込まれていく『火喰鳥を、喰う』に、没入感のある劇場空間で浸ってほしい。
文/平尾嘉浩