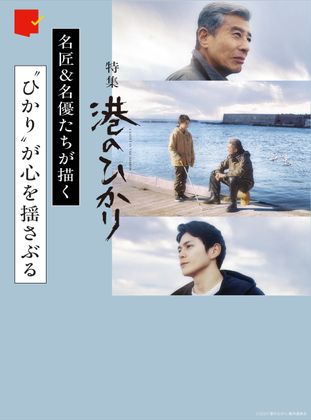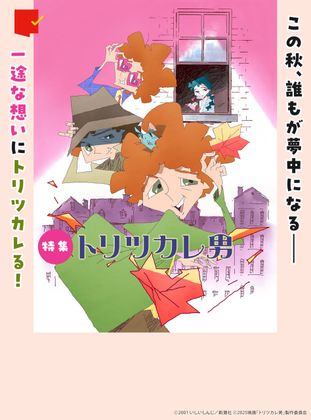コーダとして育ったイラストレーター、門秀彦が語る『君の声を聴かせて』の魅力「手話の”かっこよさ”と”豊かさ”がリアルに描かれている」
「手話を『かっこいい、楽しい』と思ってもらえる機会を増やせば、社会は変わると思いました」
アーティストとしての道は、決して真っ直ぐなものではなかった。中学校のころから絵画コンクールで賞を取り、才能を周囲に認められていた門は、美術高校への進学を希望していた。教師から推薦の話もあったが、色弱であることが判明し、推薦は取り消されてしまった。
その後は思うように進路が定まらず、門曰く「流浪の日々」。横浜で就職するもほどなく九州に戻り、建設作業員やアパレルショップ店員などの仕事を渡り歩いた。それでも絵を描くことだけはやめなかった。そして20歳の時、人生を変える出来事が訪れる。長崎市の百貨店から依頼を受け、壁画を制作することになったのだ。
「そのとき、父が『息子の絵の前でろう者の仲間と待ち合わせたい』と言ったんです。それを聞いて、ろう者にとって自分たちの言葉が描かれている場所があったらうれしいんじゃないかなと思い、壁画の中に『ありがとう』や『こんにちは』の手話を入れてみました。すると知人が『かっこいい。ヒップホップっぽい』って言ったんです。手話だと知らないで。手話って『かわいそうな人が使うもの』と見られることもある。でもアートを入り口にすると、『かっこいい』『楽しい』って思ってもらえる。そういう出会いを増やせば、社会はだいぶ変わるんじゃないかと。そのとき思いました」。
「『自分だったら』と想像しながら観てもらいたい映画です」
この気づきが、アーティスト・門の出発点となった。以降、ポップに描いた手話を、ファッションや音楽と結びつけていく。NHK『みんなの手話』でアニメーション作品の企画と作画を担当したり、宮本亜門、佐野元春など多彩なアーティストのアートワークやフジテレビ『めざましテレビ』の情報コーナー「モアセブン」のアニメーションを制作し、多くの視聴者に作品を届けた。
なかでも大きな注目を集めたのが、スターバックスとのプロジェクトだ。国内初となるサインニングストアの店内アートとデジタルサイネージを担当。ろう者たちが働く店内には、フラペチーノやマグカップにまつわる言葉や『THANKS』『GREETING』といったコミュニケーションの言葉が手話で描かれている。
「来店したお客さんがアートを見て、『あ、これ手話なんだ』と自然に知ることができる。コーヒーを飲みに来たついでに手話に触れるきっかけになればと思いました」。
門の活動は、個展や商業的なアートにとどまらない。全国で行うワークショップも、活動の大きな柱だ。子どもたちや地域の人々と一緒に絵を描く活動は、「手話」や「ろう文化」と出会う入口となり、世代や立場を越えたコミュニケーションの場を生み出している。
特に大きな取り組みの一つが、今年11月に東京で開催されるデフリンピックに向けた活動だ。門は行政や地域と協力し、学校や商店街でのアート制作を通じて、大会の周知と理解促進に取り組んできた。
「みんなで一緒に絵を描く、みたいな感覚ですね。手の絵やデフリンピックに関連する絵を描くんです。誰でも参加自由で、ろう者も来るんです。『デフリンピックってなんだろう』ぐらいの、ちょっと入り口に立った聴者の人たちもいっぱい来ます」。
アートを媒介に聴者とろう者が楽しく出逢うコミュニケーションの機会をつくる。紆余曲折を経ながら、幼い日に抱いた夢を形にしてきた門。手掛けるブランド「SMILE TALKING HANDS」には、次のような想いが込められている。
「コミュニケーションは、すべての人と人の間にある。出逢い方をできるだけ楽しく。伝えたい思いは、すべての大切な人の数だけある。手をできるだけ伸ばして」。
映画『君の声を聴かせて』で一番心を動かされたセリフを尋ねると、こう答えた。
「『これからはヨルムとして生きてほしい。ガウルの妹や私たちの娘としてでなく』という、ヨルムの母親のセリフです。僕の父も『好きなことをやれ』って、よく言っていたんです。子どもの時は気づかなかったけど、大人になってから思うと、もしかしたら深い意味があったのかもしれない。自分たちが好きに生きたくても生きられなかったからこそ、『お前はそうならないように、自由に生きろ』という願いが込められていたんじゃないかと。この映画は恋愛映画でもあるけれど、同時に家族の物語でもあると思います。ろう者は特別な存在じゃなく、実はすぐそばにいる。自分と全然違う世界の話じゃなくて、『自分だったら』と想像しながら観てもらえたらいいなと思います」。
取材・文/桑畑優香