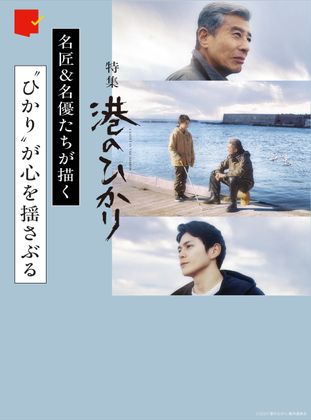12年ぶり来日中のザ・スマッシング・パンプキンズの名曲をスネイル・メイルがカバー!『テレビの中に入りたい』サントラが公開
第74回ベルリン国際映画祭パノラマ部門正式出品のA24製作映画『テレビの中に入りたい』が9月26日(金)より公開される。このたび、本作のサウンドトラック全16曲がスペシャル映像と共に解禁。さらに各界著名人たちからの感想コメントも到着した。
第74回ベルリン国際映画祭をはじめ、数々の映画祭で上映されると「唯一無二の傑作」、「変幻自在の不穏さ」「型破りな映画」「この作品を表すのに“リンチ的”という言葉を使いたい」と絶賛され、全米公開では熱狂する若者たちが続出。公開から1周年記念で新たなグッズが発売されるなど、続々と“中毒者”を生み出し続けている『テレビの中に入りたい』は、1990年代のアメリカ郊外を舞台に、自分のアイデンティティにもがく若者たちの“自分探し”について描く物語だ。郊外での日々をただやり過ごしているティーンエージャーのオーウェンにとって、謎めいた深夜のテレビ番組「ピンク・オペーク」は生きづらい現実世界を忘れさせてくれる唯一の居場所だった。同じくこの番組に夢中になっていたマディとともに、2人は次第に番組の登場人物と自分たちを重ねるようになっていく。閉塞した日常をやり過ごしながら、自分のアイデンティティにもがく若者たちの、せつなく幻想的な青春メランコリック・スリラーが魅惑の映像世界と共に展開する。
このたび、本作の全16曲のサントラを一挙公開するスペシャル映像が解禁となった。オルタナティブロック界のレジェンド、ザ・スマッシング・パンプキンズの名曲「Tonight, Tonight」を本作にも出演するスネイル・メイル(リンジー・ジョーダン)がカヴァーした楽曲も。大型フェスのような充実のラインナップとなっている。サウンドトラックは、キャロライン・ポラチェック(Caroline Polachek)の頭から離れないエレクトロポップ曲「Starburned and Unkissed」から、フローリスト(Florist)の哀愁を帯びたフォークソング「Riding Around in the Dark」まで、現代のインディーズ音楽業界の幅広いアーティストを網羅。インディーからオルタナティブシーンの実力派までが集結した映画ファンのみならず音楽ファンも必聴の豪華サウンドトラックとなった。スネイル・メイルによる「Tonight, Tonight」のカバーと、映画全編でオーウェンのテーマ曲として繰り返し使われるyeule(ユール)による「Anthems For A Seventeen Year Old Girl」のカバーの2曲は、1990年代と2000年代初頭の楽曲となっている。
さらに、本作の音楽を手がけたのは、現代アメリカきってのシンガーソングライター、アレックス・G。本作で2度目のタッグとなるシェーンブルン監督は、はじめにアレックス・Gにミックステープを作ったといい、「音楽編集ソフトウェアをダウンロードして、ザ・スマッシング・パンプキンズのあのアルバムの曲から音とストリングセクション、様々な楽器の音を切り離しました。アレックスに、あのアルバムが鮮やかにとらえている1990年代の独特な雰囲気を心に留めてサントラを作ってもらいたかったからです」と語っている。
また、一足早く本作を鑑賞した各界の著名人たちから、続々と“感想コメント”が到着。音楽界からは、尾崎世界観が「あのころにだけ見えていたものを、いまこうして観られるのが嬉しい」、川上洋平が「自己認識が曖昧だったあの時代を思いだし、胸が締め付けられた」とコメントしている。また芸能界から、お笑いトリオ、パンサーの菅良太郎が「何度も観たいが、それをすると今度は僕自身がこの映画に囚われてしまいそうで恐ろしい」、フリーアナウンサーで俳優の宇垣美里が「たすけて。たすかりたい。本当の自分ってなんなの」、IMALUが「この映画は全然可愛くない!心をえぐられます!」、豊田エリーが「突き放すことも、寄り添うこともせず、ただそこにクールに佇む映画が、心の中の10代にはいつも必要なのだと思う」とコメントを寄せた。
さらに映画ライターの斉藤博昭は「誰もが通過した“あのころ”の孤独感、行き場のない閉塞感が、リアルかつせつなく胸を締めつけてくる」、小説家の大前粟生は「どこかに逃げたくてたまらなかった、でも逃げることができなかった"あのころ"の映画」、ゲームクリエイターの小島秀夫は「何本も観たなかで、唯一、頭に焼き付いて離れなかったのが『テレビの中に入りたい』」と、それぞれ印象的なコメントを寄せている。
孤独なティーンエージャーがクラスメイトから深夜の謎めいたテレビ番組のことを聞き、番組の中の世界を現実よりリアルに感じ始める本作。1990年代半ば、主人公が成長していく心揺さぶる不可思議な物語の行方をぜひ劇場で見届けてほしい。
文/鈴木レイヤ