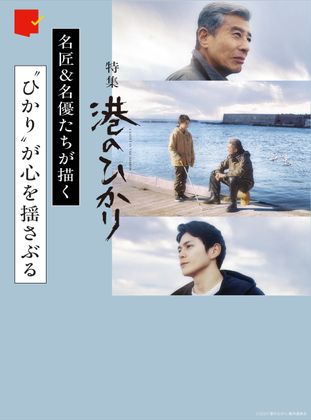『ワン・バトル・アフター・アナザー』初のビスタビジョン上映会後のQ&Aを現地レポート!ディカプリオ、デル・トロらが撮影秘話を語った夜
「私が自由に探求し、安心できる場を設けてくださった」(チェイス・インフィニティ)
――チェイス(・インフィニティ)さん、この映画に出演するまで、長いオーディションの過程があったとうかがっています。ご自身でも、以前まではアンダーソン監督の映画をあまり多くはご覧になっていなかったと率直に認めていらっしゃいますが、この役を勝ち取った時、あるいはどの時点で、監督の作品をご覧になったのでしょうか?
インフィニティ「撮影が終わってから、熱狂的な鑑賞が始まったような気がします。撮影の合間に、『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』を観て、彼がどのような監督で、彼の世界や仕事の範囲がどのようなものかを、頭のなかで理解している自分に気づいたのです。そして、私は『よし、この撮影を終えるために、自分の気持ちを落ち着かせよう。そして、ウィラや物語のため、そしてすべての人たちのために、必ずや満足のいく結果を出そう』と思ったんです」
――あなたのシーン、特にショーンとのシーンを観ると、ウィラのなかに恐怖と反抗心が同時に存在しているのが伝わってきます。そんな相反する感情を同時に表現していたのが本当に驚異的でした。この役柄と向き合うなかで、どのような感情を抱いていたのでしょうか?
インフィニティ「文字通り、完全に没入したかったんです。特にショーンとのシーンでは、彼を燃え上がらせるような演技をしたいと思っていました。あのシーンは、この映画で撮影したなかでもお気に入りのシーンの一つです。でも、最初は確かに非常に緊張していました。ところがポール、レオ、ショーン、ベニチオ、レジーナ(・キング)といった皆さんが大変親切にサポートしてくださり、私が自由に探求し、安心できる場を設けてくださったのです」
「たとえ暗い題材でも、その不条理さに可笑しさを覚えるもの」(ポール・トーマス・アンダーソン監督)
――アンダーソン監督、この映画では、ユーモアのすべてが完璧に機能していますが、この強烈なストーリーのなかで、うまく機能するユーモアを挿入するのはとても難しい塩梅だったのではないでしょうか。
アンダーソン監督「私が映画を観る際に、ある前提条件があります。それは、その映画に笑える場面があるかどうかです。笑える場面がない映画は観たくない。以前は、まじめな映画を観たいと思っていたのですが、いまは、笑える映画を観なければ気が済まないのです。私たち全員が、おもしろいと思うものについて、同じ感覚を持っていたと思います。それは、大抵、人間の不条理さに立ち返るものでした。しかしジョークの難しいところは、キャラクターにとっての理由があったうえで生まれる必要があるところです。ただキャラクターがジョークを言うのでは大抵うまくいきません。状況や環境から生まれるユーモアが最も効果的です。私たち全員、ある種のユーモアのセンスを共有していると思います。たとえ暗い題材でも、その不条理さに可笑しさを覚えるものです」
――カースタントについてお聞きしたいと思います。すばらしいカーチェイスのシーンがたくさんあります。ベニチオのすばらしいスタントもありましたし、もちろん、最後のジェットコースターライドのような道もありました。それでは、ベニチオさんから始めましょう。自動車のスタントは、どうでしたか?
デル・トロ「とても楽しかった(笑)」
ディカプリオ「上級ドライバーです(笑)」
アンダーソン「彼は優秀で、どんなアメリカ車でも、正確な場所に駐車することができます」
――終盤のカースタントはとても魅力的なショットでした。どのようにして撮影されたのでしょうか。
アンダーソン監督「それを尋ねられるだろうと思っていました。映画の結末を決めずに撮影に臨んでいたけれど、いよいよ終盤に差し掛かり、どういうわけか、ずさんな主人公が事態を救うか、少なくとも娘を取り戻さなければならないだろうことはわかっていました。結末については様々なバージョンを考えていましたが、どれも満足のいくものではありませんでした。何億ものロケ地の中から、その答えを見つけようと移動を続けました。結局、アリゾナ州境から20マイル離れた場所のボレゴ・スプリングス にたどり着きました。そこで、ある道路を高速で走りながら撮影を行いました。その時気づきました。これは非常に恐ろしい状況だと。時折、後続車が見えなくなり、地平線の向こうになにがあるかもまったくわからない。時速75マイル、80マイルで走っている時、ただ目を閉じて、そこになにかがあることを祈るしかないのです。そこで私は携帯電話を取り出し、ダッシュボードに置きました。そしてなにが起こるかを見守ったのです。戻ってきた頃には、最大の急降下区間、いわゆる「テキサス・ディップ」に差し掛かっていました。おそらく映画の神様が味方してくれたのでしょう。奇跡が起こり、この結末が自然と浮かび上がりました。最高なのは、私たちの真のヒーローが状況を掌握し、彼女を奮い立たせ、行動する姿を見られたことでした。すべてが自然な流れで生まれたのです」
「このメンバー全員を信頼し、尊敬している」(ポール・トーマス・アンダーソン監督)
――レオさん、結局のところ、アンダーソン監督との仕事は想像と比べていかがでしたか?
ディカプリオ「興味深いことに、自分自身で言葉にすることがますます難しくなってきています。ただただ自意識が強くなり、奇妙な気分になるから。それに、長年尊敬してきた人物について、その人のすぐ隣で話すのもまた奇妙なことです。しかし実際のところ、そこにはある種の自然さがあるんです。ほかにどう表現すればいいのかわかりません。ベニチオが参加した時もそうでしたが、物事が自然と噛み合い、うまく機能するんです。そこに化学反応が生まれます。セット上で無理に努力して開花させる必要のある類のものではありません。ポールについては、こう言わせていただきます。彼は驚くほど嘘を見抜く鋭い能力を持っていて、それが本当にすばらしいのです。俳優として、私はそういう存在が必要です。特定の選択を抑制してくれる人が必要なんです。私は様々なアイデアを提案しましたが、彼は自分のやりたいことに対して、このうえない落ち着きとシンプルさ、そして確固たる信念を持っています。また、役柄の主導権を俳優に委ねることもいといません。ただし、俳優のアイデアが優れていると感じた場合に限ります。大抵は10回に1回程度ですが、彼は即座に方向転換し、まったく異なるアプローチを取ることもありました。この映画は、まったく違う作品になる可能性もありました」
アンダーソン監督「それは、お互いに信頼そして尊敬があったからです。私は、このメンバー全員を信頼し、尊敬しています。誰とも争うことはありませんでした。それは圧倒的な喜びだったんです」
9月26日に全米公開を迎え、アンダーソン監督史上最大の興収でスタートを切った『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、10月3日より日本でも絶賛公開中。
取材・文/平井伊都子