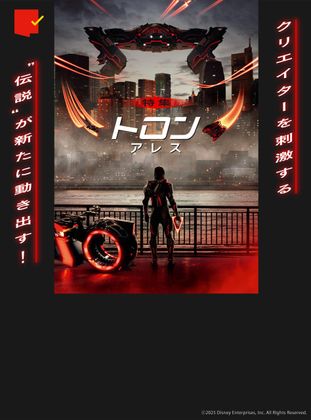イム・ヨンウンの主題歌が流れる『最後のピクニック』特別映像が解禁!綾戸智恵、角田光代らから絶賛のコメントも
<コメント>
●綾戸智恵(ジャズシンガー)
「ピクニックは楽しい!
この二人は今回どうだったんやろうか
親友と振り返った日々半分以上はつらかったなぁでも
この海だけは優しく迎えてくれたんだろう。
タイトルに最後の――とあるが、私にはそう思えない。
この二人も年齢を重ね本当に必要なものがなんなのか見えてきて、
最期は備えるのやなく、迎え入れあえるものと思うたんとちゃうかなぁ。
どう生きるかを画面から問われたように感じた!
砂の一粒ほどの私でも頑張ろうと思わせてくれる映画やな」
●松本明子(タレント)
「人生最後の日に、一緒にいたい人は誰ですか――?この言葉は深く心に響きました。そういえば私の母も他界する前、女学校時代の親友の話ばかりしていました。哀しみは半分に、喜びは何倍にも大きくしてくれる“友情”。私も瀬戸内海が見える街で生まれ育ちましたので、この映画の舞台、南海の美しい景色に、私の故郷の鮮やかな思い出がよみがえりました。私も残りの人生をどう生きるか、いかに自然体で自分らしく生きられるか、考えたくなる作品でした」
●角田光代(作家/劇場パンフレットより引用)
「映画のラストの、そのあとはどうなるのか。二人は自分たちの決意を貫くのか、それとも笑って手をつないで家に帰るのか、わからない。観た人それぞれに、ラストのあとに続く二人の姿があるのだろう。この映画が描くのは、たんに老いの問題ではなく、生きることの本質なのだ。だから、若い世代にも自分ごととして響いたからに違いない」
●太田博久(ジャングルポケット/芸人)
「誰の人生にも喜びや波乱はあるけれど、ともに受け入れ分かち合える存在の尊さに胸を打たれました。大切な人との時間こそ人生の宝だと教えてくれる映画でした」
●片岡信和(俳優、気象予報士)
「思い出に距離はないのかもしれない。昨日のことのように蘇る青春は胸が締めつけられるほど鮮やかだった。だからだろうか、浮かび上がるほど現実に重くのしかかる。それでも歩みを進める二人は美しかった。ピクニックの最後、振り向いた彼女たちにはなにが見えていたんだろう。まだまだ捨てたもんじゃない世界であってほしい。空気を読まずに言わせてもらうが、僕は家に帰るまでがピクニックだと信じている」
●おじゃす(タレント/TikTokクリエイター)
「まだまだ続くであろう人生の悩みや最期について考えさせられる作品でした。故郷での再会や、何十年経っても変わらぬ親友との友情が温かく、思い切って足を踏み出す勇気をくれる素敵な映画でした!」
●平井桃伽(モデル/俳優)
「なんだか心が温まったような、けど儚くて寂しいような、そんな複雑な気持ちになりました。それと同時に私も何歳になってもこんなに素敵な親友と居れる素敵な人になりたいと思いました。ぜひ私と同年代の皆さんにも観てもらいたい作品です!」
●木宮正史(東京大学、名誉教授/朝鮮半島地域研究)
「短期間に急速な発展を遂げた『圧縮近代』韓国の一断面を、同郷の幼なじみで姻戚になった二人の女性の追憶と再会、悲しくもありながら、人間へのリスペクトを忘れない生き様を通して描いた。ナ・ムニ、キム・ヨンオクの二人の名優の演技に注目したい」
●崔盛旭(映画研究者)
「変わりゆく時代のなかで、思い出といまをつなぐ変わることのない友情は、ついには人生をも越えて永遠へと向かう。喜びも悲しみも、苦痛さえも美しい一篇の詩のように輝きながら。二人の大女優の演技は、老いることを知らない」
●石津文子(映画評論家)
「かけがえのない時間を過ごした友とその記憶を手に、波乱の日々を生き抜いた二人の女性。最後に、大切なものを失わずに済んだ彼女たちは決して不幸ではない。それでも他の選択をできる社会であってほしい」
●ISO(ライター)
「人生の不条理さも、夢見る凡人の哀れさも、“家族の絆”の脆さも、老いと死の絶望も。この映画は現実をなに一つとして隠さない。むしろより過酷な未来を首元に突きつける。だがその大荷物をそっと分かち合う彼女たちの姿に、この世界を生きていくための光を見た気がした」
●児玉美月(映画批評家)
「『最後のピクニック』は、老年期の女性二人の友情をメインテーマとした稀有な映画だ。生まれ変わってもまた友だちになると宣言し、あなたは自分を見守ってくれる天使だと表現し、そんなふうに衒いなく相手への想いを伝えられる彼女たちの姿が、心底愛おしい」
●mikoザウルス(韓国映画沼の住人)
「ここで語られるのは、”未来”の私たちの物語、そして”いま”私たちが語らなくてはならない物語」
●ゆいちむ(映画好きOL)
「感情、揺さぶられまくりです。厳しい現実、問われる尊厳。人生も老いも、美しいことばかりじゃない。だからこそ、ピクニックの果てに見た友情の尊さに、胸が熱くなりました」
文/久保田 和馬