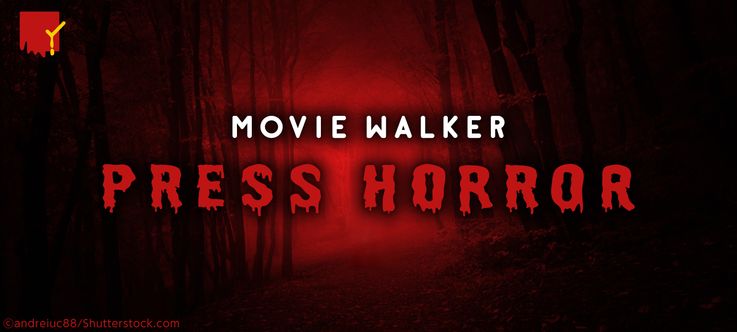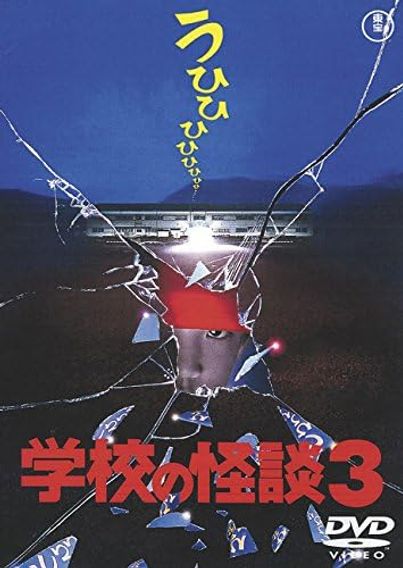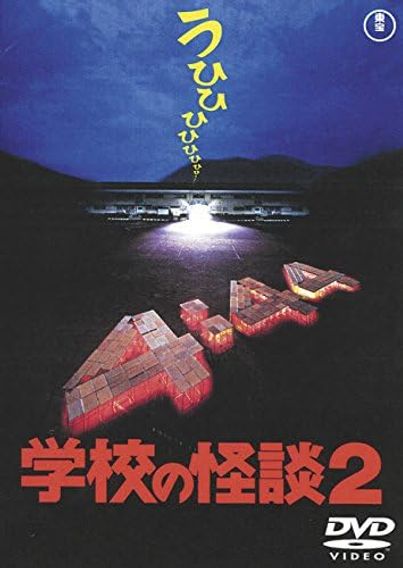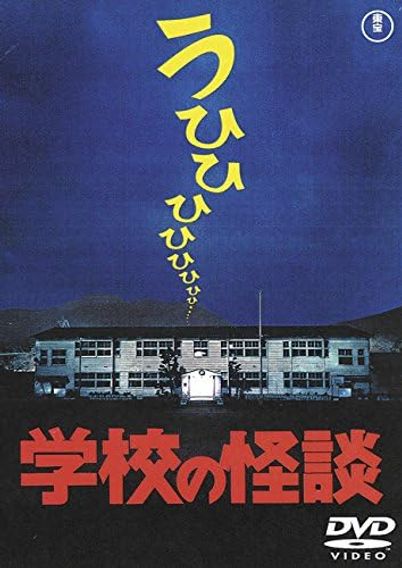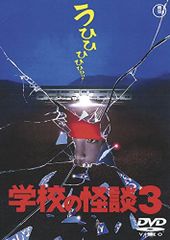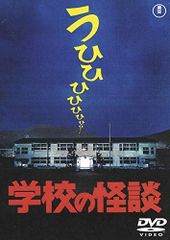『学校の怪談』から30年…上映会に平山秀幸監督、野村宏伸、奥寺佐渡子が集合!「同窓会をやってみたい」
「子どもたちにとって、いい夏休みになってくれれば」
ーー「学校の怪談」シリーズといえば、生き生きとした子どもたちの演技が魅力ですね。
野村「私は現場ではあまり子どもたちと接していなかったと思います。嫌ってるとかじゃないですよ(笑)。あえてです。子どもたちは慣れ合っちゃうと、そこで緊張が緩んだりするので、ある程度の距離を保つようにしていました。でも皆さん『おはようございます』とか『おつかれさまでした』とか、とても礼儀正しくて」
平山「子どもたちはあっち行ったりこっち行ったりしていましたから、僕らがやることは枠をきちっと作ってあげて、そのなかでなら走っても転んでも泣いてもいいようにすること。あとはずるいやり方ですが、テストの時からカメラを回して、彼女ら彼らの普通の状態を見れればいいなと。でもとにかく言うことを聞かないんです(笑)。どこかスタッフが学校の先生みたいになってしまって、子どもたちも、この人は言うことを聞いてくれる、この人は怖いと見透かしている。だから子どもたちとの争いのようでもありました」
ーーオーディションは700人規模。決められたポイントは演技力よりも自然さだったのでしょうか?
平山「いろいろな選び方があるんですけれど、『学校の怪談』でいえば『おはようございます』と入ってくる子はみんな面接で落ちていた気がします。個人的には子どもたちにとっていい夏休みになってくれればと思っていたので、将来すごい俳優になるかどうかとかは気にしていませんでした。参加してくれた子どもたちの思い出になればそれで充分だという気持ちでやっていました」
ーー奥寺さんの書かれた子どもたちのセリフも自然体で、時にシュールで感動的で。1作目の「貯金好き?」などの名ゼリフはどのように生まれたのでしょうか?
奥寺「あんまり考えてなかったと思います(笑)。1作目の脚本を書いたのが26歳か27歳の頃で、まだ自分も子どもというか、中身が小学生だったので。それにデビューしてすぐということもあって、くだらないセリフを書いちゃダメという意識もなく、あまり考えずに自由に書いていましたね」
ーーもしいま、リメイクや続編をやるとしたらどういう作品にしますか?
平山「難しいですね…。最初に話をもらった時に、ホラーがまったくわからなかったので参考試写として『トリュフォーの思春期』を観たんです。もしそういうことがあるのならば、ベースはジュブナイル映画のかたちにして、その上にアクションやホラーめいたものを重ねていく点は変わらないんじゃないかと思います」
奥寺「私はやっぱり木造校舎が見たいなというのがあるんですけど、いま残っているのかなあ…」
野村「私は現代ではなく、昭和とか昔の時代。携帯のない時代のほうが話が膨らませられるのではないかと思います。でも今年で還暦なので、先生役はもう無理でしょう(笑)。なにになっているのか、近所のおじさんかもしれないし」
平山「お化けがいいんじゃないですかね?(笑)」
野村「いいですね(笑)」