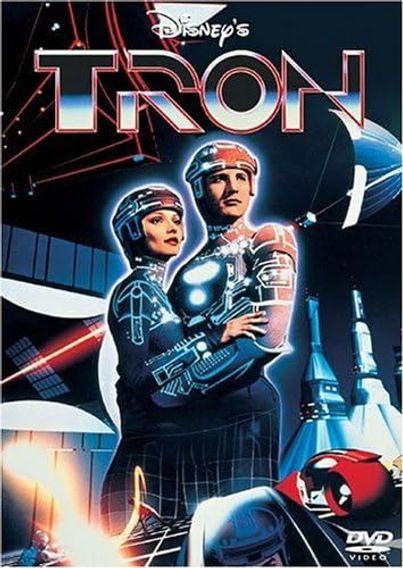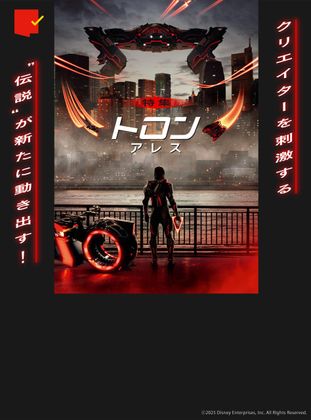ナイン・インチ・ネイルズが電子の神殿に降臨!『トロン:アレス』で導きだした次世代につながるエレクトロ・ミュージック
トレント・レズナーと彼の右腕アッティカス・ロスが“電子の神殿”へと降臨した。AIプログラムがコンピュータの内部から現実世界を侵食していく――サイバーSF映画『トロン:アレス』(公開中)のオリジナルサウンドトラックが、その降臨の記録である。
ナイン・インチ・ネイルズとして伝説を背負ったトレント・レズナー&アッティカス・ロス
初めての挑戦でアカデミー作曲賞を獲得した『ソーシャル・ネットワーク』(10)以来、2人はデヴィッド・フィンチャーやルカ・グァダニーノの監督作を筆頭に膨大な数の映画音楽を手掛けてきたが、本作で特筆すべきは、初めて「ナイン・インチ・ネイルズ(NIN)」名義を掲げたことだ。このアイデア自体はディズニー側の提案によるものだというが、2人にもその名を使うだけの確信があったはずだ。
そもそもNINは「ザ・ダウンワード・スパイラル」や「ザ・フラジャイル」といった初期の代表作において、“人間の存在意義”というテーマを掘り下げてきた。『トロン:アレス』が描く“感情を吹き込まれた人工生命の存在意義”という主題は、その延長線上にある。しかも「トロン」シリーズの音楽は、常にエレクトロ・ミュージックの伝説が手掛けてきた。
第1作『トロン』(82)はシンセサイザー音楽で初めてのヒットアルバムである「スイッチト・オン・バッハ」で知られるウェンディ・カーロスが、そして再起動作『トロン:レガシー』(10)はダフト・パンクが担当している。NIN名義を避けるのは“逃げ”ととられる可能性もある。レズナーとロスは、伝説を背負う覚悟を決めたのだ。
エレクトロ・ミュージック史を横断しながら次世代につながるサウンドに
その覚悟はサウンドに如実に表れている。カーロスやダフト・パンクがスケール感を醸しだすために、生のオーケストラを融合させていたのに対し、NINは電子楽器のみで壮大かつ重厚さをあわせ持ったスコアを構築している。その音楽的要素は、カーロスが手掛けたスタンリー・キューブリック監督作『時計じかけのオレンジ』(71)のサウンドトラックから、デヴィッド・ボウイが1977年に発表した傑作「ロウ」のB面、映画内でも言及されているデペッシュ・モードをはじめとする80年代エレポップ、さらには90年代レイヴやインダストリアル・ロックまで、1970年代以降のエレクトロ・ミュージック史を横断したもの。
だがそれは決して懐古的なものではない。ツアーを共同で行ったボーイズ・ノイズやハドソン・モホークといった後輩アーティストを全面参加させ、次世代につながるエレクトロ・ミュージックとして昇華しているのだ。