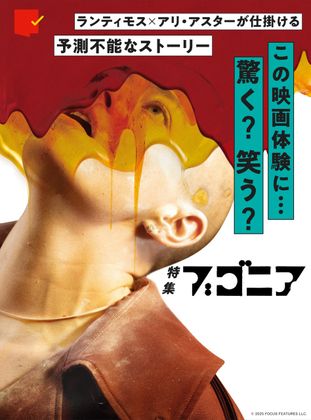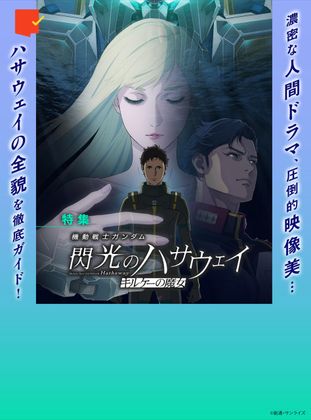“Jホラーの申し子”近藤亮太監督と大森時生が『テレビの中に入りたい』を絶賛!「最新のダウナーな青春映画」
第74回ベルリン国際映画祭パノラマ部門正式出品のA24製作映画『テレビの中に入りたい』の公開記念トークショー付き上映会が、10月5日にkino cinema新宿で開催された。「第2回日本ホラー映画大賞」で大賞を受賞し、今年1月に『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』(24)で商業映画監督デビューを飾った“Jホラーの申し子”近藤亮太監督と、SNSで幾度もトレンド1位を記録している「TXQ FICTION」の仕掛け人であり、企画を手掛けた「恐怖心展」が動員13万人を記録するなど話題作を連発する、テレビ東京の大森時生プロデューサーが登壇。近藤監督が「最新のダウナーな青春映画」と、大森プロデューサーは「自分のアイデンティティを見つけるような作品」と感想を語った。
本作は、90年代のアメリカ郊外を舞台に、自分のアイデンティティにもがく若者たちが自分探しをしていくメランコリックスリラー。現地アメリカでの上映時は、若いファンを中心とした考察が始まり、SNSが非常に盛り上がった本作。日本でも9月26日より公開がスタートし、「今年のベスト」「超絶大傑作」「ぶっ刺さって抜けない」「情緒ぐしゃぐしゃ」といった非常に熱い感想が出ている。
「TXQ FICTION」「恐怖心展」などで幾度も共作している近藤監督と大森プロデューサーは、登場から終始息ピッタリ。まず本作の感想について、近藤監督は「昔懐かしい80年代90年代作品の雰囲気と、そこに絡む青春模様のような感じのノリなのかなと思っていたら全然違う映画で、もっとよりメランコリックな、一番最初に僕が世代的に思い浮かんだのは『ドニー・ダーコ』という映画でした。青春時代の鬱屈した想いのようなものを映像表現として落としこんでいて、それがいまの2025年のモードとして最新のダウナーな青春映画になっている。その表現の新しさとおもしろさが、かなりすごいなと思いました」と称える。
大森プロデューサーも「この作品は全体的に、自分のアイデンティティを見つけるみたいな作品。そのうえで、自分のアイデンティティをなにをもって見つけるのか、そもそも見つけることが大切なのかとか、見つけた結果幸せになるのかってことも、すべて曖昧にされているのが新しい。アイデンティティを求める作品というのは、だいたい最終的にそれを見つけたことによって成長するみたいな物語が一般的にはよくあると思うんですけど、まったくそうじゃないっていうのも含めて、それが現代的だなとすごく思いました。やっぱりアイデンティティを見つけようと思っても、見つけようがない時代というか。自分のなかでこれがいいかもと思ったことも、SNSとかを見たら自分よりはるかに得意だったり、それをアイデンティティにしている人がもう1万人とか見つけられちゃうわけなので、その時代におけるアイデンティティを求める物語としては、すごい妥当な感じがするというか、そこが僕は一番刺さった部分かもしれないですね」とコメント。
また、アメリカでは“サイコロジカルホラー”という言い方をされている本作は、日本人が想像するいわゆる“ホラー映画”とは異なる印象で違った感覚の作品となる。大森プロデューサーも「生きていて、自分のなかでなにかにぶつかったり、精神的な落ち込みのなかに入ってそこから戻ってこなかったり、途中でなにかアイデンティ的なものを見失って暗くなってしまって、そのまま帰ってこないみたいなことっていうのは、まさに本作で書かれている怖さとすごく近いなと思って、リアルなホラーだと思いましたね。サイコロジカルは精神的なっていうような意味だと思いますけど、それぐらい本当にありそうな怖さ」だと指摘する。
近藤監督も「たぶん、それぞれが自分の人生のなかで触れてきたなにかをちょっと仮託しながら、その思い出とともに見ているような感じがあるんでしょうね」と分析する。大森プロデューサーも「自分の記憶だったり、自分のなかのノスタルジーだったり、自分のなかでなにかを失った経験みたいなものと妙に接続するというのが、この映画の魅力かもしれません。しかも全部35mmで撮られているので、質感とかが全部夢のなかみたいなんですよね。それがけっこうこの作品を特殊なものにしているところなのかなとも思いました」とも語った。
そして、ホラー映画を手掛ける近藤監督は、本作のジェーン・シェーンブルン監督のアプローチについて「例えば『死霊館』シリーズのようになるべく詰め込んでいくホラー映画とは違って、考える時間を逆に長く取るというアプローチの仕方。余白がすごくあるので、人によっては退屈と思われるぐらいの尺を割くのですが、その代わりにいろんな想いを想像したり、思い返したりするということを込みで鑑賞体験としている。アートですよね。観終わったあとに誰かと感想を話したりしている時に真価を発揮するようなタイプの映画でもある。それを演出や物語構成としても意図的にやってるということなのかなと思って、それは現代のイケてる作り手のやることとしてすごいなと思いました」とその手腕を絶賛した。
さらに、ラストは衝撃的な展開となる本作だが、大森プロデューサーは「やっぱりどこまでも行っても、『テレビの中に入りたい』は、取り返しのつかなさに関する話でもあると思います。人によって規模は違いますが、例えば人生である人と出会って、その人と一時期仲良くしたけど、なにかしらで取り返しがつかなくなって、完全に離れ離れになったみたいな記憶は、たぶん誰しも1つぐらいはあるものです。その取り返しのつかなさが身につまされるから、本作の最後は急にグッと自分のほうに向かうというか、作中ずっとぼんやり自分のこととかも考える時間も与えられているような映画なので、それプラス最後のラストで急に自分ごととして引き寄せてしまうから、『最終的にどうしようかな』みたいな気持ちになって、映画が終わるという効果があるのかな、と思ったりしました」と語った。
最後には、近藤監督が本作について「賛否いろいろあったりもするかもしれないし、なかなかすぐぱっと感想を言える作品ではないかもしれないんですけど、感想をいろいろ共有していくなかで発見や気づきがある作品だと思います。一旦整理できてから、もう1回繰り返すことによっておもしろいタイプの作品。そういう形で、理解していったりしてほしいと思います。あとパンフレットがめちゃくちゃ出来が良かったので、ぜひご覧ください!」と呼びかける。
大森プロデューサーも「自分のなかの記憶とすり合わせるように見ると、すごい作品だったのかなと思います。このようなトークショーがある上映ではなく、あのラストが終わってそのまま浸る時間があるバージョンも楽しいと思うので、ぜひ皆さん2回目以降も観ていただきたいです!」とメッセージをおくった。
文/山崎伸子
※記事初出時、登壇者の発言箇所に誤字がありました。訂正してお詫びいたします。