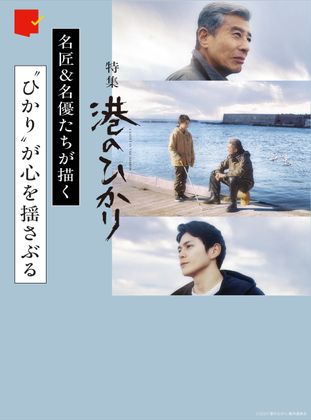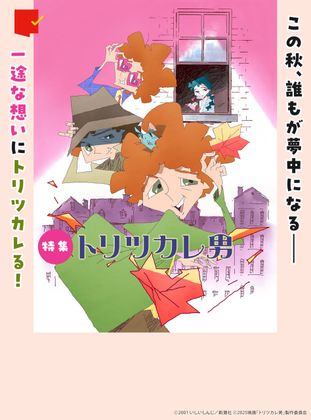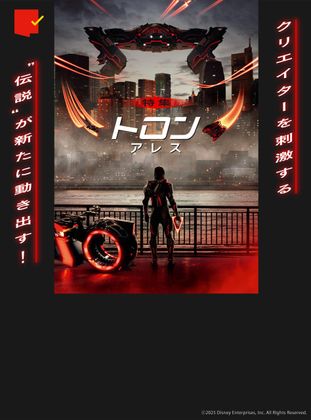チェーザレ・パヴェーゼの名作を映画化した『美しい夏』に、イタリア文学の専門家が太鼓判!「パヴェーゼは確実に嫉妬した」
20世紀イタリア文学を代表するチェーザレ・パヴェーゼが1940年に執筆し1949年に出版された同名小説を、70年以上の時を経てラウラ・ルケッティ監督が映画化した『美しい夏』(8月1日公開)。本作の公開記念試写会とトークイベントが7月15日に日比谷図書文化館にて開催され、イタリア文学者で東京外国語大学名誉教授の和田忠彦と、イタリア文学研究者の渡辺由利子が登壇した。
本作の舞台は1938年、戦争の影が忍び寄るイタリアのトリノ。田舎から出てきてお針子として洋裁店で働く16歳の少女ジーニア(イーレ・ヴィアネッロ)は、3つ年上の美しく自由なアメーリア(ディーヴァ・カッセル)と出会う。画家のモデルとして生計を立てる彼女によって、大人の階段をのぼりはじめるジーニア。2人は互いの姿に自分の過去と未来を映しながら、徐々に惹かれあっていく。
1950年にイタリア最高峰の文学賞であるストレーガ賞を受賞した原作について渡辺は「原作にはなにが起きているのかわからないような描写が多い。でも、その控えめな書きかたのなかにこそ魅力があった」と振り返り、原作には描かれていない感情や状況が丁寧に加えられた本作に「最初は違和感を覚えた」と述懐。その上で「原作の“へこみ”と映画の“ふくらみ”が、デコボコしながらもぴったり噛みあっているように感じました」と、原作と映画が互いに補完しあうことで、新たな魅力が生まれたと評価する。
一方で和田は、ジーニアが出会うアメーリアの描きかたに注目し、「原作では映画ほどの存在感はなかった。パヴェーゼは女性を描けない作家だった。そこを監督のラウラ・ルケッティが、女性を前面に押しだすかたちで再構成している」と分析。「もしパヴェーゼがこの映画を観たら、不機嫌になっただろう。『自分よりうまく描いているじゃないか』って。彼が描きたかったのはこういうことだったのかもしれない。確実に嫉妬したと思います」と、会場の笑いを誘いながら、脚本も手掛けたルケッティ監督の脚色力に賛辞をおくった。
さらに和田は、パヴェーゼの「孤独な女たちと」を原作にしたミケランジェロ・アントニオーニ監督の『女ともだち』(55)にも言及。「『美しい夏』を観た時に、『女ともだち』で映しだされた女性たちの姿やトリノの街が重なって見えた。ルケッティ監督は、ある意味でアントニオーニへのオマージュも込めているのではないだろうか」と語り、それを受けて渡辺も、映画オリジナルで描かれた洋裁店でのジーニアと店主のシーンを挙げながら「アントニオーニを意識していると思いました」と同意。
物語の舞台であるトリノについて話題が移ると、和田は「フランス文化の影響が強く、計画都市として築かれた点でローマやフィレンツェとは異なる独自の空気を持つ」と説明。「パヴェーゼの作品には、故郷であるランゲの丘陵地帯と都市トリノという二項対立があり、そのなかで自分の居場所を探しつづけている。今回の映画でルケッティ監督は、その主題を丁寧にすくいとっていた」と、改めて評価。
また時代設定の1938年が、ファシズム政権下のイタリアで人種法が施行された年であることにも触れ、「映画のなかでムッソリーニの演説が窓の外から聞こえ、ジーニアがそれを疎ましそうにして窓を閉めるシーンがある。あれは1938年8月に実際にトリエステで行われた演説を再現している」と指摘。挿入歌なども含め、当時の空気感をリアルに再現した時代考証が物語の背景理解を深めるうえで重要な役割を果たしていると語り、「本作を機会に原作やイタリア文学に興味を持ってもらえたらうれしいです」と締めくくった。
文/久保田 和馬