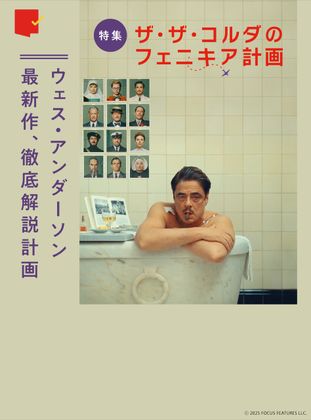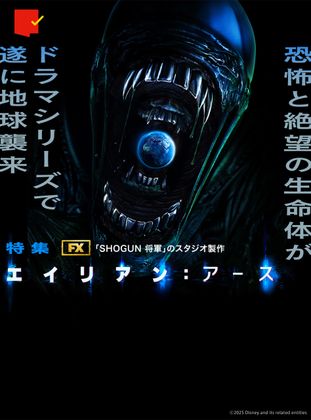是枝裕和監督に独占インタビュー。”普段はやらない”試みだらけの『ラストシーン』で探求する、技術革新と人間性の調和
「すごく少人数で、役者とスタッフも3人だけで、あの親密な感じはやっぱりなかなかないです」
小型カメラの最大の強みは、観覧車のシーンに表れている。是枝監督は、iPhoneの特性を活かし狭い空間での撮影を念頭に脚本を書いたそうだ。「iPhoneで撮るのが一つのチャレンジだから、逆に言うと、すごく映画的なカット割りをしています。いつもはあまりやらないほぼ2人だけの芝居なので、フィルムのカメラだと入りにくいところ、車の中とか観覧車など、狭い空間で展開しようと思って脚本を書きました」と言う。『ベイビー・ブローカー』で観覧車のシーンを撮影した際は、俳優と撮影スタッフだけでコンパートメントに乗り込んだ。
「韓国では、地上でモニターを見ていたら、観覧車が上がっていくと無線が届かなくなっちゃって、降りてくるまでなにがどう撮れているのかさっぱりわからなくて、すごいストレスだった。あのお芝居に立ち会いたかったなあ、と思っていたから。今回は一緒に乗り込みまして、とても個人的なリベンジです(笑)」と笑う。韓国では断念した観覧車での撮影に、「小さなカメラだから」というシンプルな理由で今回は立ち会うことができた。「すごく少人数で、役者とスタッフも3人だけで、あの親密な感じはやっぱりなかなかないです。大きな(フィルム用の)カメラだと難しいかな。あのシーンに関して言うと、カメラの存在が消えたのはすごく良かったって、(役者の)2人とも言ってましたね」と満足感を示している。
ドキュメンタリー出身の是枝監督は、「カメラを意識させないで撮るのであれば、ドキュメンタリーや子どもを撮るときは、iPhoneはすごく適していると思う。僕はあまりやらないけど、マルチで撮るのでも、すごくおもしろいものが撮れる可能性がありますね。iPhoneを20台仕込んで、ワンシチュエーションのドラマを舞台みたいに一発撮りするみたいな」と、新しい企画にも胸を踊らせる。
第四の挑戦は、昨今多く見られるタイムトラベルという題材に是枝流の哲学を注入したことだ。古典的なタイムトラベル作品が「過去をやり直したい」という願望を描くのに対し、是枝監督は「過去は変えられないが、現在の選択で未来は変えられる」という視点を提示した。「古典の『素晴らしき哉、人生!』もそうですが、人生をやり直したいっていう思いは、誰の中にも後悔として必ずあるでしょう。人生は1回だって考えてない人もいるかもしれないけど、そうするとどうしても、過去に戻ってやり直したいって気持ちになるじゃない。でも、そうじゃない話にしたいなと思ったんです。いまの自分が未来を変えられるんだという。感情の方向性としては、ベクトルとしてはそっちへ持っていきたいなと思って脚本を書きました。過去は変えられないけれど、解釈は変えることができる、と」。
この哲学は、是枝監督自身の日常生活にも現れている。「旅先でも、ロケ先でも、なるべく町の本屋で本を買うようにしてます。この間も秋田にロケに行っている2か月の間に30冊買ったんです。もちろん読めてないんですけど。帰りの荷物が大変なことになりました(笑)。買わないと本屋が消えてしまうっていうふうに思わないと、街の本屋とチェーン店ではない喫茶店は消えちゃいますよね。なるべく喫茶店で飲んで、本屋で買った本を読む。それは自分の中で大事にしてる場所と時間です」。そういった小さな選択を意識的に行うことが大切だと語る。「ドラマが消えてなくなる」未来から来た由比と共に、自分が大切にしているものを守る未来を作ろうとする倉田。是枝監督の消えゆく文化を守ろうとする思いは、今作のテーマにつながっている。
最新のデジタル技術を駆使しながらも映画や文化の本質を問い続ける是枝監督の探求は、この短編作品を通じて、技術革新と人間性の調和という永遠のテーマに新たな光を投げかけるものとなった。
取材・文/平井伊都子