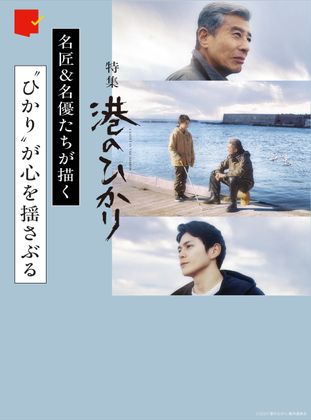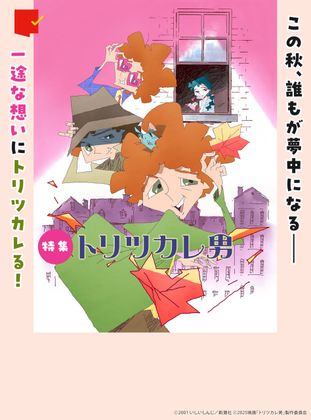【ネタバレレビュー】「キャシアン・アンドー」シーズン2前半戦を総括&後半戦予想!モン・モスマはついに反乱軍リーダーに?ロマンスの行方は?
「スター・ウォーズ」ドラマシリーズ最新作「スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー」のシーズン2がディズニープラスで独占配信中だ。『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』(以下、『ローグ・ワン』)で強烈な印象を残した反乱同盟軍の情報将校キャシアン・アンドー(ディエゴ・ルナ)の素顔を描く本作。シーズン2全12話の折り返しを迎え、完結まで残すところあと6話に迫ってきた。そこでシリーズを振り返り、『ローグ・ワン』へとつながる後半の見どころをチェックしたい。
※本記事は、シーズン2第6話までのネタバレ(ストーリーの核心に触れる記述)に該当する要素を含みます。未見の方はご注意ください。
トニー・ギルロイの手腕が光る、これまでになかったストーリーテリング
まずはドラマの概要に触れておこう。『スター・ウォーズ/新たなる希望(エピソード4)』(77)で初代デス・スターを破壊した“ヤヴィンの戦い”、その勝利に導くきっかけとなる名もなき戦士を描いた『ローグ・ワン』で、主人公ジン・アーソを支えたキャシアン・アンドーのバックグラウンドを描く本作。映画の中で「反乱軍のために汚れ仕事をしてきた」と語ったキャシアンの、反乱軍に参加したいきさつや私生活、過酷な任務の日々がスリルとアクションを交えて描かれる。キャシアンのほかにもテロリストのソウ・ゲレラ(フォレスト・ウィテカー)や帝国の超兵器デス・スター開発を指揮したオーソン・クレニック(ベン・メンデルソーン)、モン・モスマ元老院議員(ジェネヴィーヴ・オーライリー)など『ローグ・ワン』や「スター・ウォーズ」シリーズでお馴染みのキャラクターも登場する。
なかでも注目は、のちにリーダーとして反乱軍を率いるモスマ元老院議員。『スター・ウォーズ/ジェダイの帰還(エピソード6)』(83)で初登場して以来、様々な作品に顔を出してきた彼女が、本作では議員・妻・母の顔を使い分けながら反乱軍のために奔走する姿が描かれる。裏の仕事を担うキャシアンや資金面で支えるモスマと、これまでにない視点から反乱軍を切り取っているのもおもしろい。
脚本を手掛けたのは、キャスリーン・ケネディらと共に製作総指揮に名を連ねたトニー・ギルロイ。『ローグ・ワン』では共同脚本のほか追加撮影など全編に深く関わった彼は、マット・デイモン主演の「ジェイソン・ボーン」シリーズで知られる脚本の名手。得意とするハードなストーリーテリングは、本作でも生かされた。ギルロイはアカデミー監督賞にノミネートされた『フィクサー』(07)や『ボーン・レガシー』(12)など映画監督としても高い評価を得ているが、本作では脚本や製作の立場で作品全体に目を光らせている。
「スター・ウォーズ」らしからぬテーマが、リアリティあふれる重厚なドラマを生みだす
キャシアンが反乱軍に加わるまでを描いたシーズン1は“ヤヴィンの戦いの5年前”、つまり『ローグ・ワン』や『スター・ウォーズ/新たなる希望(エピソード4)』の5年前という設定だったが、シーズン2はその1年後、“ヤヴィンの戦いの4年前”から幕を開ける。シーズン2では構成が変更され、3話分を1つの章に見立て全4章で完結するスタイルになっている。1章ごとがまるで1本の映画のようなスタイルに心躍ったファンも多いと思う。
第1話で、反乱軍のアクシスことルーセン・レイエル(ステラン・スカルスガルド)のもとで暗躍するキャシアンは、兵器開発施設に潜入し新型タイ・ファイターを盗みだすことに成功する。その後、惑星ミーナ=ラウで不法移民として暮らしていた幼なじみビックス(アドリア・アルホナ)たちと合流。帝国軍の攻撃をかわし、ミーナ=ラウからの脱出に成功した。一方、惑星シャンドリラでは、反乱軍の資金繰りに息詰まっていたモスマが、14歳になった娘を裕福なスカルダン(リチャード・ディレイン)の息子に嫁がせることで、なんとか窮地を抜けだした。
ここまでがシーズン2の1~3話の物語だ。キャシアンはルーセンの元で工作員として数々のミッションをこなし、右腕的な存在へと成長。6話でルーセンはキャシアンに、「いち兵士ではなくリーダーとして物事を見るべきだ」と期待の高さを伺わせる台詞も口にする。しかし反乱軍の内情も不安定で、タイ・ファイターを盗んだキャシアンが最初に立ち寄った惑星では、偶然に合流したマヤ旅団がグループ内で些細なことをきっかけに対立。同じ反乱軍でありながら殺し合いをする様も描かれた。目標達成のためなら仲間でも排除する反乱軍の暗部に切り込むシビアな展開にも、“トニー・ギルロイらしさ”がにじんでいる。さらに3話には、ビックスに目を付けた帝国軍将校による性的暴行未遂シーンも描かれている。「スター・ウォーズ」でこういったテーマを扱うことに驚かされたが、戦争の惨状や人権を否定する行為に正面から向き合う姿勢は評価したい。