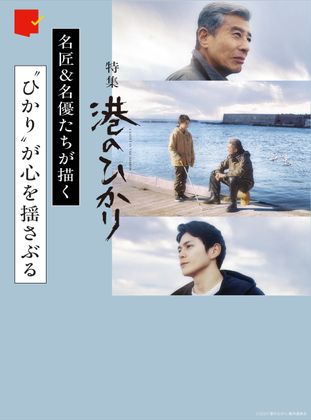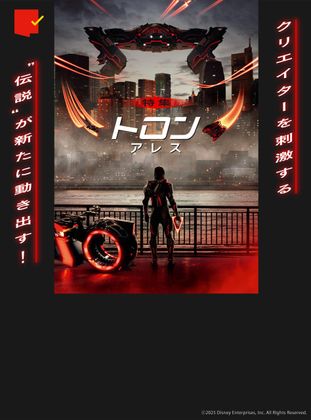渡部陽一&LiLiCo、実在の報道写真家リー・ミラーの生き様に感銘!「カメラマンとして惹きつけられた」「やりたいと思ったら進むべき」
『シビル・ウォー アメリカ最後の日』(24)の主人公のモデルにもなった、実在の人物の数奇な運命を映画化した『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』(5月9日公開)。本作のトークショー付きプレミアム先行試写会が5月1日にユーロライブで行われ、戦場カメラマンの渡部陽一とタレントで映画コメンテーターのLiLiCoが出席した。
トップモデルから報道写真家に転身し、第二次世界大戦が始まると、凄まじい情熱とエネルギーで戦争の最前線を駆け抜けたリー・ミラーの姿を描く本作。彼女の生き方に大きく感銘したケイト・ウィンスレットが製作総指揮、主演を務めた。
本作を鑑賞した2人は、それぞれカメラマン、女性という立場からも感銘する点が多かったという。「戦場カメラマンとして、現代の戦争、ウクライナやガザ、アフガニスタン、イラク、シリアなどの最前線を動いてきた」という渡部は、「映画では第二次世界大戦という過去の戦争が描かれていて。当時はいかに武力を全面に出した戦争の時代であったのか。そこに従軍するカメラマンは、カメラで撮影するだけではなく、いかに自分の命を差しだしていくような撮影の仕方を余儀なくされていた時代であったのかということを強く感じました」としみじみ。当時の戦場報道の背景が「作品からにじみ出ていた」とカメラマンとしても目を見張るような映画だったと話す。
「写真は、一生の記憶になる」と持論を述べたLiLiCoは、「戦争や紛争の現場では、なにが起きているのか。皆さんの写真がないと本当のことはわからない」と報道写真家の仕事の意義を口にしつつ、「ケイトがこういう役をやりたいというのも、よくわかる。自分の声を持っている俳優で、出ている作品もテーマ性のあるものが多い。ちゃんと自分でやりたいことを選んでいるところは、リーさんと似ているんじゃないかと思う」と製作総指揮も務めたウィンスレットが、ミラーの生き様に惹きつけられたことに納得の表情。ウィンスレットが演じるミラーが道を切り開いていく姿を「震えながら観ていた」そうで、「自分だったら『カメラマンとして行きますか?』と言われたら、『行きたい、伝えたい』という想いはあるけれど、勇気があるかどうかと言ったら考えてしまう。陽一さんはすごいと思う」と命をかけて戦場に飛び込む写真家たちに敬意を表した。
すると渡部は、「戦場報道には、大きく分けて2つのスタイルがある。ひとつは、戦場の兵士に同行して、兵士と共に動いていく従軍カメラマン。もうひとつは、戦場となった町に暮らしている方々の生活に入り込み、それを記録する方法です」と紹介。「リー・ミラーさんの撮影の手法は、もともとファッションやポートレートを手掛けていたこともあり、シルエットや美しさを大切にしています。戦場に入り、もちろん銃撃の激しさを撮っていくんですが、戦場に立たされた子どもたちや、生活臭の残っている洗濯物など、“戦場のなかの日常”という切り口で、シルエットや色合い、写真が持っているエッジを立てて撮影していく。カメラマンとして惹きつけられる撮り方で、見ていてハッとさせられることが多かったです」とミラーの写真には、特別な魅力があると語った。
ミラーは、歴史的1枚と言われる“ヒトラーの浴室”を撮影した写真家としても知られている。“ヒトラーの浴室”は、アドルフ・ヒトラーが自殺した日に、ミラー自身が彼の浴室に入って撮った1枚だ。LiLiCoが「伝えるためにシャッターを押さなければいけないという、彼女の想いを感じた」と心を寄せると、渡部は「ほとんどのカメラマンは、自分が写ることはないんです。常に撮影をしていく側ですから。でもリーさんは自分自身がモデルだったので、撮られる側、撮る側という両方についてたくさんの時間と出会いを通して学んでいる。自分が被写体となることを理解して、構図や色合いなどもコントロールしたものとして残した。写真家としての力が全面に出た1枚」と彼女にしか残せなかった1枚だと力を込めた。
固定概念から自由になりたいという願望に従って多彩な人生を生きたミラーは、女性たちのリーダーとも言える存在だ。LiLiCoは「ケイトやミラーさんを見ていると、やりたいことに向かっていいんだよと思った。(ミラーが)モデルから戦場カメラマンになった時に、『どこに向かっているの?』と思った周囲の人もいると思う。でもいいんですよ。いろいろな顔を持って。やりたいなと思ったら、そこに進むべきだと思います。すごく強いメッセージを持つ、ステキな映画」と勇気をくれる映画だとアピール。「女性として、(突き進むことに)躊躇する時もある。でも自分が後悔のないようにやっていきたい。興味を持ったものには全力で向かっていきたい」と意欲をみなぎらせた。
「ゆっくり、一生懸命に毎日生きている」と柔らかな笑顔を見せた渡部も、「やっぱりやりたいことをやってみようと思いました」と本作から力をもらった様子。「世界情勢が荒れている2025年。改めて、ゆっくりであっても自分自身のペースで、繰り返し戦場に立たされた子どもたちや家族の声を、カメラマンとして記録に残していくという柱を再認識しました」と自身の進む道のりを確かめるように話していた。
取材・文/成田おり枝