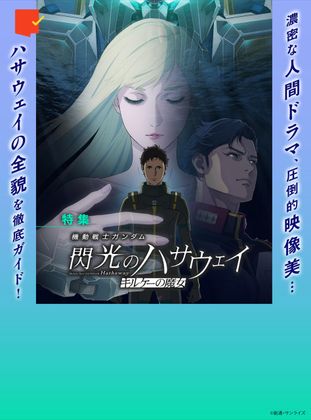日本映画の未来に向けて「映適」の輪が広がっている。3年目の目標は「議論をさらに深めていくこと」
2023年3月に設立された「一般社団法人日本映画制作適正化機構」の記者報告会が4月11日、東宝株式会社にて開催され、理事長の島谷能成(日本映画製作連盟 代表理事)、理事の浜田毅(日本映画撮影監督協会 代表理事)、同じく理事の新藤次郎(日本映画製作協会 理事)、幹事の小畑良治、顧問の佐藤直樹が出席し、2024年度の運用状況と今後の取り組みについて報告した。
「一般社団法人日本映画制作適正化機構(以下、「映適」)」は、日本映画製作者連盟、日本映画制作者協会、日本映像職能連合の合意により調印され設立。既存の各種法令において適法であることを前提に、映画制作者、制作会社(プロダクション)およびフリーランスによって、あらかじめ明示的に合意した条件を定めた「映画製作の持続的な発展に向けた取引ガイドライン」に基づき制作された”適正な作品”であることを認定する制度だ。
報告会には立ち上げメンバーの全員が集合していることが明かされ、さらに2023年に急に出来上がった制度のように捉えられがちだが、実は2019年10月ごろから、現場スタッフ、制作会社などさまざまなアンケート調査やヒアリングを通して浮かび上がった問題に対し、「(調べれば)もっといろいろな問題があるのではないか」という声からはじまり、4年間55回の会議で議論を重ねた結果として制定されたものであるとも伝えられた。
「映適」についてはネガティブな反応も多かったそうだが、スポンサーも公的助成金もないなか、2年間の活動で赤字を出すこともなく、地味ではありつつもひとつひとつの事務局による仕事、努力の積み重ねで、「徐々に良くなっている状況です」と報告。その変化、成長を踏まえた上で「映適」がどう変わっていくのか、そして「映適」を支えてもらいたいという思いで、賛助協会を立ち上げたことも報告し、「映適」3年目となる2025年度(2025年4月〜)からは賛助会員は合計70となり、日本映画の未来に向けて、「映適」の輪がさらに大きくなっているとしていた。
開始から3年目「まだまだ問題はある」としながらも、なにもルールがなかったところにガイドラインができたことは自慢できるとのこと。見直すべきところは見直そうと着々と進めている状況であるとし、3年目である今年の動き、変化こそ注目してほしいポイントとし、今年一年で議論をさらに深めていくとも宣言していた。
報告会では「作品認定制度」の申請から審査、認定までの流れを運用マニュアルに沿って解説。さらに作品認定制度の3年間のロードマップも公開し、3年目となる今年は認定プロセスを厳格化し、ベストプラクティスを共有することを目指しているとのこと。ベストプラクティスの例を挙げながら、現在の映画制作の現場での問題点に触れ、プリプロダクションに時間をかけること、(そのための予算配分増も必要になること)や現場スタッフによる状況報告がしやすくなるようデジタルツールを導入することなどが課題解決に向けた動きだと指摘。デジタルツールの導入検討については現場からの声がきっかけだったとし、認知という点では「スタッフセンター」のスタッフ登録者数を見てもまだまだ足りないと理解してはいるものの、改善に向けての現場からの声はうれしいものであるとも話していた。
取材・文/タナカシノブ