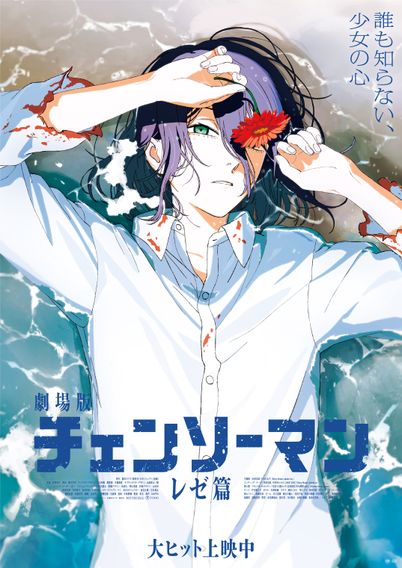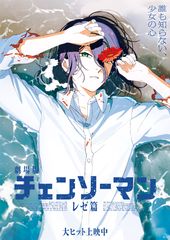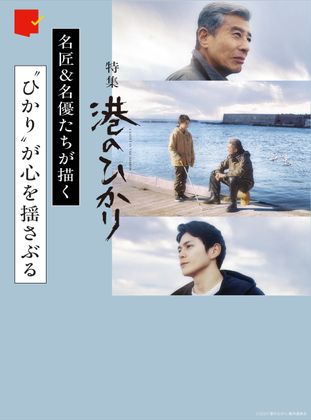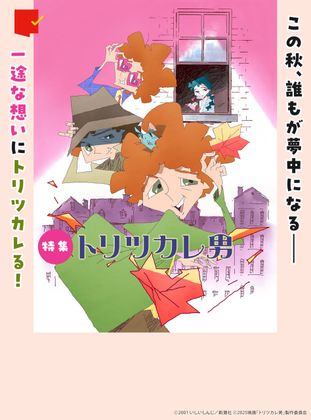日本の映画産業が”世界で最も堅牢”と評価される理由は?中川龍太郎監督作品から『チェンソーマン』まで語る、映画祭ディレクター座談会
2025年10月27日から11月5日まで、10日間にわたって開催された第38回東京国際映画祭では、コンペティション部門のほかに、アジアの未来、ガラ・セレクション、ワールド・フォーカス、ウィメンズ・エンパワーメントなど様々な部門に世界各国の映画が、ニッポン・シネマ・ナウや日本映画クラシックスには、新作から過去の名作まで様々な日本映画がプログラムされている。映画祭のもう一つの顔として、世界各国から映画関係者が集まる交流の場がある。
MOVIE WALKER PRESSでは毎年、東京国際映画祭を訪れる“映画祭のプロフェッショナル”たちのインタビューをお届けしている。今年は、ウディネ・ファーイースト映画祭の創設者でフェスティバルプレジデントのサブリナ・バラチェッティ氏、バラチェッティ氏と共に映画祭を運営し、配給会社Tucker FilmのCEOを務めるトーマス・ベルタッケ氏、そして韓国の釜山国際映画祭のフェスティバル・ディレクターのチョン・ハンソク氏の3名を迎え、映画祭の役割や世界における日本映画の現在地について語ってもらった。
「東京国際映画祭のセレクションに驚きが多く、なにが出てくるかわからないおもしろさがある」(バラチェッティ)
――東京国際映画祭(TIFF)には、いままで何回いらっしゃっていますか?
トーマス・ベルタッケ(以下、ベルタッケ)「最初に来たのは1999年の、渋谷で開催していた頃だと記憶しています。4回目くらいだと思います」
サブリナ・バラチェッティ(以下、バラチェッティ)「2001年が最初です。映画祭参加はもちろんですが、映画の制作陣の皆さんに会いに来たのが最初でした。2010年以降は、TIFFもそうですし、TIFFCOM(コンテンツマーケット)のほうにも毎年来ています」
チョン・ハンソク(以下、チョン)「私は、東京国際映画祭に来るのは今年が初めてです。でも、これまで東京国際映画祭がすばらしい映画祭だということは、たびたび聞いていました。以前は(韓国の映画雑誌)『CINE21』誌で記者をやっていたので、ほかの映画に関連するイベントには来ています。 例えば、2004年に蓮實重彦先生が小津安二郎生誕百周年記念のイベントを開催された時にも取材に来ましたし、日本の監督やクリエイターの方々に取材するために日本を訪れています」
――東京国際映画祭にいらっしゃっている間に、絶対にこれだけは見逃せないという映画があれば教えてください。
バラチェッティ「まず、TIFFのコンペティション部門はほかの映画祭と比べても、セレクションに驚きが多く、なにが出てくるかわからないおもしろさがあると思うんです。新作映画や新進監督を巧みに組み合わせる能力に長けています。例えば、コンペティション部門にドキュメンタリー作品が選出されているところなど。そのため、この部門の全作品を追うのは常に非常に興味深いです。また、もう一つ今年楽しみにしているのは、山田洋次監督の『TOKYOタクシー』です。倍賞千恵子さんが『TOKYOタクシー』に出ていらっしゃいますが、数年前、私たちの映画祭にスペシャルゲストとしていらしてくださいました。イタリアへお招きし、生涯功労賞を授与しました」
バラチェッティ「コンペティション部門では、中川龍太郎監督の『恒星の向こう側(Echoes of Motherhood)』という作品もあります。2022年に、中川監督の『やがて海へと届く』を私たちの映画祭で上映したご縁もあり、すごく楽しみにしています。日本のクラシック映画を観るのも、すごく楽しみにしています。イタリアでは、日本の古い映画を観るのがとても難しいので、この機会に大きなスクリーンで観られたらいいなと思っています」
ベルタッケ「それに、私たちはイタリアで日本映画を配給しているので興味があります。いままでイタリアでは11本の日本映画を公開しており、そのうち3本は相米慎二監督や黒澤明監督の作品でした。今後は日本の古典映画の公開を検討しています」
チョン 「9月に開催した釜山国際映画祭で、私たちも新たにコンペティション部門を設け、最高賞を中国のチャン・リュル監督に授与しました。 今年の東京国際映画祭でも、チャン・リュル監督が『春の木(Mothertongue)』という作品を出品しています。釜山受賞作の『Gloaming in Luomu』は『春の木(Mothertongue)』よりあとに制作された映画なんですが、釜山で先に公開され、『春の木(Mothertongue)』があとに行われたTIFFで上映されることになります。この2つの作品はかなり関連性があるということでしたので、観たいと思っています。
それから、ぜひ観たい作品が3作品あって、マレーシアの『母なる大地(Mother Bhumi)』(チャン・シーアン監督)、中川龍太郎監督の『恒星の向こう側』、ベルギーと北マケドニアの『マザー(Mother)』(テオナ・ストゥガル・ミテフスカ監督)に注目していました。偶然にもすべて”Mother”が入っていますね(笑)。
今年、アジアで開催された映画祭を開催する立場から言わせていただきますと、中国のチャン・リュル監督作品が2本、東京と釜山で一作ずつ、それもワールドプレミアで公開されることは、記録に残すべき出来事だと思います。この時代を代表する監督の作品がアジアを代表する2つの映画祭で、同時期に初公開されました。これは極めて意義深いことだと思っています」
「映画祭が持っている現場性、フェスティバル性としての映画祭がいかに重要であったかに気付きました」(チョン)
――チョン・ハンソクさんはフェスティバルディレクター、そしてサブリナさんはフェスティバルプレジデントというポジションですが、この映画祭のお仕事に就くきっかけになったことを教えてください。映画祭のプログラマーのどんなところを楽しんでいらっしゃいますか?
バラチェッティ「私たち(私とトーマス)は、イタリアの文化協会で長年一緒に活動してきました。私たちの町では2つの映画館を運営しています。映画祭を始める前は、特にイタリアやヨーロッパのジャンルの映画配給に力を入れていました。しかし、世界中のほかの地域、特に東アジアや極東にも重要な映画産業があることに気付き、視野を広げることにしたのです。例えば1990年代後半の香港は当時、より強力な映画産業を擁していました。彼らは多種多様なジャンルの映画を数多く生みだしていたのです。そこで私たちは香港に目を向け、新たな映画祭を始めることにしました。こうしてウーディネ・ファーイースト映画祭を創設し、同時に研究や調査も試みていったのです」
チョン「私の場合、長年『CINE21』で映画ジャーナリストとして働いてきました。そして2019年に釜山国際映画祭から協力の申し出を受け、韓国映画を担当するプログラム責任者になりました。いまの仕事に携わって得た喜びというのは、コロナのパンデミックが過ぎてみると、映画祭が持っている現場性というか、フェスティバル性としての映画祭がいかに重要であったかということに気付きました。人と人が集って、楽しい時間を過ごすという事実。その事実がいかに貴重なことであったかということを、改めて感じることができました。 映画祭というのは、人が集まって映画を観て、映画について会話したり、分かち合ったりするということです。それは私だけではなく、ほかの映画に携わっている人々もそう感じたのではと思いました。
先日、シッチェス・カタロニア映画祭に参加してきまして、映画祭スローガンも”ミーティングポイントになる”ということでしたし、東京国際映画祭のチェアマンである安藤(裕康)さんのインタビューでは、ネットワークを強調なさっているように感じました。ですから、サブリナさんやトーマスさんも映画祭の本来の役割を指摘してくださったのでしょう。私はお2人よりも映画祭における経歴ははるかに少ないんですけれども、ウディネ・ファーイースト映画祭は、とてもすばらしいことをやっていらっしゃると思います。映画を集めるだけではなくて、そこから多くの楽しさを得られる機会を作ってくださったと思います。映画に携わる人々を集め、出会いを作るという。映画祭はそういう役割を果たすことができればいいのではないかと思い、喜びを見出しています」